池田龍雄 オーラル・ヒストリー 第1回
2009年2月11日
吉祥寺ルノアールにて
インタヴュアー:西澤晴美、坂上しのぶ
書き起こし:坂上しのぶ
公開日:2009年6月1日
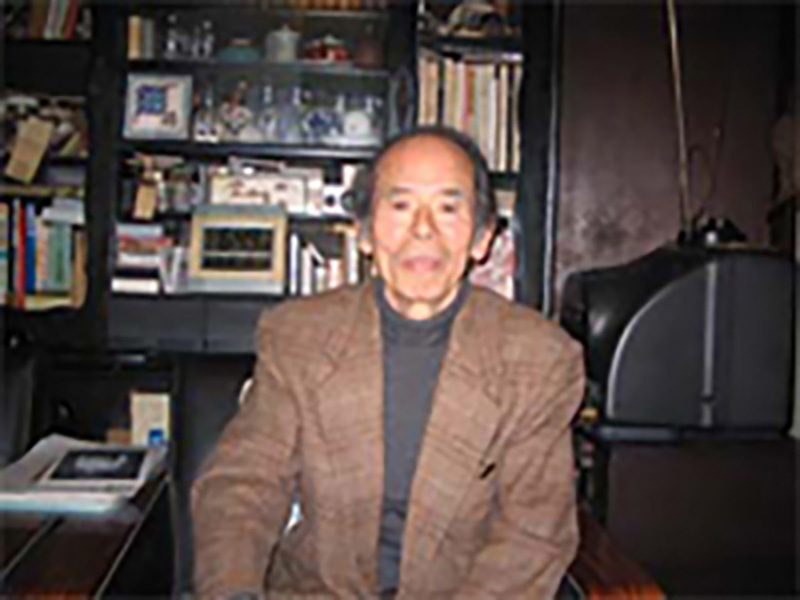
美術家
佐賀県伊万里に生まれ、特攻隊員として過ごした戦争の時代。戦後、画家をめざして上京。多摩美術大学に入学し、アバンギャルド芸術の道を切り開いていく。河原温、粕三平、松澤宥らとの交流から、前衛美術への熱い想いまで、1950年代、1960年代、1970年代の話を中心に、第二次大戦後一貫して反戦の意思を貫き続ける作家の人生が語られたインタヴュー。
池田:去年の11月頃に『視覚の外縁』という本が出たんです。『芸術アヴァンギャルドの背中』(2001年)と同じ沖積社からね。これが僕の最後の本だ、ということで5冊目を出したんです。前に赤瀬川君の千円札論みたいなのを書いた事があってそれをそこに収録しているんですよ。
千円札裁判が終わって間もなくの頃ね、その頃僕は世田谷に住んでいたんです。そこには大家さんの玄関じゃない別の入り口があって、アトリエに使えるくらいの12畳くらいの洋間、そこを借りて使っていたんです。そこで仕事してたら、玄関のところでごそごそって音がしたから、誰か来たかなと思ってふっと見たら誰もいないんです。それで何かと思ったら、誰かが玄関のドアの隙間に封筒みたいなものを差し込んでそのまますっと行っちゃったんです。何かと思ったら、赤瀬川原平の手紙でね。和紙に墨で字が、候文で書いてあった。後で聞いてみるとお父さんが書いたそうで達筆でねえ。「千円札裁判ではお世話になりました。つきましてはささやかなお礼を差し上げます」みたいな感じの事がそこには候文で書いてあってね。それが昔の「上意!」って感じの古風な紙の折り方で折ってあって。コピーじゃなかったですね。一枚一枚、千円札裁判でお世話になった人たちに書いていったんでしょうねえ。ふと見たら木の葉が一枚入っているんですよ。だから僕はね、それに早速ローラーで絵具をつけて和紙に刷りとってね。「ありがとうございました。今は木の葉に化けてるけれども、いずれは元の小判に戻りますのでお返しします」って言って返したんですよ。でもその木の葉いつの間にかなくなってしまった。100年後には元の小判に戻るはずだと今でも思っているんですがね。そんな事も文章に書いてます。
坂上:それではインタビューを開始したいと思います。池田さんは佐賀県伊万里でお生まれになりました。その頃の話からお聞きしたいと思います。
池田:僕は昭和3年8月15日生まれです。
西暦で1928年という年です。翌年29年が世界の大暴落、今と似てる。大恐慌で、てんやわんやになって。結局それが原因になって戦争に入っていくんですね。要するに今もそうなる恐れがあるんですよ。それは第二次大戦みたいな、ああいう戦争の形じゃなくって、戦宣布告なんてやらない、テロとテロに対する報復みたいな形の戦争がもっと大規模にあちこちで起こる。戦争の原因は結局資本主義にあるわけですね。だから経済的な理由で起こる。結局はアメリカの一国支配。帝国主義になっていって、それを盛り上げようとしている。いわば新自由主義なんていわれてるでしょう。あるいは新保守主義とかネオコンとか。そもそもアメリカ帝国主義って言い方は戦後すぐに共産党系が使っていた言葉です。すでに帝国だったわけですアメリカは。
長い事ソ連との2国で、共産主義との対立、社会主義対資本主義。それが結局、社会主義が潰れたわけですよね。中国も社会主義だけれども経済は市場経済を導入していまや超資本主義などと言われている。
だからいずれにしろ戦争の要因はかつてなく色濃く成りつつあるわけですね。これがどういうことになるか。前の、僕の生まれた次の年の1929年の世界恐慌から第二次大戦が終わるまで10数年の時間があるんですが、これから10年後にはどうなるか、現在もあちこちで戦争が続いているわけですが、それが大規模になるか。最悪の場合は核が使われる。それはいつ、どういう形で起こるか予測つかないけど起こる可能性が非常に強い。
坂上:経済がダウンしてきたときに立ち直る最大のカンフル剤はいつも戦争ですよね。
池田:オバマもまた前と同じ様な政策をしようとしているわけですよね。結局ブッシュの尻拭いをオバマはやるのでしょうけれど、尻拭いが結局は同じような、アメリカが世界の1位を保とうとする限りにおいてはそうです。ブッシュによってダウンしていって、危険な状態になっている。それを再びアメリカの力を盛り上げようという思いがあるんでしょう、オバマにね。
今って、アメリカのナショナリズムがかつてなく高揚してる時期だと思うんです。昔はそんな事なかったと思います。第二次大戦後世界をリードしてきたアメリカ。その間にアメリカの自尊心、ナショナリズムの高揚というものがかなり国民の中にある。だからアメリカが世界一の座から落とされようとすると武力で立ち上がる危険性があるわけです。だけどロシアの方も、強いロシア。だから強いアメリカ、強いロシア、それから中国もまたやがて経済大国になって三極構造。それとアラブ勢力。キリスト教とイスラム教との対立。だからどこでどうなるか僕なんかに予測はつかないんだけど、非常に危険な状態であることは確かですよ。
坂上:例えば陶芸家の林康夫さん、彫刻家の村岡三郎さん、私の身近な方で1928年生まれの方が結構多いです。そして皆、特攻に行っているんです、予科練から。
池田:昭和3年生まれ。僕らは、小学校に入ったときから教科書が新しくなったんです。国定教科書ですね。「サイタ サイタ サクラガ サイタ」から始まるんです。その前は「ハナ ハト マメ マス」とかいうカタカナの授業です。サクラの次が「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」。もう軍国主義なんです。桜だって結局はそうでしょう。国家主義の高揚を狙ったわけでしょう。
そこから始まって、支那事変といわれた戦争、昭和12年だから1937年、僕が小学校2年生のとき。まだ世の中の事も何もわからない。戦争が始まったという事だけ知っている。その戦争の理由はね、北京の近くで日本兵が演習してるとき、支那兵が鉄砲を打ってきたからそれに応じて応戦してそれで事変が始まったと、そういう具合に教わっていたわけ。それが支那事変と呼ばれた。それがどんどんあちこちに日本が進出していって、やがて南京陥落とか…。
坂上:そういうニュースが入って来ていたのは新聞からだけでしたか?
池田:そうです新聞だけ。ラジオは村全体でも何台かしかなかったから。その頃は新聞はぼつぼつ読める位になってました。みんなルビが振ってあるからね。意味がわからなくても読める。南京陥落、あれが小学校3年生のときになるのかな。
昼間は旗を振って行列です、「万歳万歳」って。夜はちょうちん行列になるわけですよ。ずっと田んぼの道をあるいて「万歳万歳」とちょうちんをぶら下げて歩くっていうのをやってました。
そうこうするうちに今度は出征兵士がぼつぼつと出てくるんですよ。そうすると小学生全部が旗を振って出征する兵を見送るんです。出征するたびに、10日に一回とか一月に一回とか。学校から歩いて40分位のところの小さな駅なんですよ。そこで出征兵士は敬礼し決意を述べてね、村長さんはじめ、ばんざいって言って…。
そのうちに今度は白木の箱が帰ってくる。戦死者。それをまたしずしずと迎えにいくんです。遺族がね、白木の箱を首から提げてやってくる。それを小学生徒たちは列を作って、頭を下げて迎える。そういう状態だった。そういうことでだんだんと。戦争っていうのは小学校2年の頃から。本当をいうと満州事変からの15年戦争といわれているから、僕が学校に上がる前から満州事変っていうのは起こっていて。それが日支事変につながって。みんな事変って言う。それで満州国ができ、それで満州国の歌も歌わされてね。今でもちゃんとはじめのほう歌えますよ。(満州語で歌う。)
満州国ができた頃にこれを歌わせられたんです。それで溥儀っていうのがね、清朝の末裔ですよ、それが皇帝にさせられて東京にやってきてね、天皇に会って。つまり傀儡政権が出来た。それも新聞の写真で見て知っているわけです。
そういう時代でね、いよいよアメリカと戦わなくちゃならない。その頃「日米若し戦わば」みたいな仮に想定した言葉が雑誌なんかにかなり前から見られたんです。それでいよいよ危ない、っていうのはやっぱり昭和16年になってからでしょうね。僕はその年の4月に伊万里商業学校っていう所に入りました。本当は工業学校に行きたかったんです。だけど工業学校は小倉にしかなくて。小倉に行くには下宿しないと通える距離じゃない。商業なんて関心まるでなかったんだけど、うちから歩いて45分くらいのところだから通えるわけで入ったんです。
それで入ってみたら教練というのがある。軍事教練です。いよいよ戦争が始まるかもしれないっていうのは、夏くらいから予感はしてたんです。12月に入って寒稽古の最中でした。朝早くね。そうしたら重大放送ということで、学校のラジオの前に行ってね。夜が明けたばかりの時間で、甲高い声で、「帝国海軍はただいま東太平洋海域において戦闘状態に入れり」とかいうニュースです。そういう文語調の言葉なんです。戦闘状態というので、「ああ、戦争だ!」と。
坂上:その放送の前には特別放送っていうのはなかったんですか?
池田:なかったけど雰囲気としては、アメリカとは戦わざるを得ない。戦わないといけないっていう状態になっていたわけですよ。
坂上:その特別放送を聞いたときはどんな感じでしたか?
池田:「戦争はじまった!」って。その後すぐに真珠湾攻撃の放送ですよ。大勝利、大戦果!数日後にはマレー沖で、プリンス・オブ・ウェールズっていうイギリスの戦艦を轟沈、と、それが新聞に大きな活字で出て。今でも覚えてますよ。たちまち南方に進出していってシンガポール陥落でしょう。「勝った勝った万歳万歳」で、最初の数ヶ月はね。
天皇も喜んでいるらしくて、あとで聞いたことですが、天皇はアジア全体の地図を広げて、勝ったときにその勝った場所に日の丸の旗を立てて喜んでいたらしい。
僕は小学校の頃まではそんなに軍国主義者じゃなかった。大きくなったら物理学者とか科学者になりたいと思っていました。物理に興味を持っていてね、というのは要するに好奇心が強くて、何に対しても「何故だろう」と思うのです。小学校で理科を習うようになってから、地球が丸いって習うと引力がわからない。地球が丸いことをイメージしてね、僕が立っていて地球の反対側の人がどうして立っているんだろうっていう…引力がわからないわけです。引っ張られてる感じもしない、磁石ならぱっとくっつくけど、地球が僕を磁石のようにくっつけてる感じがしないからよくわからない。星だってたとえばあの星は今から500年前に光った星。もっと長いのでは5万年前の星の光、それが今見えるっていうのがわからない。時間についてもわからない。5万年前を見るということがわからない。そういう疑問をだんだん持つようになってきてね。引力に関しても大きな岩があってね、岩の下の面のところを蟻が歩いてるわけです。すると岩が引力で蟻をひっぱっているのかなと思うわけで。実際そうなんですが、でも岩が引っ張る力よりも地球が引っ張る力のほうがはるかに強いから、蟻は死ねば離れて落ちますけどね。けれども岩が引力で引っ張っているのかなと思いましたね。よくわからない、だから大きくなったらそういうのがわかるように勉強したいと。それを小学校5~6年生くらいまでは思っていた。だから工業学校に行きたいと。
けれどもそういうわけで商業学校に入った途端に戦争でしょう。このあたりからね、やっぱりどっちみち男は兵隊に、それで特に負け戦になってからは…… 負け戦ってそれこそわからない。だってずっと勝ってることになってるから。昭和18年、戦争がはじまって2年目、その頃になったら一週間に1回か10日に1回位か、3年生になった頃、近くの佐世保から将校が学校にやってくるんです。「只今祖国の将来は君達青少年の肩にかかっている、お国のために天皇陛下のためにふるって志願しろ」と、さかんに煽り立てる。それで段々と戦争に行かなければならないような雰囲気が出来てきたわけです。
その前から忠国・愛国がひとつの美徳。国のため天皇のためにご奉公、つまりお国のために命を捧げる事が素晴らしい事というのを叩き込まれている。それでもって戦争が段々激化してきてるでしょう。どっちみち二十歳になれば兵隊に取られると。それと、もうひとつは僕の中で飛行機に乗りたい気持ちもあるんですね。機械をいじりたい、そういう思いもある。それから忠君・愛国の純情な気持ち。
ある日、海軍将校がいつものように演説して教室に引きあげた。その後の最初の時間が数学の授業でこれが担任だったんです。三十歳くらいの先生。その頃の僕らの学校は授業がはじまるたびに級長が声をかけるんです。「黙想」って号令をかける。しーんとなります。
そこで先生が、「先ほど朝礼で将校がこう言った。だから皆志願してくれ」って言うんです。学校の名誉のためでもあると言う。たくさん送り出せば学校の名誉。担任も自分のクラスからこれだけの生徒を出したっていう名誉。教員室の中でも鼻が高いという状態になることですよ。
僕は責任感を感じた。誰も立たない。そりゃそうですよね。今立てと言われたって。普通だったら親と相談して決めろって、今だったらそうです。でも昔はそうじゃなかった。僕はそのとき満で14歳と9ヶ月、数えでは16歳。昭和16年の正月に僕は親父から、大人になったと言われたんです。お前は大人になったんだ、と。昔、元服は16歳、数えっていうのは、生まれたときは1歳で、正月に年をとるんです。ですから中学3年は16歳なんです。だから大人という判断なんでしょう。侍と一緒で、元服という観念があったらしい。学校もそういうつもりなんでしょうね。だから親と相談しろなんていわなかった。今立てっていったんです。そう言われてもすぐに立てる人なんていないから、し-んとなってね。しーんとして気まずい状態。先生の要望に答えない。しーんって。それが仮に10秒であってもねえ、10秒間シーンとしてるのはいたたまれない。おそらく10数秒で僕はいたたまれなくなって、これは率先して立たないと、という気持ちになった。もともといつかは行かないといけないかなという思いがあったから。わざと椅子を後ろに下げてガタガタっと音をさせて立った。そしたらつられた何人か立ちましたね、おそらく6~7人かそこら立ちました。他の教室もそういう状態で、3年生だけで20数人。4年生はもっと多くて、試験を受けにいった人は全部で7~80人くらいだったか。それで佐世保に試験に行ったんです。
航空隊に入る試験。身体検査とか厳しいですよ。まず眼が1.2以上じゃないとダメ。だから眼がちょっとでも悪いとはねられる。体力、能力のテストがある。機敏性とか学力。夏休みに試験があって、それで合格っていうのが9月。全部あわせて合格者13人でした。不吉な数ですね。
それで9月の末に伊万里から見送られて鹿児島に。まだその頃は鹿児島まで伊万里から10数時間かかってました。午後遅い時間に駅を出発して汽車の中で寝て、翌朝着きました。それで訓練が始まったんです。地獄の世界でしたね。「娑婆(シャバ)」って言ってましたから、普通の世界を。
西澤:予科練に行くときの家族の反応はどうでしたか?
池田:家に帰って、「僕、志願してきた」って言ったらね、当然反対すべきなんですけど反対を口に出せないんです。しょうがない。しぶしぶ。反対を口にして、うちの息子の志願を取り消してくれなんて言えたものじゃない。そういう親は非国民ってやられちゃう。まず、僕が不名誉な生徒になりますよ。親も不名誉になるんです。
西澤:弟さん方も見送りするときは万歳で。
池田:もちろんですよ。家族や全校生徒や先生たちが伊万里駅に集まりました。600人近い人たちが駅にあつまって「万歳万歳」って言ってね。
その時は知らされてなかったけれど、もう負け戦になっていたんです。日本海軍はミッドウェーで大敗していた。けれどもそれを一言も言わない。アッツ島の玉砕がはじまったのも間もなくでしたね。藤田の絵にもあるでしょう、あれは全滅ですからね。
坂上:ああいう戦争画はよく目にされてましたか?
池田:僕は見てない。ああいうのがあったって知らなかったですね。小磯良平が描いた支那事変の兵隊のスケッチみたいな画集本を見た記憶はありますがね。
兵隊に入ったらすぐに、身に付けるもの全部は天皇陛下から借りているもの、与えられて借りてるものだ、ふんどしまで全部。だから、もし失くしたりすると、ものすごい体罰を受けるんです。ふんどし一本でも体罰ですから、ふんどしのひもの付け根のところに「第○分隊池田龍雄」って名前を書くんです。墨で墨痕あざやかに。そうじゃないと洗うと薄くなりますからね、濃く書いておかないと取られちゃう。時々抜き打ちに検査があります。足りなくなると半殺しの目にあう。支給なんてない。取られたら取り返す、盗むのです。だから一番最初はおそらく予備のために盗むんでしょうね、干してある奴を。名前が薄くなってるのはその上から自分の名前書いちゃう。
僕、弁当箱の事も本に書いてるでしょ?『絵画の距離』(創樹社、1980年)に載せたと思うんだけど、弁当箱をなくしてね。当番で洗っているときにふと気がついたら1個たりない。日曜のたびに外出があったんですよ。その時にアルミの弁当箱に当番で御飯を詰めて、みんな外出して帰って来て、それを洗って返却する。一班に30人。それを当番が2人だったかな、15人分の御飯を朝つめて、みんなが持って返ってきたらそれを洗っておさめに行く。ところが弁当箱が一つ足りない。使っていた流しはお向かいにも蛇口があるから、たぶんそこで洗ってた奴が取ったのかわからないけど、とにかく15個あったのが洗い終わって1個たりない。そうするとおさめるまでの2時間くらいもう必死になってね、僕もどっかから盗んでこようと思ったくらいだけどもう手遅れですよ、どうする事もできない。半殺しの目にあうことがわかってる。海軍には、「バッタ」っていって、長さ160センチ位の樫の棒を振り上げて、尻を思い切りひっぱたく。しかもそれだけで済まない。殴られてから腕立て伏せ100回とかね。リンチです。みんなが見ている前でやらされる。見せしめ。それが鍛える事の条件なんです。そうやって軍人は強くなっていくわけです。
まず入隊した。その時僕は中学生でしたけど、その中学校は僕らのときからカーキ色の菜っ葉服。それでゲートル巻いて学校に行ってたんです。行列して登校。先生に会うと、「歩調とれっ頭右」、の軍国主義。1年生のときからそうでした。でも、それでもそこを「シャバ」だっていうんです。シャバっ気を叩き出すんだって言ってね。最初に素っ裸になって全部を変えさせられるんです。14~5歳くらいから一番上が今の高校2年生くらい。僕は若い方で、僕より若年は数人しかいない。そういうのが180人位。廊下に裸になれと言われて、素っ裸でざーっと並んで、そこへひとつひとつ持ってきたものを置いて着替える。そこから始まる。シャバで着ていたものを脱ぎすてて、天皇陛下から与えられた海軍の軍服を着る。それからその後の儀式が、一発ずつ。軍隊ってのはこういうものだとわからす。それがものすごく痛くて。二日かそこら仰向けで寝れなかった。みんなそうだった。腫れちゃって。仰向けになるとお尻が痛いので横を向くか腹ばいで寝ましたね。それが度重なると慣れてくるので、3~4発だと耐えられるけど5発以上で気絶しちゃうんです。気絶すると水をぶっ掛けるんです。それで両側から支えられて殴られる。薄い白い作業服着ていてその下はふんどしひとつでね。痔の悪い奴など血が滲んでくるんです。あたり所が悪くて死んじゃった人もいる。殺されたに等しいんだけど、殺された者の家族には病死扱いになるんです。家族には病気で死んだと。殴り殺されたとは言えない。殴り殺した方も訓練で鍛えるためにやってたら死んだということになる。天皇陛下の命令で殴ったことになっている。上官の命令は朕の命令と心得よ、と。だから上官が命じた命令は天皇が命令したのと同じことなんです。天皇陛下にかわって殴って、それであたり所が悪く死んだ、と、そういうのが日本の軍隊です。日本は精神力、大和魂で敵を倒す、精神力で勝つ。武士道。大和魂。神風って言っていたでしょう。特攻隊の名前も最初は「神風」って名前がついていました。
坂上:負けた時はどんな気持ちになったんですか?
池田:負けるという観念は最後までなかったですね。その前に死ぬだろうと思っていた。先がどうなるかわからない。勝つことはないだろうと。それは昭和20年になると大体わかっていた。沖縄上陸が20年の3月ですか、情報は必ずしも正確に伝わってない。沖縄が陥落した、占領されたっていうのは知らなかったですね。教わってないのです。でも空襲があった。飛行場もやられて。新聞を読まないから、口伝えに聞くだけで詳しい情報は知らないけれど、ただ負けているっていうのはわかっていた。飛行機だってゼロ戦に乗るはずだったのに無くて、練習機のまま特攻隊になってる状態です。しょっちゅう空襲があるようになってるから勝ちはしないとは思っていた。けれども負けるというのは考えないんです。その前に死ぬだろうと思っているから。
それでいよいよ8月15日のお昼近い時ですね、玉音放送、天皇陛下の放送があるという。その時は松林にいた。霞ヶ浦の飛行場から歩いて30分位の所の松林の中に空襲を避けてそこで暮らしていたんです。そこにラジオをどこかから持ってきて、天皇放送が始まった。でも、がーがーがーがー。時々朕は、って聞こえるだけであとはがーがー、何言っているのかわからない。妨害されていたのかラジオが悪かったのか。みんながそういいましたね。ほとんどわからなかったって。だから終わっても今天皇陛下は何て言われたのかな?などとがやがや。ソ連が参戦したのではないかとか、いよいよ戦局が逼迫してるから皆一層がんばれって言われたとか、そういう風にしか解釈できなかった。無条件降伏なんて知らなかった。それから数時間たって3時頃になってから、上から無条件降伏だって知らされて兵舎に帰ったのです。夕方になってね。カナカナカナカナ…ってセミが鳴いていてね。そのあと特攻隊は銃殺されるって聞いたから、どうせ銃殺されるならたてこもって アメリカ兵と刺し違え一人一殺して死のうと決めて、ピストルを打つ練習。日本刀を一本ずつもらって斬る訓練。それが中々切れないんだけど。そういうのを一週間近く続けたと思う。
坂上:特攻隊はすぐに解散したわけではないんですね。
池田:解散は8月下旬です。それまではアメリカ兵と刺し違えて死のうっていう白虎隊みたいなことを考えて、それでどこに立てこもろうかと夜になると協議してね。日本の地図を見て検討してるの。最終的に、決まったのは平家の落ち武者と同じ、飛騨の高山とか白川郷とかあの辺りが一番奥まっているからここへ行こうっていって、そこまでどうやって行こうかって相談していた。だけどみんな飛行機には乗れるけどトラックの運転の経験者は誰もいないしね、トラック運転できる奴、兵隊を拉致して一緒に運転してもらって行こう。ガソリンは隊にあるだろうからそれを盗んじゃって燃料にしてとかね。そのうち銃殺とかはデマであるから、まどわされるなと。武器は返上しろと命じられて、それでピストルと日本刀を納めたわけです。それから24日だったか。(注:『夢・現・記』では24日に出発とある)そこでようやく特攻は解散。
その晩はパーティをやりました。何人かが倉庫に行って飲み物など勝手に持ってくるんです。それがねえ、一部屋に4人ずつに分かれていたんですが米俵が一俵一部屋あたり。とにかく解散という事で、ワーワーどんちゃん騒ぎになって、缶詰、赤玉ポートワイン、ウイスキーもあって缶詰食べてね。赤玉ポートワインって甘いんです、それをがんがん飲んで。酔っ払って。でもオレは酔っ払ってないなどと強がり言って、50回の腕立て伏せをやって見せた。その事も本に書いてますけどね。その翌日はひどい二日酔い。頭がんがんして、みんな戻してしまいました。朝9時頃出発だったと思うんですが、霞ヶ浦から伊万里まで3泊4日かかりました。汽車の中で3度寝て、4日目に家についてます。
まず霞ヶ浦から東京上野。上野で乗り換え。上野駅は惨たんたるものでしたね。死んでいるのか生きてるのかわからないのが地下道にワーッといるんですよ。腐臭みたいな嫌なにおいがいっぱいたち込めて。そのあと東京駅。東京駅も数ヶ月前に通ってるんですけどね、レンガがあちこちくずれていた。空襲のあと、もう焼け野原です。東京全体焼け野原で、ところどころぽつんと焼け残ったビルが建ってる、そういうのを見ながら、東京駅で1時間ちょっとあったから、周りを見に行って、それから列車に乗って、豊橋に行く。東京・豊橋間は一応電化されていたんです。豊橋には翌日着きました。だから一晩明かしているんです。
翌日豊橋に着いて、午後出発。貨車でした。屋根がない。雨が降ったんですけど幸いにしょぼしょぼ雨でした。名古屋を過ぎたあたりから降りだしたんじゃないかな。雨も大変だったけれど、トンネルが大変で。汽車でしょう、石炭の機関車ですからトンネルの中は石炭の煙がもうもうで臭くて苦しくて死にそうでした。
やっと京都についたのは午後遅い時間で、次の列車はいつ出るかわからないから、はじめてそこで飯を炊いて食おうって事になってね。それまでは缶詰と乾パンしか食べてないんですね。誰かが飯はどうやって炊くんだって言うと、なぜかやかんを持ってた奴がいてね。その時は総勢、大体九州に帰るやつばかりが6~7人くらいいたかな、一緒に貨車に乗り込んでいて。線路際に石を集めて木々を拾ってきて、マッチで火をおこし、やかんのクチをぼろきれで塞いで噴出しないようにして炊いた。そのご飯の味は今でも覚えてるくらいうまかった!
結局夜が更けてから列車は出発したんじゃないかな。大阪についたのが夜遅い時間でしたからね。そうしたら京都でもう満員だったのに、大阪ではホームにあふれるほど人がいるんですよ。困って、もうこれ以上乗れないから列車の入り口辺りは中からドア閉めて開かないようにして、窓も下ろしてる。それで足でガラスを蹴破って窓から入ってくるんです。荷物をいれてきて、お願いしますって窓から入ってくる。夏だから寒くはないんだけどとにかくそういう状態で満員ですよ。すし詰め。ひどいのはトイレの中から鍵を掛けてトイレを分捕ってるやつもいる。女性は困るでしょ。駅につくと窓から飛び降りておしっこしてました。
明け方が広島。夜が明けて、もやがあってね。僕は窓際に座ってた。それで、広島。広島ってアナウンスだから駅に着いたと思うんだけども建物がないんです。はじめて原爆と言うもののひどさを見ました。原爆と言う言葉は当時はなくて、隊内ではチラシみたいな通知が時々配られるんだけど、それに「敵、新型爆弾投下」って見出しを見てます。新型爆弾が落とされて被害は甚大と、その程度のことです。そういう情報しかないわけですから。それで広島について見たら何もないんです。見わたす限り何もない。ひどいと思った。
広島を出て、それでもう一晩汽車の中で寝て、翌日の夜明けに佐賀を通って、伊万里のうちに着いたのが午後1時ころだったか。いきなり「ただいま」って言って帰ったんです。通知も何もしないで。
坂上:ご家族は皆さん生きていましたか?
池田:佐世保に近いからどうかと思ったけど、伊万里の町そのものは空襲の被害などほとんどなかったみたいですね。わが家はもちろん焼けていない。
それで、ただいま!って言ったら、おふくろが眼をまんまるくして、「あら…っ」て感じで。「帰ったの」って、そういうくらいの事であとは何もいわない。演劇的じゃないですよね。抱き合って涙流して喜ぶなんて、そういう場面なんてない。でも、とにかくうれしかったのは確かでしたね。
それは8月の28日だか29日だったかもしれない。汽車で3泊4日かかった事は確か。3泊を汽車でしたのは間違いないから逆算すると24日か25日に霞ヶ浦を出ていることになりますね。
それから僕は虚脱状態なんです、何もできない。死ぬと思っていたのに生きて帰ってきたからね。師範学校に入るまでの2ヶ月くらい、何をしたらいいのかわからなくてぼやっとしてました。それから俄然、勉強しなくちゃって思い始めて。学校へ戻ろうかと思ったんです。商業学校5年生です。間もなく卒業です。だから今学校に戻ったってすぐ卒業。それで新聞で知ったかと思うけれど師範学校が生徒を募集してる。転入学ができる。予科練を出たものは中等学校を卒業した者と同じ資格者と認めるとなってる。それで師範学校に行こうと思ったんです。別に先生をやりたくて師範学校にいったわけじゃあないんです。勉強したい、学校へ行きたい、と。その他師範学校に入った理由に学費がいらない、というのがあったんです。そのかわり義務として卒業したら先生をやらないといけない。けれどそれで入ったんです。佐賀で試験があったんですが、受けにいったのは、記憶では10数人。同じ予科練の出身とか海兵とか、陸士出身とか。※2 それで合格したのが2人だけ。僕と海兵の在学中に戦争が終わった二人だけが合格になって入った。11月に入学。
それが一年ちょうどくらいで学校を退校になったんです。
坂上:日記をいつくらいから書かれてたんですか?
池田: 9月の何日か位から付けはじめてます。日記は軍隊で予科練のとき義務的に書かされていて、そういう習慣がついていたんですよ。予科練の日記は全部検閲が入って、班長のハンコが押される。一ヶ月に一回とか一週間に一回とか提出しないといけないから、いい事ばかりしか書かない。誉められるようなこと。うかつな事は書けない。立派な事ばかり書いてる。その一冊を持って帰って来てたんですけどそれもどこかにいっちゃってますね。とにかくつまんないですよ、和歌みたいなのも書いてる。その影響ですね。9月から翌年まで付けてたんだけどその一冊目はどうしたのかないんです、手元に。2冊目からは残っている。手製の冊子でね。「つぶやき」ってタイトルつけて。昭和21年の8月14日から。『夢・現・記』(出版社、出版年)の一番最初の文章はここから引用してるんですよ。「あの日からちょうど忘れられない一年目…。」それはここに書いてあるんです。藁半紙に線を自分で鉛筆で引いて、それにびっしり書いてます。あとは大学ノートみたいな…… 大学ノートも薄っぺらな粗末な紙でね、それに書いてます。とにかく2冊目は手製。大学ノートすら買えなかったってことです。わら半紙に厚紙をそえて糸で閉じて『つぶやき』とタイトルつけてる。それにずっと。最初の頃は割に几帳面に書いてるけどあとになると間遠になったりして。毎日書いてるわけじゃないんですね。
坂上:せっかく師範学校に入ったのに退校だったんですね。
池田:校長に呼ばれたのは夏休み前でね。僕一人だけなんですよ、呼ばれたの。一緒に入った、兵学校から来たのは呼ばれない。行ってみたら僕一人が退校だって。海軍の将校を養成する海軍兵学校の在学生は卒業するとすぐ将校になるじゃないですか。半年くらいで彼(海兵の在学中に戦争が終わり一緒に師範学校に入ったもう一人)は将校になるんだけど、まだ将校じゃないから現役でない、僕は現役で、下士官だったから(戦争加担者に)該当すると。
そういう人は追放、つまり先生になる事が禁じられた。マッカーサーの占領政策で軍国主義を一掃する。だからあの頃のね、皆さん知ってると思うけど教科書は全部戦争に関することは、忠臣蔵だって禁じられた。剣道も禁じられた。軍隊とか戦争とかそういうものに関する箇所は全部消された。「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」も黒い墨で消された。だから教科書は黒い墨の縞模様になっていた。
坂上:それまでそれを覚えなさいって言われたのに否定されるって困りますね。
池田:だから先生がガラっと変わって。歴史の先生なんかその直前まで皇国史観を教えていた、それがたちまち民主主義教育。だから学生の方は不信感を持つの当然ですよ。師範学校にもいたんです。元海軍少尉で歴史の先生が、彼は予備役だから追放されないで、生徒の僕が追放。実に理不尽です。
坂上:誰も助けてくれなかった
池田:そうです。だから大いなる反発。17歳ですから当然ですね。
坂上:追放されたら何で芸術にいくんですか?
池田:芸術が一番自由だと思ったんです。芸術なら追放される事はないし上からの命令で動かなくていいでしょう。だから先ずは映画監督、次が小説家、三番目が画家。しかしその最初の2つ両方ともちょっと難しい。どうやって映画監督になれるのかね、僕は黒澤明の『素晴らしき日曜日』なんて映画も見た。それから外国映画もいろいろ見て、すごく映画好きだった。それもただ映画を見る観客の立場じゃなくて、見ながら僕だったらもう少し違うように撮ったのになあ、と思って見てたんです。つまり映画を自分で作りたいという気持ちがあった。
坂上:小さな頃からたびたび映画をみてたんですか?
池田:見には行ってます。ちゃんばら映画とかね。丹下左膳とかね。トーキーは僕の小さな時からはじまりましてね、驚きを感じましたよ。それまでは無声映画。楽団がいましてね。スクリーンの下で演奏するんですよ。バイオリンかギター鳴らしたりね。そこで一方に舞台みたいなのがあってテーブルに弁士。画面をみながら「そこで彼女は!」とか台詞を言うんです。説明する。そのうちにトーキーが映画館にきた。驚いたよ。はっきり覚えてる。あれは丹下左膳かなんかで、なにやら文字を書いた浴衣みたいなのを着て、煙草を吸ったシーンがあってね、大きな煙草のキセルを叩く、「トン」という音とそのシーンをはっきり覚えてる。トーキーだから「トン」と。弁士はそういう事はいわないんです。台詞は言うけど。「トン」まではいわないから。はじめて聞いて、トーキーってすごいなって思った、そういう時代。
戦後はもちろん黒澤明の『素晴らしき日曜日』など。映画を見てラブシーンなんかもうちょっと違う角度から写したらよかったんじゃないかと思って見たりしてるんですよ。好きになると同時に自分で作りたいと思うんです。だけど、どうやってなったらいいのかわからない。小説家になりたいけど出版する当てもない。小説は書いたですよ。不倫の話を書いた。それから演劇も不倫の戯曲。これは上演しようとしたんですが、青年団の「敬老会」で。けれど敬老会にふさわしくないということで、立ち稽古まではいっていたけど、止めにした。師範学校を追放されてから、村の青年団の文化活動に参加していたのです。
その頃はもちろんまだ絵描きになろうなんて思ってない。
いよいよ絵描きになろうという風に段々決意を固めたのが22年の夏くらいからですね。それで願書を出したのが23年の1月くらい。願書を出す場所がわかんないんですよ。上野の美術学校(現在の東京芸術大学)は、調べてみたらね、その年は募集しないと。それは12月位にわかったんです。そうしたらどこを受けたらいいのかわからない。上野の美大しかわからないし、知らないから。それで色々聞いていったら多摩美っていうのがあるとわかった。多摩美の卒業生が同じ村にいたんです。その人も池田って名前でね、しかも、うちから10分くらいのところにいたんです。電話なんてその頃はないし、いきなり行くと大抵いない。何度行ってもいない。いよいよ、佐賀にいって師範学校の美術の先生に美校のアドレスを教わろうと、そのために佐賀に行こうとして伊万里の駅に行ったらばったりその池田さんに会った。それでやっと住所教えてもらってそれから願書を出した。全部親に内緒だから今の学生達と違いますよ。
坂上:どんな入試だったんですか?どんな科がありましたか?
池田:試験がどんなのかもわからない。とにかく実技の試験と学科の試験はあるだろうと。どういう試験があるのかも知らないまま。だって入試の日程の案内をもらったのが1週間前でしたよ。それで初めて親にうちあけたわけです。もちろん反対。親戚一同が集まってきて大反対。その時、僕は特攻隊で死んだと思ってくれと親に言って。乞食してもルンペンになっても東京にいくんだ!って言ってね。
自画像を油絵の稽古のために描いたのは22年の夏でした。初めて描いた。何もおそわらないまま画材を買いにいって。伊万里に画材屋はなくて文房具屋はあるけどクレヨンぐらいしかないからね。油絵の具を買うために、佐賀の師範学校のときから知っていたお店へいって筆を2~3本と絵具も限られた種類の絵具だけ。黄色・茶色・黒・白とかそれくらい。お金がないから。だから4~5色だけ買った。必要な色だけ。使おうと思う色だけ。緑も買った。それだけを買って隠れて小さな板に納屋の中で描いたんです。夏だから裸です。
坂上:(図版を見ながら)上手ですね。
池田:絵はうまかったんです。小学校のときから。1年生のときに北九州一円のスケッチ大会に先生に誘われていって銅メダル。2年生のときは佐賀県全体の小学校の図画コンクールで銀メダル。つまり絵はうまかったって事です。似せて描く事はうまかったです。戦争中に樺島勝一って挿絵画家がいてね、写真みたいにペン画で描いていて。それをまねてペン画で描いてましたよ。
坂上:「絵がうまいな」って自覚があった。
池田:先生に、うまいといわれて教室の後ろにいつも張り出されていたから、うまいって自覚はあったんです。でも絵描きになろうなんて思ってもみなかった。
坂上:色々素材はある中でなぜ油を選んだのですか?
池田:特にはっきりした理由はないですね。水彩も描いてます。
坂上:伊万里の書店でダリの絵を見て感激されたって何かに書いてありましたね。
池田:感激というより、「妙な絵だなァ」と、反発も混じった興味でしょう。絵には関心を持っていて。絵と小説と映画。絵に関心を持ってるから、『アトリエ』なんか見てました。
坂上:ダリのどの絵だったんですか?
池田:あれは、デッサンで、時計が描いてあって、ペンで描いたのを、北園克衛(きたぞのかつえ)が解説してました。そこでシュルレアリスムって言葉を知ったんです。その時はダリをキチガイみたいな絵を描く人だと思いました。だからそのときは絵描きになろうと思ってない。こんな絵を描く奴がいるんだということを知ったわけです。
坂上:とりあえず見たものを描くと。
池田:その頃は当然です。印象派的なものが絵だと思ってる。
それがね、中村彝(なかむらつね)のエロシェンコの像ですね。それを見た記憶があって、いいなと思ったんです。学校時代に画集で見てます。色刷りの。それでいいなあと思って見た記憶があってそのような色彩で描こうとした。大体茶色っぽいです。その影響で自画像描くとき同じようなその色を選んだんです。その頃は画集なんかで青木繁なんかは知ってます。それから学校ではすでに岸田劉生の『美の本体』(1954年、河出文庫)って本を読んでます。それから夏目漱石の文学論とか盛んに読んでるんです。美術に関する本も読んでる。それもあったから芸術ってものに大いに関心を持った。追放されてから、芸術の世界は自由で表現は自由なんだと。その表現が映画と小説と美術ということだったんです。
坂上:お父さまの影響は強いですか?
池田:親父は文学青年的なところがありましたし、うちに文学全集があったんですよ。昭和~大正だったか、明治~大正だかの文学全集が小さな本棚3段くらいの幅であって、夏目漱石とか谷崎潤一郎とか芥川龍之介、尾崎紅葉などいろんなもの、それで読みましたね。
坂上:でもお父さまは美大に行く事には大反対されたんですね。
池田:もちろん。家業の石屋をつがせようとは思ってはないけど、師範学校に行って先生になって家の経済を助けてくれって思いはあったようです。僕の下には6人も子供がいるから大変です。僕は長男だし。学校出て先生になれば助かると思っていたけれどもなれなかったでしょ。だからどっかに勤めて働いて金を稼げという事だったんでしょうけどね。
多摩美に願書出すまえに、僕は叔父が世話してくれた農協に勤めています。金融関係の仕事。簿記なんか商業学校で3年位やってますし。殆ど忘れてしまったけれども習ったわけですから。それで農協の金融関係の仕事ですね。その仕事に昭和23年の1月から勤めていたんです。3ヶ月たらず勤めてその給料をこっそり溜めようと思って。だから叔父さん、ばっととんできて説教したんですよ、「何でやめる、何で美術学校なんか行くんだ」って。「勤めているのに…」と。だから「僕はね、一切仕送りなんか期待してない、僕は自分で作った金で行くんだから、あとは向こうでルンペンになるなりして金を稼いで苦学しても、一切親の世話にはならない、僕は特攻で死んだと思ってくれ、僕はすでにいないものだと思ってくれ」と言って出てきたんです。だからそういう覚悟だから後に引けないわけですよ。途中で絵描きになるのに疑問を感じてね、「絵なんて駄目だ」って。ダダイズムまでいってるヨーロッパの絵を見て。「あとは一体自分は何をすりゃいいんだ」って。「これから絵でやれることなんてあるのだろうか、いやだなあ、やめようかな」と思ったけども辞めるわけにいかない。今さら田舎に帰れない。
坂上:芸術を目指していくのに、当時は芸術が自由だと思うのと同時に何か明確にどんなものを描きたいとかやりたいとかありましたか?
池田:ただ、いい絵を描くように努力しようと、それだけ。いい絵っていうものがどんなものなのかはわからないけど、とにかくいい絵を描こうとそれだけです。絵描きとしてえらくなるには、その頃は美術団体に入る事だったんですがね。僕は学生のときにね、伊原宇三郎先生に0点をつけられて、「こういう連中に審査を受けなくちゃいけない美術団体なんて絶対に入らない。公募展には出さない」と、審査を受ける事を拒絶する考えになった。そこへもってきてアヴァンギャルドです。岡本太郎。ちょうどアンデパンダンがはじまって。アンデパンダンに出せば無審査だし。そういう気になって僕は美術団体に入るなんて一度も思ったことがない。岡本太郎に誘われて二科に出さないかと言われたのも断った。
坂上:多摩美に入ったときはアヴァンギャルドなんて知らなかったですよね?
池田:知らない。せいぜいセザンヌまでで。でも、「アヴァンギャルド芸術研究会」に参加してしばらく後に、アヴァンギャルドってのは単なる反逆なのではないか…って日記の中に書いてる。やはりセザンヌからはじめるべきではなかろうかと。それはアヴァンギャルドに入ってからの話で、しばらくしてからそういう迷いみたいなのがありましたね。だから多磨美に入ったばかりの時は当然知らないわけです。ただ、さっきも言ったように田舎にいたときにダリのデッサンを見て、「気違いみたいな絵だけどこういうのもあるんだなあ」と思った。けれど自分でそういうのを描こうという気持ちにはなっていないんですね。
坂上:多摩美にはいって同級生たちはもちろん石膏デッサンで……
池田:もちろん。その頃は粗末な中身でね、何もない。それで普通、石膏デッサンは、パンを練ってそれで木炭を消すけど、パンがないでしょう、金持ちがたまにパンを持ってきても皆に食べられてしまう。大抵はつばで消してね。しつこくやると紙が擦り切れて穴だらけ。そういうのもありましたよ。そういう状態だから石膏だってね、多摩美には4~5種類しかなかった。それで、数人で日大の芸術学部、江古田の学校、あそこに行って借りてきた記憶があります。そうやって描いていたんです。指導も、実技の先生はいるけど殆ど学校に出てこない。多摩美を数年前、戦時中に出たという25~6歳の人が助手として石膏デッサンの指導をしてました。石膏デッサンは一週間に一枚描いて提出するノルマだったかな。あと学科がフランス語、人体解剖とか芸術概論などがありました。そのノートは今でも持ってます。
2学期に入って9月の半ば過ぎになってから授業がはじまって、その頃から僕はアルバイトに通いはじめた。10月に入ってからともかく、そのせいか、一切その頃は日記がないんです。9月頃から12月頃まで空いている。だからいつアヴァンギャルド芸術研究会に入ったかの記憶がないんです。
多分10月の終りか11月。田原太郎が行こうって。花田清輝とか岡本太郎はその前から知ってたんです。伊万里の本屋で花田清輝の本は立ち読みしてましたからね。名前を知っていた。岡本太郎は上京してすぐ二科展を見ていて覚えていた。それは《女》って題名で、半ば抽象なかば具象。黄色とかピンクとか黒、赤が使われていたかな。まず変な絵だから、岡本太郎って変わった絵を描く人だっていうので覚えた。ところが入学したら女子学生のひとりが、「私岡本太郎のところに下宿してるの」って言うので、夏休み前に行った事がありましてね。ところがその時は岡本太郎はいなくて、会うことはできなかったですね。その時はアヴァンギャルド芸術研究会は始まってなくて知らなかった。はじまったのは9月からで、僕は10月になって知った。行ったのは10月の終りか11月だと思うんです。場所は東大、赤門の右斜め前を入ったところ。そこの喜福寺ってお寺です。これはね、今井大彭っていう和尚さんが絵も描いていて、二科にも出してるんです。抽象画。だから岡本太郎とつながりがあったのでしょう。そこの本堂でやっていた。月に2回か3回位集まったときもあったかな。いつも昼間。僕が最初に行ったとき、今でもはっきり覚えているのは、椎名燐三がしゃべってるの。その時椎名燐三が「この魔法の杖とは」って言いながら何かをしゃべったんですよ。一通りチューターていうか報告者がしゃべると、それを受けて質問とか議論をする。そういう形でした。
坂上:絵の合評もあったようですが。
池田:それは時々岡本太郎が、描いたものを持ってこいっていうから、小さい絵をもっていってね、そこで見たり。それからときには東大を使ったこともあるんですよ。18番教室だったか、安部公房が東大出身だったしね。
出席は誰でもできるんです。だからいつも入れ替わり立ち代わりいろんな人がきた。三島由紀夫まで来たって言うし。僕は覚えてないですけど。野間宏、埴谷雄高、佐々木基一、梅崎春生など文学者が多い。椎名燐三、武田泰淳、そういう人達。絵描きは岡本太郎ひとり。その年の1月に「夜の会」っていうのが岡本太郎の家で発足してるんです。中心が花田清輝と岡本太郎。花田清輝が佐々木基一とかに声かけて。画家は岡本太郎ひとりだけ。岡本太郎がその年23年の夏に「アヴァンギャルド講座」っていうのをやってるんです。その講座を受けに来ていたのが、山口勝弘とか北代省三とか福島秀子とか。それで9月から始まる「アヴァンギャルド芸術研究会」にこないかって岡本太郎に誘われたらしい。僕はやや遅れて行った。だから僕が入ったときには山口君たちはすでに来ていたわけです。
最初は「アヴァンギャルド研究会」とは言っていなかったらしくて、「20世紀研究会」と日記には書いてある。それはね、安部公房なんかが「世紀グループ」っていうのを20代の文学者たちが集まって作っていて、そのグループに岡本太郎、花田清輝が合流してるんです。それで「20世紀研究会」って最初言っていたんじゃないですかね。それがいつのまにか「アヴァンギャルド芸術研究会」って名前になって。そのうちに翌年24年の3月頃に僕の日記の中に準備会の事が書いてあるんですよ。5月の1日の日付で「世紀の会」を作ってる。5月1日付の「世紀ニュース」っていうのがガリ版刷りで出来てる。そこに世紀の会の組織が記してある。会長安部公房、副会長関根弘。会計誰々、会計監査だれ。
それでね、そのとき(1949年5月)「絵画部」ってのを「世紀の会」の中に作ろうって事になって。「世紀の会」は文学の集まりだけども、そのほか絵画部ってのをつくったんです。だからそれはちゃんとした組織。会員証っていうのつくって僕も持っていると思いますよ。会費いくらっていう事を決めて。それで、ちょうど一年後の50年5月にね、僕らやめるんです。絵描きの殆どが辞める。辞めた理由はね、どうも研究会のテーマが文学にかたよる。報告も、しゃべるのは文学者が得意だし美術の問題はたまにしかないから段々詰まんないねってことになって、やめようや、となったんです。それで別にグループをつくった。それが「プボワール(pouvoir)」っていうんです。命名は北代さんかな。フランス語なんですね。可能性とか能力って意味もある。
坂上:そういう動きのなかで1950年2月には(読売)アンパンに出しますね。
池田:そうですね。それは、岡本太郎がアンパンに出そうっていって。そういう気運があった。あの頃アンパンは全部、有名な人も出してます。梅原龍三郎も出したはずなんだけど、但しこれは、あとで、瀬木慎一がアンパンの全部の記録をつくったんですよ。それによると新聞の予告に名前は出てるけど実際には出品していないみたい。翌年は出してます。新聞社は梅原龍三郎にアンパンに出す話をもちかけて、出すとか承諾したらしくて、広告は出してるんです。梅原も出品って新聞に載ってる。だから並んだと思ってたんですね、僕も『夢・現・記』にそう書いてるんだけど、実際は、あとで記録を見ると梅原の作品はないんです。一回目は。
坂上:池田さんが展覧会に初めて絵を出したのは?
池田:49年秋に「第2回モダンアート展」(1949年9月23日~29日)を「日本アヴァンギャルド芸術クラブ」が主催してやって。それ三越で9月かな。《実験室》(1949年)って作品。その作品はもうない。つぶして別の作品になってしまってます。
坂上:どんな絵だったんですか?
池田:《実験室》って題をつけた絵、少しピカソの影響が出てまして。ウサギを描いてね、それから試験管だとかはさみだとか描いたかな?それらを組み合わせて構成した全体は抽象的な感じ。
坂上:色は?
池田:その時はグレーっぽい色を使っていたかな。黄色を使ったかも。黄色とグレーと黒、そういうのを使って、赤など暖色系等。僕は寒色系を使うのが苦手です。グリーンは時々使うけど。
坂上:この頃に流行っていた絵に「お決まりのはらわた」(があったとか)『夢・現・記』にそんな事が書いてありました。
池田:そこには「美術文化」系の作品が何点かあって、それを見た感想です。殆どがダリ風のシュルレアリズムというかね、パターン化してるんです。卵とかはらわたとか、類型化したシュルレアリスム。それでその事を批判的に書いたんです。岡本太郎の考えは、一方にシュルレアリスムを非合理の極とし、もう一方に抽象絵画、アブストラクトを合理の極におき、その両者を折衷するのはモダニズム、それを折衷しないで両極にまたがって、太郎的に言うと「引き裂かれたまま、血を流しながら進んでいく」のが対極主義なんです。折衷しない、だから岡本太郎は言うことは勇ましい、言うことはわかるけど、どうやってそれが可能なんだと頭を傾けたくなる。それを実際に証明したと思われる絵が《重工業》(1949年)って作品。工場が抽象化して描かれてますね。そこに突然ねぎがバーンと描かれている。彼は無機的な工場とは無関係に巨大なねぎを不協和のままに放り込む、あれが「対極主義」の図解の絵だと思います。
それを知った上でね、少しあとの話になりますが、僕はたまたま、石炭をどうとらえたらいいかという問題をかかえて、八幡製作所に行ったんです。そしたらその中で、巨大な圧延機を使って薄い鉄板を作っている。真っ赤に焼けたインゴットという鉄の塊が、その圧延機の間を猛烈な勢いで往復するのですが、そのそばに背丈以上ある青い笹が、何十本と立てかけてあるんです。それを労働者が―彼は上半身裸です。それが、火の粉をあびながら次々に往復するその熱い鉄板の上に(笹を)投げ込んでいるんです。笹の中の空気で、パチパチと不純物になるカナクソを弾きとばす。その光景を見て、僕はとっさに岡本太郎のあの《重工業》を思い出しました。巨大な鉄の機械ばかりの完全に無機的な世界。その中にある全く不調和な青い笹の一群。あ、これはまさにシュルレアリスム的だな、と思いましたよ。1956年頃の話ですね。そのあとでね、直前にできたばかりの新しい圧延工場があるんだって聞いて、そこを見せてくれと言って行ったんです。それが《ストリップミル》(1956年)という作品になった。それは近代化された工場で、その前に見たような光景が全部覆われているんですね。最初のローラーだけ見えて最初の入り口からインゴットがはいっていって、それがはるか向こうでね1ミリぐらいの薄さで流れるように薄い鉄板がでてくる。中身は見てないけどその仕組みをこの作品で描いたんです。
坂上:池田さんの作品の中に出てくるモチーフはすべて、生きてるみたいに見えるんですけどそういう風に描いてみようって思ったのっていつですか?
池田:現実のものから解釈してそれで形をかえているんですね。生き物みたいなもんじゃないですか。動いているものってみんな生き物と思っていいと思うんです。あれも石炭とかエネルギーを食べて生きてる。動いているものは生き物的仕組みを持っている。そう解釈していいと思いますよ。だからそれらはようするに石炭を食ってるっていう感じを持ったんです。
もうひとつ《贈り物》っていう作品ね。これは川崎の火力発電所を見たんですね。火力発電所を見たときね、石炭が燃えてる。そこに働いている人と知り合いになってルポルタージュのつもりで行った。すると大きな炉、蒸気を作り出す炉に覗き窓があってね、そこから見たら猛烈な勢いで白い状態で石炭が燃えてね、その火力で蒸気をつくってるんです。タービンを回して電力に変えてる。そういう装置が生き物的な解釈になる。石炭を食って電気を吐き出してるっていうか。それで、しかもこれは《贈り物》っていうマン・レイが作ったアイロンのオブジェと同じ題名を付けました。
坂上:「プボワール」っていうグループをアンパンが終わったらすぐにやめてますね(1951年5月頃)。そのきっかけは何ですか?
池田:あれはね、すぐやめようっていう気持ちで作ったんじゃないグループなんですけど、50年の5月でしょう。6月には朝鮮戦争が始まるんです。それで僕なんか花田清輝とかの影響を受けているから芸術は世の中の変革ということに役割を果たすべきだ、という考え方があったんです。つまり芸術の革命というのと革命の芸術というものを一致させようという考え方があったんです。連中はみんな共産党員になってましたね。だから当然、「朝鮮戦争反対、平和」って言う声を上げる。僕もそういう意見を持ったんだけど、「プボワール」ではそういう事はほとんど問題にならない。美術のアヴァンギャルドはどうあるべきかっていうことだけが、―新しい絵はどうあるべきか、どうすべきかという芸術の変革だけに重点がかかってる。だんだん不満を覚えるようになってきたんです。それで一年そういう状態がつづいて、いよいよ翌年5月になったら、「プボワール」というグループを続けていてもしょうがないっていう考えになっていてね、僕の周りの何人かが、プボワールやめようということになった。そしたらじゃあ解散ってなった。5月に解散。原因は朝鮮戦争です。こっちは絵に社会性を持たせようと考えたんですよ。
坂上:「絵はいかにして戦争への現実の流れに抗し得べきか」って本にも書いてありますね。
池田:反戦ってことですね。そういう議論が「プボワール」ではほとんどなされない。「世紀の会」から別れて「プボワール」っていう美術独自の会として作ったでしょう。ところが朝鮮戦争がはじまって社会的政治的問題をさておいて、美術だけのアヴァンギャルドで行くわけです。山口勝弘さんとか北代さんとかはそういう面が強い。僕なんかと違うなあと段々思いはじめて。この辺で辞めましょうってことになったんです。そして僕らが辞めるって事になった事で解散になった。
僕らはすぐ「NON」っていうダダ的な名前で、近くに住んでる連中、阿佐ヶ谷、高円寺の連中が集まってグループを作ります。殆ど同時期に北代、山口は「実験工房」っていうものをつくるんです(1951年6月)。これは瀧口さんが名づけて、武満徹など。美術だけじゃなくて音楽もあわせて総合的なグループ。僕は少々文学的要素が強かった。その後また安部公房との付き合いが続くことになるんです。シュルレアリスムに文学的要素が強いでしょう。この「NON」って言うグループは、長続きすると、馴れ合いになるからそれを嫌って、はじめから一回展覧会をやって解散っていう風に決めたんです。約束どおり1年後に展覧会をやって解散しました。
坂上:大きな画面に共同制作をされてますよね。
池田:300号の共同制作をやった。それも人称(名前)を消してそれぞれABCという記号になって。じゃんけんで順序を決めて、その順序で描く。それでお互いを遠慮なく否定してもいい、という申し合わせで描く、つまり妥協しない。その上で絵をどうやって描くか。合作だけど、お互いの妥協なしにどんな絵ができるか実験です。それで方法として、一番最初にテーマだけ、「現代」というのも、話し合って決めた。後は全く話し合わない。方法としては一番最初の人が10分間描く。あんまり長く最初に描くと次に影響が強いから。次は20分、その次は30分ってひとまわりしてね、1時間になったところで、次からは2時間づつ。一日ひとりずつ。阿佐ヶ谷に12畳のアトリエを僕は借りていたから、そこに共同でお金を出し合って300号のキャンバスを置いて描いたんですね。一日二時間ずつ描いた。前に描いた奴のが自分が気に入らなかったら容赦なく消していいっていう約束だから、筆洗油みたいなもので、気に食わないと思ったら消すんです。だけど前に描いたのが乾き始めてるからすぐに消えないんですね。特に消されるの覚悟で太い刷毛で強い線を描く。そんなものは中々全部は消えないです。それで描き足すでしょう。消えないで残ってゆき、全体の形はどんどん変わる。描いているうちに、アンデパンダンが迫ってきたんですね。誰かがアンパンに出そうって言い出してね。どっかに、見せたいって気持ちがあったんですね。発表するっていうのが念頭になくて描いていたわけじゃないんですね。審査がないから持ちこんだらいいだろうと。出そうとなったら多少見られるようにしようという気持ちが働くんでしょうね。体裁を作り始めて何となく納まりはできてきたけどつまらない、最初の勢いがなくなりました。妥協しなくて思った通りの事を描くという勢いがなくなってきて、まとまってはきたけどどうもならない中途半端なものになりましたね。(注:読売アンデパンダン展 1952年2月28日~3月18日)
坂上:丸善画廊での展覧会は。(1952年7月14日~19日)
池田:その後です。グループ展は。アンデパンダン展は2月。瀧口さんにどうですかって見てもらった。瀧口さんが何を言ったか覚えてないですけどね
西澤:新聞に評が出てましたよ。
池田:え、載ってましたか。
西澤:実験工房のところに出していて、瀧口さんが書いてました。「なんか制作過程は面白かったけども結果は…」というふうに。
池田:実験工房も実験としてやってますが、「NON」は共同制作の実験としてね、誰もやってない実験ですよ。お互いに否定して何が出来るかという実験ね、話し合わない。前に描いた奴を容赦なく消していいと。ABCと人称までを消して。
西澤:そういうオリジナリティを消す考え方、発想はどうして生まれたんですか?
池田:誰が誰を否定するという考えじゃなくて、自分自身の否定をする事も含まれるからね。人称を、名前にこだわる個人を消そうということになった。ちょっと正確には覚えてませんけどね、記号にしようと思ったんですね。誰々の作品といわないですむと。
坂上:「NON」の活動をやっている頃に、それまで抽象か具象か定まらない感じでしたがこの頃「ものを見て描く」地点に立ったと本に書いてあります。
池田:それはねえ、やはり共産主義とか社会主義とかは、大衆の存在抜きには考えられないというのがあって、大衆に抽象的な絵って、わからないと言われるわけですよ、もちろんシュルレアリスムだってわからないといわれているわけだけれど、かといって普通の印象派的レアリズム、自然主義レアリズムは過去のものとして僕は否定的に考えていた、そこに戻るわけにはいかないから新しいレアリズムという事で、一応シュルレアリスムを踏まえた上でのレアリズムというのを模索する形で具象的な形態をとるんですね。だからその方法論の中にはかなりシュルレアリスム的な要素が入ってるんです。「超現実」だけど、現実の「もの」が重要です。
坂上:使っているモチーフも。
池田:モチーフというより、関心は外部の社会的問題です。特にそのころの共産党は、朝鮮戦争以前からアメリカによって非合法化されていたでしょう。幹部は皆追放されて地下に潜っている。その地下に潜った連中が秘密会議を開いている。その場所に僕のアトリエが…… これあとになって、どうやら安部公房の斡旋だってわかったんですけどね、その少し前、ある日、彼が僕のところにやってきましてね、「いい所だなァ」なんて言っていたし、いついつ会議をやるからその間貸してくれって、僕のアトリエはちょっと出入りする人がわからない状態になっていたんですよ。秘密会議にはもってこいの場所。しかも鍵なんかかけないから、誰でも出入り自由です。
坂上:泥棒なんかは……
池田:入らないですよ、持って行くもんなんて何もないから、第一、絵だって、大衆にわからないのを持っていくわけがないじゃないですか(笑)。その他、何もとられるものはないです。
会議があるときは前もって知らせがくるんです。明日お願いしますって。そのときに伝令役の若い党員が僕の絵を見て、これわからないですね、っていうんです。大衆にはわからないですよって。なんで骨になった魚が泳いでいるんですかねえって。大衆って言葉を、いや「人民」っていう言葉を常に彼らは、使いたがるようです。「共産党に入らないか、入らないか」って言われたんですが、入ったらこんな事を言われるのはかなわないと思って、まあそのうちに、と逃げてついに入らなかった。でも周りはみんな、絵描きも「NON」のグループも4人くらい共産党に入ってましたよ。安部公房も、花田清輝も野間宏も。
「人民芸術集団」っていうのを安部公房はつくったんですね。51年に(1951年6月1日に第一回集会)。その少し前に「世紀の会」を解散したんです。それで人民芸術集団をつくって。その頃僕らは「NON」を作って間もなく。それで僕とか福田恒太とかそこに。しかしそれは芸術運動じゃなくて、その年「世界青年学生平和友好祭」っていうのがブタペストで開かれる、そこに代表を送ろうと。代表は阿部公房のつもりでね、そういう運動だったんです。その集まりが何度か勅使河原宏の西荻の家であって、ポスターを描いたりしましたね。それはしかし間もなく、代表は送れないということになったんです。外務省が旅券を出さないんです。だからそのまま。「人民芸術集団」の集まりもなくなった、
その後に「エナージ」(1953年2月結成)です。「NON」を解散してから。「NON」にいた仲間の三人、福田、山野卓造、僕の三人で作ったんです。その少し前に「青年美術家連合」っていうのをつくろうって動きが始まるの。52年末くらいから。その動きの中心が山下菊二さん。前衛美術界というグループのメンバーが中心になって僕もそこに加わって。
西澤:「エナージ」の頃にいろいろなルポルタージュをやりはじめたんですか?
池田:ルポルタージュという意識を持ちはじめたのは、その頃山下菊二さんがルポルタージュ的方法、つまり現地に行って色々な事情を調べた上で作品にするという、それは「あけぼの村物語」っていう山梨県で起こった事件に基づいて作品にしたんです。文学の方では、安部公房が『理論』(1952年8月)という左翼雑誌に「新しいリアリズムのために」という論文を載せていて、その中に、これからのレアリズムはルポルタージュという方法が有効であるという主張をしているんですよ。それはもちろん文学の問題としてね。彼自身も九州で行われていたダムの反対運動ですね、熊本の山奥にあるダム建設反対運動の見聞に行ったりしてる。そのころ彼はルポルタージュを盛んに提唱していた。
ルポルタージュ運動っていうの、ルポルタージュを彼と真鍋呉夫が中心になってつくった「現在の会」で、『ルポルタージュ叢書』っていう小冊子を作り始めた。そのルポルタージュを、美術で可能であるかどうかという事を試そう、試すというよりも実践しようという事で、まずは人民文学から頼まれた仕事をしました。それが53年の春です。
「青年美術家連合」(1953年3月~1956年)ってのが同じ年の3月に結成されるんですよ、その直前にわれわれ三人、福田・山野・池田で「エナージ」というグループを作っているんです。その「エナージ」でね、立川に行く。立川に行ったのが4月かそこらじゃなかったかな。そこで色々実際に見たり調べたりするわけです。立川の状況を。それで須藤伸一と言う詩人が文章を書く。我々は絵を分担して描く。それは意識においてはルポルタージュですね。「青年美術家連合」は機関紙『今日の美術』というのをすぐに出し始める。最初から編集委員として編集にかかわって、表紙も僕が担当。『今日の美術』って僕のレタリングです。そこに絵画におけるルポルタージュの問題っていう文章を載せるんです。それがルポルタージュを絵画に意識的にとり入れたはじまり。おそらく山下菊二さんはルポルタージュという意識じゃなくて、事件を、空想で描くんじゃ駄目だからってんで山梨県にいって話を聞いてそれを基に描く。ルポルタージュだけど意識的にははっきりしていなかったでしょう。彼らはその前に小河内ダムの建設現場に共産党から派遣される形で入っていくんですね。桂川寛や尾藤豊など山村工作隊として。二ヶ月近く。労働者と一緒に生活をともにして描いた絵がある。それも結果においてはルポルタージュという事になるけど、意識においてはまだはっきりしてないです。僕は安部公房のそれに関わっていたから、はっきり絵画におけるルポルタージュという意識を持って、内灘に行ったんです。だけど結局どうも成り立たない。難しい。困難だなんていうのは内灘に行ってわかったんですけどね。つまり時間的な経緯を写真なら写真でぱっぱと出せるけれども、内灘の問題を一枚の絵で示すにはねえ、だから僕はシリーズという事を考えたんです、「内灘シリーズ」と。シリーズで描くという方法を取ったけど、それでも非常に難しいとわかった。それによって《網元》(1953年)を描いた。僕は実際には網元に会った事はないわけです。話を聞いてね、網元がどういう状態であるか、どういう役割をはたしているか。聞いた話では補償金の問題がある。それを網元がもらうんですね。それでわずかなお金が舟子漁民たちに渡る。そういう構造になってる。だから網元たちにとっては、基地反対は切実ではない。一方的に浜辺を奪われて接収されて漁業ができなくなった連中たちはもちろん生活に直接響いてくるから反対闘争をやってます。でも結局は基地に浜を提供しているということは、網元自身が自縄自縛。戦争に加担しているということになるわけで、そういう意味で首に縄を巻いて自分のものとして持っているつもりの舟を手に持たせて、骨だけになった魚が泳いでいる。漁民にとっては取れない魚ですから、骨だけの魚と同じ意味ですね。そういうのを描いたけどいちいち説明するわけにいかないでしょう。だからわからないですねと言われると。その時は一応説明するけど、いちいちみんなに説明するわけにはいかないしね。
坂上:この頃に油からペンの方に切り替わってますね。
池田:それはね版画、エッチングをやろうという考えがあって。それと油絵がたまってくると居場所もなくなってくる。紙だったら100枚描いてもいくらもかさばらないじゃないですか。油絵は材料も高いから買えないんでキャンバスをつぶしちゃ描く。練習のつもりもあって古キャンを白く塗りつぶして描くのです。その他大衆性という問題がひとつあってね。版画は何枚か一緒に刷れるでしょ、そうすると複数の人に渡せるし、買ってもらう人にも安く買ってもらえる。だけど版画も、エッチングやりたいけどプレスを買うお金もないし、置く場所もない、それでエッチングをやるんじゃなくてペンで描く。練習も含めてペン画をやったわけです。
坂上:そのペンのタッチが結果的には池田さんのスタイルの確立に結びついていきますね。
池田:ペン画はね、線をスーっと、皆同じ方向にそろえて描く方法もあるんですけど、僕はわざと縦横無尽に線を走らせて、それで黒い面をつくっていく、そういう方法です。
坂上:その頃は周りの人もモノクロームに近い色彩ですね。心象的にあまりカラフルじゃないんですか?
池田:岡本太郎は対極主義であえて赤とか黄色とか青とか原色に近い、お互いに調和しないような色をわざと使うという。
坂上:戦争直後は町がすさんでいるのに油絵は明るい。しかし10年たって作品は逆にモノクロームになってきて……
池田:それと僕は色を使うと甘い絵になる感じがするのです。でもユーモアの要素は多少意識的に。乾いたユーモラスなもの。いわゆる浪花節的な湿ったのは嫌です。乾いたユーモア、笑い。そういうのが好きです。ただし綺麗で甘くて華やかっていうのは避けたくて、だんだん色が、とくにペン画は色使わないから、モノクロが多くなった。だけど反動的にたまに派手な色を使いたくなって赤とか黄色とかを使うんですね。
坂上:1953年に「エナージ」は解散しましたが、その原因は3人の絵画性のずれというのが表面の理由。しかし裏の理由には政治的なものがという風に『夢・現・記』に書いてありますが。
池田:ひとつは共産党の中でスパイ事件が起きたんです。一緒に内灘に行った党員の一人。立川にも一緒に行ったその人で、内輪ではそんなに密につきあってない。一緒に行って帰りは別々だったんですけど。その人が内灘から帰ってしばらくたったらね、共産党で査問委員会にかけられたんです。スパイの嫌疑で。で、あの人スパイだったのかと驚いたんです。それがずっと後になって、結果として濡れ衣だったって事がわかったんですけど。それで共産党を追放されてるんです、そういうことね。だから共産党ってやたらに疑心暗鬼になって。
でも一応革命という事は真剣に考えているんですよ。このままじゃ世の中駄目だとか、その当時は社会主義、社会主義の形態が一番人間にとってはいい形態だ。資本主義は資本家が搾取して、会社で労働者は働かされて、安い賃金で、儲ける奴はどんどん儲けて。そういう状態は正しくないと。だから社会主義って完全な理想じゃないけど、平等なんて実現しっこないけど、金持ちも貧乏人もいない同じ位の生活をして、誰しも食いっぱぐれはしない、ほどほどの状態、極端な差がない、そういう状態が人間として一番理想的な形態だろうと思うんです。だからそういう意味で僕は資本主義をなくさなくちゃ、そのための革命って考えていた。そういう意味での社会の変革。アメリカの家来のような状態から脱却して、天皇制もなくして、それでみんなが平等になるような方向に歩める形態が社会主義だと考えていた。安部公房も「革命は近いよ」とか言っていた。漠然とそれは1957年あたりだなんて言ってたんですよ。
西澤:初個展についてですが……
池田:それはねえ、1954年がはじめての個展ですね。養成堂画廊。まず53年がルポルタージュ、内灘とか行ったりしたでしょう、その作品をアンデパンダンに出すんですよ。その頃はもうひとつのアンデパンダン、日本美術会のアンデパンダンがあって両方出してるんです。読売はどうしようかと思っていたんです。結局《網元》を出す気になって出したんですが。それを安部公房が評を書いて、新聞に名前が出たんですね。それから結局美術批評とかそういう雑誌なんかの取材を受けたり文章を書いたりするようになって、この辺で個展をやろうかという気になったんです。それが翌年の54年。それで瀬木慎一が、「養成堂画廊は夏は借り手がないから安く借りられるはずだから夏やったらどうだ」って言ったんですよ。8月は借り手がないから、おそらく半額くらいになるって。交渉したらそうなった。それで借りてやったんですよ。その前にね、養成堂画廊から時々展覧会の葉書が来るようになって、行くようになっていて、そこで芥川紗織が僕の2回くらい前にやったのを見てるんです。そこで芥川さんと知り合った。
西澤:この個展をきっかけに「制作者懇談会」の粕さんとかと知り合いに…
池田:そうです。粕三平も多分その前から。はっきり覚えてないけど。僕の個展に彼は来てる。風呂敷になにやら土器(かわらけ。陶器片)みたいなものをガラガラ持ってきましてね、考古学に興味をもっていたんです。そのころ島村潔と、石井茂雄と二人で展覧会をやってる。多分僕のあと。それで二人とも知りあった。芥川紗織ともそこで知り合っている。翌年、瀧口さんがタケミヤ画廊で55年に僕に個展をやらしてくれた。そして僕より後だったかにそこで吉仲太造が個展をする。吉仲の事は54年の段階で行動美術に出していて彼の仕事を知っていたが…。河原温は53年の「ニッポン展」ね。青美連が開いた「ニッポン展」に《浴室》シリーズという衝撃的な作品を出品して、それで友達になった。そういうことでどんどん僕の友達がその前後に増えていくわけですね。だから粕三平はね、多分ね、はっきりしないけど多分53年です。54年の個展の時はすでに知っていた。個展にやってきて。土器の事を覚えているから。
西澤:『夢・現・記』では個展のときに知り合ったとことになっていますね。
池田:じゃあそうかもしれないですね。しかし、54年だとしても、ごく初めのころ。石子順造もそうなんです。同時期に知りあっている。二人とも高円寺で歩いて来れる距離にいた。特に粕三平は知り合って間もなくは、毎日のようにやって来た。朝早く僕が寝ているときにね、勝手に入ってきて、「いけださーん」って、庭から用事をいうんですよ、箇条書きで。「今日は何々と何々の用で来ましたー」って、大きな声で口実のために作った用件を言いながら、階段を上がってきた。彼は箇条書きでラブレターも書いたんですよ。そういう生真面目な男だったたんです。
坂上:では、とりあえず次回は制作者懇談会の話からはじめましょう。