末永蒼生 オーラル・ヒストリー 第2回
2019年12月1日
東京のアトリエにて
インタヴュアー:細谷修平、黒ダライ児、黒川典是
書き起こし:五所純子
公開日:2020年11月13日
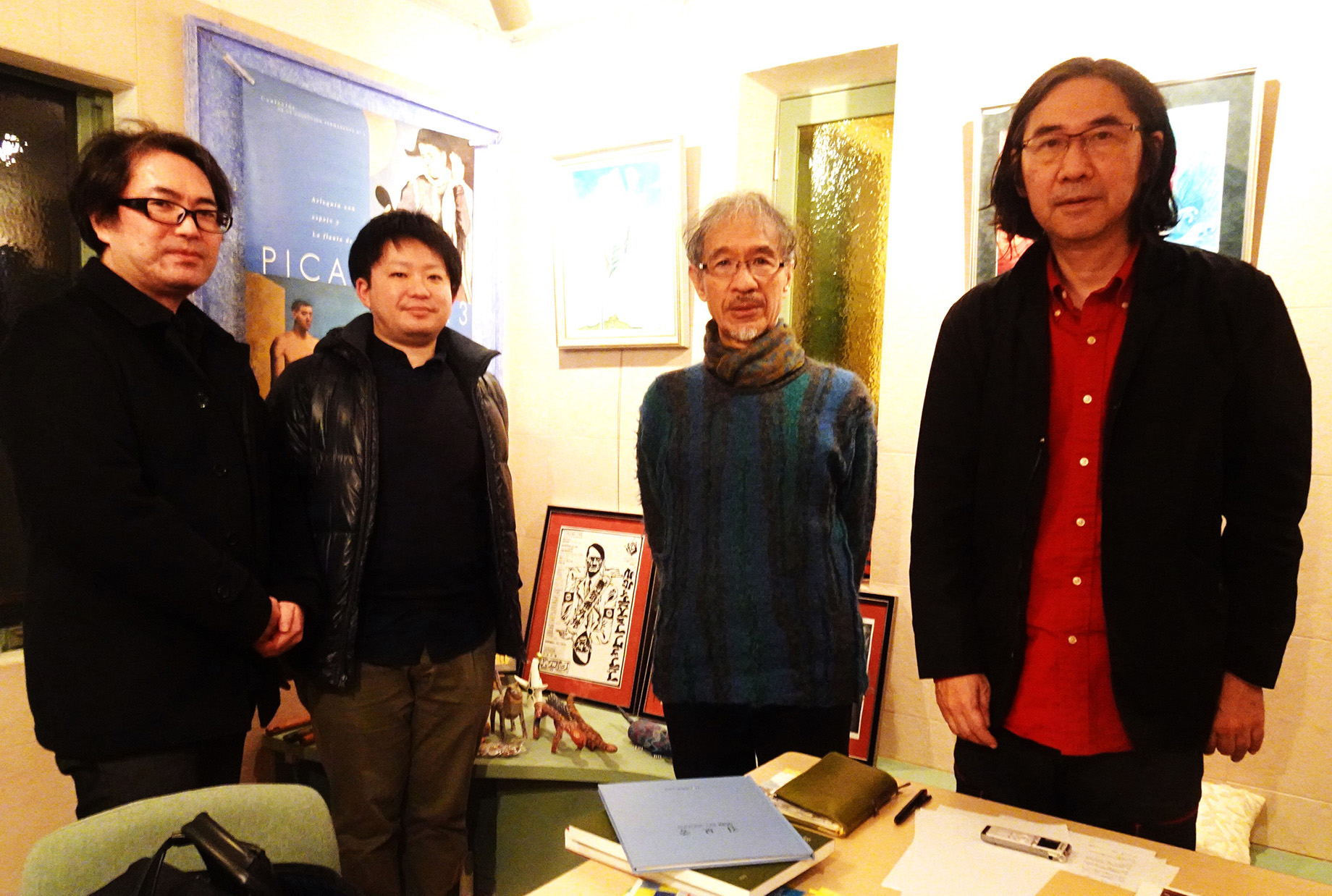
黒ダ:昨日見せてもらった雑誌をデジカメで撮って二人にも送ったんですけど(末永蒼生「『文化』が崩れ去る時」『流動』1979年5月、末永蒼生「全共闘世代の家族の組み方 彼らと子育て・仕事を語り合って」『思想の科学』1979年3月)。
末永:僕も『流動』は忘れかけてたんだけど、今回いろいろ見てて、1960、70年代に何を見るかっていうのを、ちょうどあのタイミングに書いていたので。昨日もお話した背景みたいな部分とわりと重なってたかなという気がしましたね。昨日、時系列的には70年代に入ってからのことも出てきて。
黒ダ:ちょっと戻ろうかと。
細谷:はい。なので昨日聞いているところは少し質問を飛ばしながらいきたいと思います。昨日も政治と表現というか、政治と芸術の話がありましたけれども、第二次羽田事件(1967年11月12日)に行かれて、これは撮らないといけないというか、すごいことが起こっているというお話が。第一次(1967年10月8日)は?
末永:行ってないです。
細谷:そうすると、いわゆる闘争の現場というか、政治の場所に行ったのは第二次羽田事件が最初ですか。
末永:そうですね。〈クロハタ〉の松江さんが第一次に行ってるんですね。で、たぶん第二次があるからってことで、昨日言ったようにしょっちゅう会ってたので、じゃあ行こうって。
細谷:第二次羽田は、松江カクさんと、ということですね?
末永:ええ。
黒川:情報としては松江さん経由だったんですね。
末永:そう。あの頃は松江さんとアート系の、アングラ・アート系のというか、その周辺の人たちとの付き合いがあったので、そっちからの情報がいろいろ入ってたわけですよ。彼はすごく政治的な志向があったので。ただ、彼の政治志向は左翼とか全共闘運動とかとは全然違う方向で、すごく、何だろう、民衆の権力に対する、あるいは体制に対する憤りみたいな、そういう体質をもってた人ですよね。だから彼の祭文(さいもん)[語り]というパフォーマンスというか儀式なんかも非常に泥臭いところがあって、そういうことから政治的な現場にアプローチしていくというか関わっていくところが、僕にとってはピンとくるところだった。
細谷:では、政治に末永さんが関わっていくのは、松江カクさんがキーパーソンというか。
末永:ひとつのきっかけになりましたね。それで実際、集会とかデモとか僕もよく顔を出して、昨日もちょっと話したようにすでに〈声なき声の会〉とかに関わっていたので、とにかく社会全体がものすごい大きなうねりを起こしているんだなと、それがいろんな層から出てきて、非常にワクワクするものがありましたね。そっちの波が大きくうねってきているワクワク感みたいなものから見て、逆に既成の美術の世界のほうがちょっと内向しているというか、シーンとしているんじゃないのっていう。自己変革がなかなか起きてこないという状況があったでしょう。だからやっぱり、ああいうハプニング・アートとか街頭でいろんなことをやっていくとかアングラ・アートとかいうのが出てくるのは、必然だったという気がしますね。
黒ダ:おっしゃることはわかるんです。しかし、60年代後半、67年以降とかに政治の季節になっても、当時の日本の現代アートって、そういうものを反映したというか応答した作品ってほぼないんですよね。
末永:ないですよね。
黒ダ:あるかもしれないけど、あっても歴史的にあとから顧みられなくなったので、むしろどんどん内向していると言ったのは、僕は正しいかなと思いますよ。美術制度ができちゃったんですよね。制度的にだんだん画一化されていった。もう美術業界の中でもそれなりの出世コースができていっちゃっている。その最初くらいじゃないかと思いますね。
黒川:「前衛美術」という言い方よりは「現代美術」という形で制度化されていった過渡期。
末永:なるほど。ある意味、「前衛美術」の代わりに「現代美術」という言葉に置き換えていかれることによって、毒を抜かれたよね。牙を抜かれたというか。安全圏で、でも話題になってそれなりの業界としての位置づけがあり、アーティストもそこで肩書きをもって活動の場が作られるようになったという感じがするので、ちょうど同じようなことが音楽でも起きてて、最初はロックンロールとかロック・ミュージックが出てきて、アメリカやイギリスがきっかけで入ってきたんだけど、相当社会全体を敵に回すような形で彼らは出てきたわけじゃないですか。で、それこそ内田裕也じゃないけど、それをそのまま日本にもってきたといって騒いでいたわけだよね。僕も彼に何度か会って、僕たちがやっていたところにも彼が顔を出していたりして、まだそういうのがありえたわけですよ。それがいつの間にかポップスとかニュー・ミュージックという言葉に置き換えられて、逆に安全な商品としてもっていかれてしまったというのと非常に共通したカテゴライズ化がアートの世界でも起きてたなと、今聞いていて思いました。
細谷:ちなみに末永さん自身は、黒ダさんの本のタイトルじゃないですけど、アナキズム、アナーキーとか、そういった何か、別に無政府主義とかいうことではなく、アナーキーみたいなところに関心というのは当時ありましたか。
末永:それはもうちょっと遡ると、シュルレアリスムという形になる前のダダの時代というのはある種、非常にアナーキーなものだったじゃないですか。それまでの美の概念とか美術の置かれている立場とか秩序というものを超えて、1回バラしてしまおうというようなことですよね。ほとんど偶然性みたいなことで表現していく。それがシュルレアリスムという形でちょっと整えていかれるわけだけれども、最初は、僕たちが松江さんとか〈ゼロ次元〉とかと関わってやっているときは、かなりダダ的だったと思う。そんなきれいなスタイルとかメッセージというよりも、まず1回ひっくり返してみよう、バラしてみようというようなことだったので、その感覚からいうと、自分たちの中にそれはあったような気がするんですよね。
黒ダ:そもそも黒旗ってアナキズムのシンボルなんだけど。
末永:そうなんだよね。
黒ダ:それは知ってて〈クロハタ〉とつけていたんですかね? あの人たちは。
末永:たぶん知ってたと思いますよ。
黒ダ:知らないわけないですよね。かわなか(のぶひろ)さんに同じことを聞いたら「いや、あれは単に赤旗に対してクロハタと言っていただけ」としか言わなかったんだけど。
末永:松江さんもそうだし、鈴木史朗さんとか高原(裕治)さんもそうだけど、かなりいろんなことをよく知ってた人なので、それはわかってやってたと思いますね。
細谷:ちなみに〈告陰〉でいろんな名前を旗に入れて、旗を持ってデモに出ていますよね。(1967年夏のデモの旗「告陰 共闘会議」の写真を見て)この旗の色は?
末永:これはね、白に黒ですよ。
黒川:(1969年10月のデモの旗「告陰 万博破壊教頭派 こえぶくろ連合 東京マンガゲリラ」の写真を見て)こっちは?
末永:こっちは黒ですね。
黒川:ここが黒で、ここは赤っぽく。
末永:赤じゃない。本当に黒っぽい。白抜きで字が入ってる。カラフルな感じの色は使ってなかった、当時は。わりと黒っぽいイメージでやってました。
細谷:なるほど。別に黒にこだわるわけじゃないんですけど、一応聞いておこうと。
末永:話が前後して申し訳ないけど、ここで〈PEAK〉を始めたじゃん。〈告陰〉から〈PEAK〉へという段階があって、明治公園でやったじゃないですか(1970年4月28日)。それでこのときは本当にもうバンドを組んで、いきなり即興で演奏することをやってたわけよ。
細谷:ストリート・ファイティング・ロックですね。
末永:『アサヒグラフ』(1970年5月15日)がこれを大きく出したわけ。それは多少知ってる人が書いたわけよ。なので、その記事ではたしか、「告陰というグループが」と書いてある。〈PEAK〉じゃなくて。〈告陰〉時代からつき合いのあるジャーナリストだったので。だから〈告陰〉が今度はこういうことをやってるんだな、くらいの感じよ。僕たちとしたら、いきなりここで〈PEAK〉にバーンと切り替えちゃって。昨日見ていただいたフリーペーパーもそうだけどね。これ(モノクロ写真)はカラーじゃないからわからないけど、ここ(写真に写っている横断幕)はほとんどカラフルな色で描いてる、「ストリート・ファイティング・ロック」というの。
細谷:そうですよね。文章(『生きのびるためのコミューン 幻覚宇宙そして生活革命』、三一書房、1973年)にお書きになっていましたけど、『PEAK』の2号とかすごくカラフル。
末永:もうひとつ(『PEAK』1号の)色を重ねたバージョンがあってね。
細谷:これはでも、かなり意識的に色を使おうというのがありましたか。
末永:ありました。同じものを二重に写してるだけなんだけど。
細谷:バージョン違いなんですね。
末永:そうそう。重ねちゃおうということで。このへん(『PEAK』1号、p. 2)は金坂(健二)さんが写真とか出してくれた。〈告陰〉のときはモノトーンのイメージが、ちょっとアナーキーなイメージがあったと思うんですよね。そこをなぜこういうふうに変えたかというのも、やっぱりそのときの僕の転換、戦術的な転換もあるけど、何より意識の転換がまずあって、ということですよね。というのは、〈告陰〉が、〈万博破壊共闘派〉がひと山超えて、昨日話したけども、その後どっちの方向に行こうかということとすごく関係があって、簡単に言えば、〈共闘派〉の逮捕とか弾圧みたいなものも関係してるんだけど、ああいう物理的な直接行動の限界を感じたね。それで、たぶん反戦運動とか学生運動とかやってる人たちも、本当はそれを感じてたと思うんだけど、まちがったと思う、彼らは。権力の罠にはまったことを感じるべきだったと思う。そしたらね、連合赤軍事件は起きなかったと思うんだよ。要するに、意識レベルでいくら社会変革なり革命なり言っても、観念と観念のぶつかり合いじゃないですか。体制も観念でやってるわけだからね、結局。
細谷:そうですね。同じ土俵でやってるということですよね。
末永:そう、やってるわけだから。そこを考えるとね、暴力装置をもってる権力には絶対敵わないというのを、ものすごく肌身に感じたわけだよね。そうすると、どこに働きかけるべきなのか。意識だけじゃダメだと。言葉だけじゃダメだと。やっぱり、もっと感覚とか感性とか無意識とか、そっちの方向に響くものじゃない限りダメなんだっていうね。逆に戦略的にそっちに行くしかない、そっちのほうがはるかに有効だというふうに思ったのが、〈PEAK〉を作った僕の考えだった。それはこの新聞(『PEAK』)とかでもわかると思うけども、69年の終わりから70年にかけて、昨日も話したけども、おおえ(まさのり)さんとか金坂さんとの交流があったじゃないですか。おおえさんの方向から一種のドラッグ・カルチャーが入ってきたわけですよね。あの頃、僕たちもドラッグを体験したりして、幸いにあのときはまだLSDが麻薬指定になってなかった。みんなでパーティーやろうよと言って、合宿みたいにしてそういう経験をたっぷりしたことがあったのね。それはやっぱりね、ドラッグ革命みたいなことが当時アメリカで盛んに言われていたけども、誰かいたよね、アメリカの先生でドラッグをどんどん使って……
細谷:ティモシー・リアリー(Timothy Leary)。
末永:そう、ティモシー・リアリーの書いたものを何かでチラチラ僕たちも見たりして。最初はドラッグ革命はね、僕たちの経験から言っても、ありえたんだなと思ったの。本当にね、意識がぶっ飛んじゃうのよ。理性とか刷り込まれた価値観とかが全部ほどけてしまって、意識と潜在意識の境界線がなくなっちゃうのね。すごい経験をしちゃうわけ。時間とか空間も飛んじゃうし。そうすると、そこで人間が丸ごと生きている感覚がわかる。本当はそこが人間の母体というか基盤なんだと。そうすると、そこに何かが働きかけない限り、いくら表層の意識をやりとりしてても何も変わらないということが実感としてわかったのね。結局、歴史上のいろんな革命、フランス革命でもロシア革命でもそうなんだけれども、革命を起こすじゃない? あれは完全に観念の革命と言ってもいいと思うんだよね。もちろん下層階級の人たちが反乱を起こしてああいうことが起きるんだけれども、そのときにどうやって次の世界をつくるかということは、観念でしか考えられないわけじゃない? 自分たちは経験してないわけだから。そうするとどうなるかというと、土台は変わってないけどそこ(観念)だけ変えようとするから、ロシア革命もフランス革命も結局、すごい暴力的な独裁体制になっちゃう。
細谷:どこかが犠牲にならないといけなくなる。
末永:そう。ものすごい虐殺が起きたわけでしょう。だから、権力と対峙したとき、下部構造というか下層意識に向かって揺らしていかないと、偽物の革命がずっと歴史上起きてただけというのが、すごくはっきりしたということかな。それを表明するひとつのパフォーマンスとして、とりあえずロックがまだ力をもっていたし、音楽が力をもっていたので、じゃあそれで行こうと僕たちはストリート・ファイティング・ロックというので、日比谷とかいろんなストリートで毎日のように、これを続けてたわけですよ。でも、いろんな芸術運動とか政治運動もそうだけど、どんなに新しいことをみんなでワーとやろうとしても、結局はそこにどうしても上下関係ができたりとか、引っ張る人と引っ張られる人が、リーダーとリーダーについていく人がいるということがくり返されていく。
細谷:主従関係になってしまう。
末永:これはどこまで行っても人間って変わりきれないなって。ストリート・ファイティング・ロックだってどんなに看板を作り変えても同じことをやってるだけじゃないって、さっきの話と同じなんですよ。ただ、どうやって個々の人に、個別に働きかけていくかということが、僕の方法論としてそこで身にしみて考えたことだったから、そこからさらにアートセラピーの世界に入っていったのは、それが大きいですね。
黒ダ:今のでちょっと関係するけど、あとで(公開するときに)削ってもいいけど、ドラッグをご自分で体験されて、そういう人たちも周りにいたと思うんだけど、結局ドラッグに頼ってはいけないという意識も同時にあった?
末永:それはね、僕はそんなにたくさん体験してるわけじゃなくて、本当に1回で効いちゃったみたいな人だったの。
黒ダ:ちなみにマリファナ?
末永:LSDとマリファナと、いろいろあったけど。今のはすごく大事な質問だと僕は思うんですけど、そのとき一緒にパーティーに参加してた人の中で、僕はわりとポジティブな幻覚というか体験をしてたんだけど、参加してる人の中にね、ものすごくバッド・トリップしちゃった人がいる。それで警察に追われてるとか、警察が今来てるに違いないとかパニックになる。そこでわかったのは、ドラッグでハッピーになるというんじゃないんだよ。ドラッグはひとつのきっかけであって、覚醒するわけじゃない? 意識の蓋が開いちゃう。その人の普段の自意識とか理性の蓋がポンと開いちゃったときに何が出てくるかは、その人の潜在意識の中にあるものが出てくるだけなの。だからネガティブな自分に対する感覚を根深くもっている人は、それが出てきちゃうわけ。極端な場合は地獄に行っちゃう。つまり、その個人の深層にある“地獄”が表面化する。それでわりとポジティブに感じるものが強ければ、そっちが拡張する。要するに意識拡張と言われるやつだけども。だからそうなると、おおえさんがインドに行くのもわからなくはない。別にそういう手段をとらなくても、瞑想を通して自分の内なる世界を目覚めさせていくという方法だからね。でも結局、基本は同じかなと僕は思ったんですよ。やっぱり、そこにどういうふうにアクセスしていくかっていう、自分に対しても他者に対しても。そのときに僕はたまたまアートを、美術をやってたので、その目でもう1回見直したときに、アートってそのひとつのツールだよねって思った。
黒ダ:そういうツールをもっている人はよかったんでしょうけど。あるいは蓋が開いたときに悪いものしか出てこなかった人ってけっこういっぱいいたので、そういう人を見たから、自分はやっぱりドラッグを使うのはやめた? いっぺん蓋が開いたら、ドラッグをやめても開けっ放しなんですかね。
末永:僕の場合はそれに近かった。もちろん実際の生活に戻るとさ、日々のいろんなことに対応しなきゃいけないわけだから、一応ね。でも心を制限している自我を1回パーンと取り払われるのを知ったというか。もっと強い言い方をすれば、思い出したのかもしれない。別の言い方をすると、幼児期とか胎児のときとか、もっとそういう原初の状態……。これはトランス・パーソナル心理学の領域に入っていくと思うんですけども、自我が植えつけられる前の無条件の状態に1回回帰するというのかな。それで、いかに社会的な規制や教育が埋め込まれていたかということもわかった。だからあとはそれを自分で取り払っていくだけだと思ったし、取り払い続けないと常に入ってくるからね、ネガティブな情報も。そのときにアートが、ドラッグを使わないでもう1回そういう世界に行ける可能性をもっている方法論でもあるし、無意識に対する通路でもあるはずだっていうね。フロイトが、夢は無意識への通路だ、王道だということを言ってるけれど、僕はアートがもともとそうじゃないかなと思ったんですよ。
黒ダ:(図を描きながら)こうやって蓋が開いたときにつっかえ棒になったのがアートだったっていう、そういう感じがしませんか。下手したらまた閉じちゃう。
末永:そうそう。また戻っちゃう。
黒ダ:こんな簡単な図でいいのか(笑)。
末永:だからそれはすごくね、意味深なことだと僕は思ってて、だからこそアートが常に表現を更新していく、アーティストが更新していこうとするのは、そういうことだと思う。でも更新しないアーティストもいて、ずっと自分のことをリメイクする人もいる。1回成功するとね。そうすると昨日言ったような話になっちゃう。つまり、いつまでも松葉杖にしがみついているようなもので。
細谷:アート・ワールドだけの話。
末永:そうそう。
細谷:ちょっと話を戻しましょう。昨日だいぶ〈ゼロ次元〉の話とか、いろんな方の話も聞いたので、〈告陰〉が実際やった行為というかパフォーマンスのことを、順を追ってざっと。黒ダさんのパワポを見ながらと思いますが。
黒ダ:最初の「食儀及び美術界葬儀の為の連続儀式」(銀座・あかね画廊、1967年9月)というのがありますね。これってどんなことをやったか。前にも聞きましたけど、食儀というから、何かを食べる?
末永:そうそう。これはね、女性に台の上に寝てもらって、そこにいろんな食べ物を置いて、それをみんなで囲んで、女性の生命を食べるみたいなことだけど、実際は食べ物を参加者に食べてもらうという。そういう象徴的な表現をした儀式だったかな。
黒ダ:女性はどんな格好をしてたんですか。普通に着衣か、あるいは白衣か。
末永:たぶん洋服。上はあまり着てなくてブラジャーとズロースみたいな、水着みたいなものかな。そんな感じだった気がする。
黒ダ:食べ物ってどんな? ごく普通の食べ物ですか。
末永:そうそう。果物だとか普通に食べられる物が置いてあったと思う。
細谷:この行為の発想というか、それは末永さんが?
末永:そうですね。
黒ダ:これ(パワポ写真)……。女性の周りに置いて食べたものでしょうかね。
末永:それは夢土画廊の「増殖計画」じゃないかと思うよ。
細谷:10月、夢土画廊、「オブジェと密室の中の増殖計画」。
黒ダ:67年10月のほうなんですね。これはどんなことやったんでしょうかね、夢土画廊のほうは。
末永:最初はこれ、怖いアイデアがあって、猫を抱えている人が女性なの。それで、猫をその場で殺しちゃって、死を通してもう1回再生するみたいなことをやろうと言ってたけど、さすがに画廊だし、まずいかなという。うまくいかないかもしれないし、残酷なことでもあるし、それは形だけにしてやめて。でもイメージとしては生と死の循環みたいなものがあって、増殖計画というタイトルになっていたような気がします。
細谷:最初のほう、このあたりでも使われるんですけど、「儀式」という言葉。何か儀式という言葉に込めたものは?
末永:ひとつはね、当時わりと連携してた〈クロハタ〉の松江さんとか、〈ゼロ次元〉なんかもこの頃は(東京に)出てきて活動していて接点ができてきていて、彼らが「儀式」という言葉を使ってたので、よくある即興的なハプニング・アートとはちょっと違う、様式性をもっているわけですよ。このイメージを人に見てもらう、ぶつけるんだというのがはっきりしていて、能動的な表現形態だったと思うんですよ。ハプニングももちろん能動的なんだけど、そこにいろんな人が入ってくる可能性もあるので、非常にセッション的になるじゃないですか。それとはちょっと違う、よりこっちの世界を能動的に打ち出すという。だから、いわゆるハプニング・アートと儀式というものとのちょうど中間を〈告陰〉なんかはやってた気がするし、街頭ではわりとハプニング的な感じになってたと思うんですよね。通りでワーとやるから人が集まってきて、そのことで起きるリアクションのおもしろさとか、参加型にしていくみたいなことがあって。〈クロハタ〉と〈ゼロ次元〉はわりと儀式が軸になっていたような。それはそれでおもしろかったし、魅力的な……。つまり、日常の中に非日常的な異物を差し出すことによって何かが起きるというのが儀式のやり方なわけですよね。非日常性の中に引っ張っていくみたいなことなので。だからそういう両面が、僕たちもあったような気がしますけど。
黒ダ:やっぱり「ハプニング」という言葉は当時もう普及していましたよね?
末永:してました。
黒ダ:あえてこれを「ハプニング」とは言わずに。
末永:そうそう。
黒ダ:今おっしゃったような意味合いが、はっきり違いがあったということですね?
末永:そうです。だから「儀式派」とか言われてた。
黒ダ:最初誰が言ったんだっけな。
末永:ちょっと覚えてない。
黒ダ:「儀式屋」だったかな。
細谷:あとは、このあとの「食儀」という言葉を使われる。食べるという生理現象というか、食べるということには意識的な何かがあったんですか、末永さんの中で。
末永:いろんなことが言えると思うけど、後付け的には。ただ昨日もお話したように、僕の中にエロスをどう開示していくかということがあって、やっぱりそこには性欲、食欲ということがあるわけで、食というのはある種、性のアナロジー的なものとしてあるじゃないですか。いろんな文学とか映画でもそういう描き方をしているし、本当は境界がないと思うんですよね、そこ(食と性の間)には。だけど世の中的には食べるということはそんな悪いことじゃないので、グルメじゃないけど食というのはいくらでも商品化されるし文化にもなっていくけれども、なぜか性は下半身あるいは下部構造として常にタブーにされていくということがあったので、あえて食をやることで、実はそれはつながっているんだというイメージで、僕の中ではやっていたような気がします。
黒川:この白装束にはどういう意味が? 屋外でも白い仮面とかをしてやっているパフォーマンスがありますけど。
末永:普通の街中でもどこでも、みんないろんな洋服を着て、いろんな色があるじゃないですか。そうすると、それに対してちょっと違うものを出そうとしたら、白か黒になっちゃうんですよ。適当に色があったらその場にまぎれてしまって、異質な感じはしなくなると思うんですよね。だから、たぶん儀式というのもイメージとしてはつながると思うんですけども、儀式的なものっていうのは白か黒かになりますよ。お葬式だったら黒だし、白装束という言葉があったりとか、神社とかもそうですよね。そういうイメージがどこかにあったと思います。
黒ダ:あと、写真を見ても(仮面をつけているので)みんなほとんど顔がわからなくて、誰だかわからなくて困るんだけど、やっぱりそういう個性を消すみたいなイメージだったんですかね? 個人性の違いを消していくみたいな。あるいは男女もよくわからなくしていて。
末永:そう、わからないの、ありますよね。
黒ダ:そういう匿名性。
黒川:あるいは非人称性とか。
黒ダ:そういう意味合いが仮面に?
末永:仮面って僕すごくおもしろいと思うんですけど、人間ってさ、普通は仮面をかぶってないし、素顔で私生活をしてるわけじゃないですか。それ(顔)はもうその人の個性というか、そういうものとして見られるわけだよね。表現するほうが素顔でやっちゃうと、その人のこととして見られるわけだけど、つまり僕は何が言いたいかというと、自分たちが「あの人」と対象化しちゃうわけよ。お互いに顔が違うし、振る舞いも違うから。で、対象化するということは、自分と相手を切り離して、あれは自分ではないというふうになるわけじゃないですか。だけど仮面はそういう意味での生(なま)なものはない、個性はない。見えないわけだから、見てる側が自分を投影しやすいと思うんですよ。別にそれは理屈をこねてやってたわけじゃないですよ。だけど、ああいうマスクをかぶるお祭りとかいろいろあるけども、そういう意味があると僕は思うんですね。
黒ダ:じゃあ他者性を強調するというよりは、むしろ他者性をなくしていくということですかね。
末永:そうそう。自分と他者を分けることによって人間というのは世界と自分を分離してしまっているので、そうじゃない視線をもってくるということかな、と僕は思うんですよね。
細谷:次の質問。「若い世代」、NHKテレビ。これは末永さん、出演されたみたいですが。
末永:うーん、出たのは覚えてますよ。
黒ダ:これは一人で出たのか、あるいはグループで?
末永:何人かで出た気がする。
黒ダ:それで、単にインタビューとかじゃなくて?
末永:ディスカッションみたいな感じだった、スタジオで。
黒ダ:それって何か他の文化人と討議とかじゃなくて、〈告陰〉のメンバーと?
末永:これって何年だっけ。
細谷:68年です。
黒ダ:すごい怒涛のように、毎週のようにやってる。今のは68年1月6日。岡本太郎が出てなかったですか、そのとき。
末永:ああ、「若い世代」。これ68年?
黒ダ:これ私、新聞で確認してますので。67から68年まで「ユートピアを語る」というタイトルでやってたと。新聞テレビ欄を調べたんです。
末永:ああ、そう。うーん、ほとんど僕は記憶にない。出たのは覚えてるけど、内容が。
黒ダ:グループで出たということですね。
末永:うん。もっとあとにNHKのこの番組に出たことがあるけど、それは70年代なんだよね(「若い広場―あるミニメディアの軌跡」、1973年11月4日)。ちょっとこの68年に関しては内容を覚えていない。
黒川:基本的にはトーク番組?
末永:トーク番組だった気がする。岡本太郎がメインゲストで若者とやりとりするみたいな、そんな感じだった気がする。
黒ダ:いかにもありそうですね。
細谷:次がですね、「車と仮面による儀式」(1968年1月20日)、ビックリガードというところ。
末永:池袋ですね。池袋で僕、何度かやってますね。
黒ダ:車っていうのは、自動車? これって『告陰通信』に出てたもので、それ以外の資料はないんだけど。
末永:よく覚えてない。何か僕、西武デパートの前でやったのを覚えてる。
細谷:写真があとで出てきます。(新宿の)アングラポップで〈ゼロ次元〉と一緒にやってますね(1968年1月25日)。
末永:はい。写真あるの?
黒ダ:アングラポップのやつは、ブラック・フェスティバルじゃないときの写真があります。アングラポップは何回か?
末永:やってる。
黒ダ:やってますよね。これはちょっと、これ以上詳しい描写がなくてわからないので。
末永:この頃からね、写真家の平田(実)さんがくっついてた。だから、もしかしたら彼の写真の中にこのときのものが。話した覚えがある。彼が話を聞かせてくれとか来て。
黒ダ:平田のアングラポップ、あったかな(註:『週刊大衆』掲載は平田だが、元写真は現存せず)。
細谷:平田さんってこの頃お会いになってると思うんですけど、けっこう写真を撮って、取材みたいな感じで話を聞かせてくれという感じでしたか。
末永:そうでした。ただ写真だけ撮ってというタイプの人ではなくて、かなりこっちにシンパシーをもちながら話をしたり聞いたりということで、それを記事にして写真で出していくという。
黒ダ:富井玲子さんによると、平田さんはそういうパフォーマンスの人たちの共犯者とか共謀者だったと(註:平田が自分で「共犯者」と言っている)。(別の証言で)やらせをしたこともあったと思うけど。
細谷:それから「ムチ打ちの儀式」、明治神宮(1968年1月28日)で、これは写真が。
末永:『週刊大衆』に出てると書いてあるから(「アングラの若者たち “実験タレント”がゆく」、1968年2月22日)、あるかも。黒ダさんがもってるんじゃないの?
黒ダ:これ、明治神宮でいいのかな。
末永:そうでしょう。そうそうそうそう。『週刊大衆』あったね。これ出てたね。
黒ダ:この中に末永さんいるかな。
末永:これ、僕が撮ってる、8ミリで。
細谷:撮影してるんですね。じゃあ8ミリがあったんですね。
末永:そうそうそうそう。
黒ダ:じゃあ末永さんはパフォーマンスというよりは記録者という?
末永:そう。僕の中で自分が表現することと同時にそれを記録して、何かのイベントで映像も使いながらやるという、二重、三重にやりたかったので、撮るのもやってたんです。
細谷:映像を投影させながら、そこでまた(実演を)やったり?
末永:そうそう。
黒ダ:そうか。「ムチ打ちの儀式および映画撮影」と記録されているので。鞭打ちをやっていたんですかね。
末永:実際にやった覚えはないんだけどね。そんな準備はした覚えないけどね。
黒ダ:それらしい写真はないんですけど。
末永:ない、ない。ないと思う。
黒川:末永さんも白い手袋をされていて、ただ撮影するよりは……。
細谷:入ってますよね、内側にね。
末永:そうそう。
細谷:スーツを着て。
末永:だから結局、儀式的なことをやってる。そして、それを撮影してるという。そのパフォーマンスを(さらに)平田さんが撮ってるという、そういう入れ子状の関係ですよね。
黒ダ:平田さんがいかにもやりそうなやつ。でもその写真は覚えがないと。でも鞭打ちってやっぱりSM的なそういうのに対する(興味があった)?
末永:そういうのはあった気がするね。それは僕たちのイメージの中に出てきたこともあったし。そんなに多くはなかったけれども、池袋でやったやつとかもそうだし。それから〈ゼロ次元〉なんかも、わりとそういうのが映画(『いなばの白うさぎ』)とかでもあったじゃないですか。エロスの問題とどうしてもつながってくるけど、要するに、もうこの世の中全体が、言ってしまえばSMクラブになってしまってると思うわけ、社会というのは。支配と被支配というのがあるわけじゃない? それで支配するのが好きな人もいれば、支配されるのが好きな人もいて、だから企業が成り立つし、究極が軍隊だったり学校だったりということですよね。いかに上手に支配される人間を作るかが学校教育なわけですよ。義務教育を9年もやっていれば、完全にMの状態に仕立て上げられて、そのまま企業に行けばMの社畜として一生そこで働くという、ものすごく仕上げがされてるわけじゃないですか。
黒ダ:鞭打ちは別のあとのところで出てきますけど、たしかに言われてみたら。
末永:だから僕はね、この社会とか文明、あるいは政治的な統治がされる世界というのは、必然的にSMになるようになってると思う。ならない人もいるけど、大半はなるわけじゃない? なるってことは、基本的に人間が人間を育てるという子育て、育児そのものがすでにね、飴と鞭なわけですよ、結局は。そういうふうに親は自分の価値観に合わせて子供を奴隷化しているわけじゃないですか。子供は逃げられないので、最初は。上手にそれを受け入れながらMになっていく。
細谷:この宿題が終わったらこれをやってもいいよ、みたいな。たとえばそういうことですよね。
末永:そう。そういう取引を覚えていくということですよね。だから多くの人は自分がSM趣味だと思ってないと思うの。だけれども、ときどきそれを自覚しちゃう人がいるわけだよね。「ああ、SMなんだ」というふうに。そうするとその人は公然と、というか、ちゃんとそれを趣味としてさ、団鬼六じゃないけども、文化としてちゃんと表現していくわけじゃない? そうすると、その人は無意識のSMの世界から実は一歩抜けてるわけですよ。
細谷:そうですね。自覚しているわけだから。
末永:自覚して表現してるわけだから、抜けてるわけですよ。だけど一般的にはSMはちょっと特殊だとかネガティブなイメージで見られちゃうし、ときにはそれはなかったことにされちゃうわけじゃない? それはなぜかと思ったときに、多くの人が自分がSMをやってるということを、無意識ではわかってるんだけど、認めたくないんですよ。だからそうやって表に露出したものを否定するわけよ。それがタブーになるじゃないですか。性もそうだけど。そういう社会構造になってるし、心理構造になってる。心理と社会が入れ子構造でガッチリできあがっているような中で、僕たちは生きてるっていうことですよね。だからこういう表現も、それをどうやって自覚するというか露出させて、実はみんなこうだよね、でもそれをおもしろがって見る奴もいれば、そんなの見たくないという人もいる。そんなの見たくないという人は相当重症なSMだよね、ということです。だって自覚してないんだから。そういう問題なんだよね、結局は。
黒ダ:すごい話だな。でも納得してしまいました。
細谷:ちょっと続けていきましょうか。このあと、「第1回フィルム・セレモニー」というのが〈8ジェネレーション〉と一緒に(新宿の)蠍座で。蠍座というのはアンダーグラウンドシアターの蠍座でいいですかね。
末永:はい。
細谷:これはたとえばさっきの撮られた映像を流したりとかですか。68年の2月かな? と思いますけども。
黒ダ:これは写真にありませんので何だか……。かわなかさんの本(『映画・日常の実験』1975年、フィルムアート社)に出てきたんじゃないかな。あとハガキ(末永所蔵)が残ってたかな。
細谷:主催は〈8ジェネレーション〉で、〈告陰〉のフィルムを上映した記憶はありますか、蠍座で。そうなると、68年の2月ですかね。
黒ダ:2月は推定です(註:ハガキによれば1月28日、ただし台紙に2月24日と書き込みあり)。
末永:これはね、僕は本当覚えてない。「告陰、8ジェネレーション」って書いてあるけども、何かの記録があったの?
黒ダ:ひとつはかわなかさんの本と、ハガキがあったようです。待てよ、1月28日っていうハガキだから、さっきのムチ打ち儀式の撮影と同じ日になっちゃうんだよね。おかしいかな。
細谷:蠍座ですからね。
黒ダ:そうだね。
細谷:新宿ですから。
黒ダ:場所がかなり違いますよね。1月28日に撮ったやつを上映とか……。(フィルムだから)それはないな。
末永:これがチラシだな。68年2月(24日と台紙に記載)にフィルム・セレモニーのハガキサイズ(のチラシ)なんだけど、『で・ふぉるめーず』で「告陰」って書いてあるから、やっぱり出してるんだ。
黒ダ:『で・ふぉるめーず』というのは儀式の記録(映像)なんだろうか。
末永:そうね、儀式の記録だった気がする。短い15分くらいのものですね。ああ、蠍座でやってるね。案内を出してるから。でも内容とかそのシチュエーションはよく覚えてない。
細谷:蠍座で何かやったという記憶はありますか。
末永:うん。このときだけでしょう、たぶん僕が関わったのは。
細谷:ちなみに末永さんは蠍座に映画を観に行ったりしてましたか。
末永:それはありました。いろいろおもしろい映画とか。
細谷:ATG?
末永:やってましたからね。
細谷:その流れで、たとえば足立正生の映画とかは?
末永:観ましたね。『鎖陰』(1963年)とか。
細谷:どういう印象というか?
末永:いわゆるアングラ映画的なものだと思うんだけどさ。彼(足立)はもう学生じゃなかったのかな。
細谷:若松プロにもう入ってたと思いますけれども。
末永:僕たちがおもしろいと思ってたのは、50年代から60年代にかけてのフランスのヌーヴェル・ヴァーグとかさ、ああいうのに刺激を受けてたわけじゃないですか。ゴダールとか。それが日本でこういう全然違う方向から、いわゆるシネマ文化ということじゃなくて、本当に地下から出てきたような、見ちゃいけないものを見ているのかな、くらいのインパクトが最初ありましたよね、『鎖陰』とか。
細谷:足立さんとの接触は?
末永:ありましたね。足立さんも、昨日僕がちょっと言ってた、池袋にアーティストが集まる飲み屋さんがあってさ、そこにときどき来てて、みんなで飲んだりしゃべったりしてて、それでたまたま隣に彼がいて「末永さん、グロッタってわかる?」みたいな。
細谷:しゃべり方そっくり(笑)。
末永:そんな感じですよ。グッと迫ってしゃべるんだよね。そういうところだけ印象にすごく残ってる。
黒川:ちなみに、そのお店の名前は覚えてますか。
末永:あさ。平仮名で「あさ」って書く。有名なお店だった、作家やアーティストたちが集まる。
黒ダ:足立さんはどこに住んでたんだろう、その頃。池袋に住んでたの? 行きつけなら。
細谷:でも酒場で会ってたんですよね。
末永:うん。
細谷:グロッタの話を。
末永:うん。
黒ダ:グロッタってもともと東野芳明の。『グロッタの画家』って本がある(美術出版社、1957年)。
細谷:ありますね。
黒ダ:洞窟か何かのことですよね。
末永:だから、どちらかというと、『鎖陰』とかにしても、非常にアナーキーな感じもしたし、それと、あの時代ということで言うと、澁澤龍彦だとか唐十郎とか、そっちにやや近い感覚で、映画という手法で出てきた人かなと思っていたのでね。まさか彼がのちに赤軍に関わるなんて想像つかなかったね。とても政治的に突出する形で何かをやっていく人だと思えなかったけどね。
細谷:足立さんの場合は、末永さんとは少し違うかもしれないけれども、でも政治と芸術というのを、あるいは政治と映画というのを同じラインで考えていますね。
末永:たぶん最初は記録として赤軍のことを撮ったりしていたと思うんだけどね。
細谷:だからやっぱり今でも自分のことをシュルレアリストと言います。
末永:ああそう?
細谷:ええ、言います。すいません、話がちょっとそれてしまいました。その後いよいよ「狂気見本市大会」が本牧亭(上野)ですね(1968年3月13日)。
末永:これは、この当時のチラシが。
細谷:おお、すごい。
黒ダ:これ見たかな。見てない気がするな。
細谷:これ、初めて見る。というか黒ダさん初めて見る?
黒ダ:「総出演、万国博覧会、展覧会出場決定戦」って書いてある。万博を意識してるわけ、これ? そうだったかな。そういうイベントだと思ってなかったんだけどな。でも68年頭だから、そういう態勢はもうできたという感じなのかな。
細谷:これは(松江)カクさんの文字ですよね。
末永:そう。
黒ダ:ビタミン(アート)、告陰、クロハタ、ゼロ次元。枠が2つ空いてますけど。飛び入りが入ったりして。
末永:だから、この頃からかなり、その後の〈万博破壊共闘派〉の主要メンバーみたいなものが、ここで集まり始めたというのはあった。
黒ダ:ですね。本牧亭はそれ以前かと思ってたんだけど、こうやってはっきり万博と書いてあるとは……
細谷:もう万国博というのが名前として出ていますね。
黒ダ:みんなそう思っていたかどうかはわからないけど、そう書いた〈クロハタ〉は万博を意識していたわけでしょう?
末永:そう。反万博的に思ってたかどうかはわからない。それこそアングラの万博くらいだったかもしれない。
黒ダ:かもしれませんね。
末永:だって、その後のイイノホールでやるときまで、まったく反万博的なものはなかった。
細谷:広義な万国博覧会というイメージだったかもしれない。
黒ダ:オルタナティブ万博というか。
細谷:これ本牧亭の写真なんですけれども。
黒ダ:本牧亭は(写真が)けっこう残っていて、実は映像もある。これは一番よく出るシーンですけど、立ってるのが牟田(邦博)でよかったですかね。
末永:そうです。
黒ダ:この後ろにいるのが高森だっけ。
末永:そう、高森マキちゃんとか。
黒ダ:尼さんが上島(千寿子)でよかったですか。
末永:そうです。
細谷:これはどういった儀式だったんでしょうか。
末永:このときは『芸術生活』(「『狂気見本市大会』と銘うった儀式集団のハプニング」、1968年6月)か何かにもカラーで出た。
黒ダ:これですね。
末永:そうそう。上は〈ビタミンアート〉。僕がこの頃ちょっとそういう軍服を着て。
細谷:敬礼してるやつ、ありますね。
末永:これも僕がアイデアというかイメージを作って、みんなで相談しながらやっていたんだけれども、どこかその後の68年(10月)の「ブラック・フェスティバル」のイメージにもつながっていくような気が僕はしてるんです。結局、そういう非常にエロティックな表現と、それを逆に抑え込んでいくような、禁止していくような軍国主義的なイメージ、その両極をどうやって舞台の上にのせるかというのがあって、これなんかも結局……
細谷:ヒトラーを使ったイメージですね(「狂気見本市大会」ポスター)。
末永:うん、そう。さっきのカラーのとこ(『芸術生活』)を見せてもらっていい? これなんか、軍服を着てる。本来ならば性的なもの、エロティックなものを全部封じ込めているはずの存在が、同時にこういうものを背負っているんだということね。そういう自己を自ら禁圧していくような、ある意味グロテスクなんだけれども、さっき話したように、究極、社会って心理的にはそういう仕組みで作られてしまっているという感覚は、僕の中にこの頃からすごくあったの。
黒ダ:軍服を着ながら下半身は露出しているわけですよね。
末永:そうそう。
黒ダ:フンドシですかね。
末永:フンドシ。
黒ダ:この白いのって海軍の制服ですよね?
末永:そうそう。
黒ダ:もちろん貸衣装か何かで借りたやつですよね?
末永:そうそう。
黒ダ:やっぱりこの白いほうが儀式的だったという?
末永:それはありますよね。
黒ダ:全体的に白のイメージがいっぱいありますからね。このマネキンは自分で作ったんでしたっけ。
末永:マネキンはどこかから買ってきたのか、もらってきたのかね。
黒ダ:上からペイントしたのは?
末永:(自分たちが)ペイントした。
黒川:そうか、このマネキンは〈ビタミンアート〉のマネキンじゃなくて。
末永:違う、違う。
黒ダ:こっちが〈ビタミンアート〉。
細谷:いつも思うんですけど、我々はモノクロ写真で見ていて、急にカラーが出てくるとびっくりする。こんなに色があったんだっていう。
黒ダ:これなんか真っ赤だもんね。すごい強烈。
細谷:けっこう強烈ですよね。女性の身体にサンバネティックスと書いてる。
黒ダ:サイバネセックス。
末永:サイバネティックスがもともとのね。今でいうITとか。
黒ダ:AI。
末永:AIとか、もっと初期のそういうものじゃないですか。人間の脳の神経回路じゃないけど、そういうものがだんだん機械に使われていくという時代に入って、高度成長に入って、それこそ万博に向かうような科学技術みたいなものに対する幻想がどんどん掻き立てられて、という時代があって。でもサイバネティックスだけじゃ全然ひねりがなくておもしろくないので、そこでサイバネセックスにして。でもそれは今考えると、やっぱり人間は性的な衝動とかそういうものを、結局今はAIで満たそうとするような時代に来てしまっているので、あんまり外れていなかったかなと思う(笑)。
細谷:そうかもしれないですね(笑)。
黒川:(舞台の小道具で使っている)テレビは実際に放送していた番組を映しているんですか。
末永:そうなの。
黒ダ:ニュースで何か……
末永:羽田闘争か何かのね。学生運動の。たまたまなのよ、これ。
細谷:すごいですね。
末永:うん、たまたま。別にVTRとか使ってないから、まったく偶然だけど、うまくいったんだよな。こういう人間の意識下の世界と外側の社会現象、政治現象みたいなものを同時に観客は見てたという。
黒ダ:ちなみにテレビから音は出ていたんですかね。
末永:音は出てたと思います。
黒ダ:このテレビのニュースの音以外で、何か音は?
末永:音はなかった。
黒ダ:台詞とかもない?
末永:うん。
黒ダ:ちなみにこの上島さん、どんな役割だったんでしょう。これも何か食べる?
末永:けっこう生々しいあれでね。(牟田が)ソーセージを股間から下げてるのを彼女が食べる。ここでも食べるわけです。
黒ダ:高森さんは、最初はこうやって身体を隠してましたね。
末永:そうですね。これは衣装というよりも、布をずっと巻きつけてるだけの、わりと自由に動けるようなものだった。
黒ダ:これが終わりのほうなんですかね? あるいはこの先はもっとあったんですかね? 『アサヒグラフ』(1968年3月29日)だっけ。わりとデカデカ載ってる。
末永:こっちが前半だった気がするね。それでわりと後半に、さっき僕がカラーで出てた、マネキンを背負って這いずり回るというような流れだった気がします。
細谷:これはグループによって持ち時間何分というのは、ある程度決まっていたんですか。
黒ダ:ここに書いてある。ここに時間表が。
黒川:これ(時間表)は「展覧会出場決定戦」って書いてありますが、〈告陰〉の小道具じゃなくて、全体の進行なんですか。
末永:そう。
細谷:ちなみにこのとき、〈ビタミンアート〉の小山(哲男)さんとご一緒されますけど、小山さんは何か印象というか?
末永:小山さんが出たときって、たまたま会場に永六輔が見に来てたのよ。それで小山さんがリンゴに自分のうんちをつけて会場に投げたのね。それですっごく永さんがおもしろがって、「ああ、おもしろい!」みたいな感じでゲラゲラ笑って盛り上がってましたけど。
黒川:末永さんはどうでした、その小山さんのパフォーマンスは。
細谷:小山さんのパフォーマンスや彼の行為はどういうふうに見ましたか。
末永:うーん、このいくつかのグループの中でかなり小山さんは異質な存在だったし、異質な表現をもっていた人だと思うんですね。だから僕にはよくわからないんだけれども、彼はマネキン会社で仕事してたからさ、いつもマネキンを小道具に使ってたんだけれども、何だろうな。あの時代としては早かったのかもしれないけど、何だろう。オタクとも違うんだけど、何と言ったらいいのかな、独自の非常に奇妙なおもしろい世界をもっている人で、それで、ああいうマネキンみたいなものを、たぶん自分の家にもいろいろ作って置いてたと思うんですよ、小道具として。もしそれがね、マネキンじゃなくて生身の人間だったらさ、すごいよね。
細谷:すごいことですね。
末永:そういう雰囲気をもってる人だったの。彼自身がそうだというのではなくて、そういうイメージ世界をもっている人だった。
黒ダ:なんとなくわかる気がしますね。実際にあとで、舞台で牛を殺したりなんかしてますからね。あとニワトリを殺そうとしたりとか。
末永:生(なま)のそういう感覚をすごく持ってる人だったんですよね。
細谷:小山さんと一緒にデーティングとかやるちだ・ういさんの印象は?
末永:だからね、なんでちだ・ういと小山さんが一時期とはいえ組んだのかが本当にわからないくらい。でもたぶんそれは、〈ジャックの会〉だっけ、そこで彼らは一緒にやってたわけ。そのなかで、もっと自分たちのことをやりたいというのがたぶんあって、二人で「デーティング・ショー」みたいなことを始めたんだと思うんだよ。だから、そこから出て自分たちの表現を出していきたいときに、たまたまタッグを組んだのが二人だったと思うわけ。その後のちだ・ういは、もっともっとその後だけど、全然違う世界に行ってるじゃない? 作家になって(「有為エンジェル」名)、けっこう角川(書店)から小説を出したりなんかしてた頃(註:『神の子の接吻』なら1994年)も僕は付き合いがあったんですよ。それで彼女は外国に行っちゃった。そこからはもうやり取りがなくなったけど、それまではわりと家に遊びに来たり、泊まりに来たりもあったし。だから彼女が描いている小説の世界と、あまりにもかけ離れてるので。
黒ダ:小山とちだの組み合わせは完全に佐々木耕成のプロデュースらしいです。
末永:なるほど。だからやっぱりどう考えてもわからなかった。
黒ダ:でもその佐々木プロデュースはけっこう成功してしまったわけですね、結局ね。
黒川:あれは佐々木さんにとって、あの二人が自分とはちょっと違うというか、佐々木さんはパフォーマンスをやりたくても頭で考えることが先になってしまって、身体が先に動くというのが自分にはできなかったという言い方をしてましたけどね。
末永:まあ、美術の人だもんね。
黒川:やっぱり佐々木さんの印象は美術の人という感じですか。
末永:うん。僕から見るとね。ほら、何年か前にアーツ千代田でも彼の展覧会をやってたじゃないですか(2010年4月23日~5月23日、アーツ千代田3331)。ああいう作品をずっと作ってたわけだし、美術的表現に彼は戻っていったのかなって。別に悪い意味じゃなくてね。
黒ダ:あと年齢、世代が(末永よりずっと上の)、1928年生まれじゃなかったっけ。
末永:そうなんだ。ちなみにだけどね、僕はちだ・ういに最初に会ったのも実は豊島芸術研究所だった。そこで僕が絵を描いてたら、高校生の女の子がひょっこり入ってきた。「ちだ・ういです」とか言って。きっと彼女は探していたんでしょうね、自分の場所を。それでときに会ったりしたけど、そのうち気づいたら〈ジャックの会〉に関わっていたんだなと。
黒川:当時の豊島芸術研究所というのは、アートに関心がある人が、あそこだったら何かあるかもしれないという場所だったんですね。
末永:そう。これまでのアートではないものに関心をもって、新しい表現とか生き方を模索してる人が行く場所だった。通過する場所というのかな。
黒ダ:おもしろいですね。当時、(情報・)通信手段も限られていて、SNSも携帯もない頃に、ちゃんと行くわけだからすごいなと思うけどね。
末永:うん。
細谷:次がですね、新宿インですね(1968年3月20日)。これはガリバーさん? ちだ・ういも出てるみたいですけれども、ディスコテックL.S.D.です。
末永:本当だ。青目海。
黒ダ:(写真を見せながら)末永さん、どこに写ってましたっけ。
細谷:ちょっとご覧になっていただいて。
黒ダ:ガリバーがいたりするかもわからない。
末永:どこにいる?
黒ダ:これですね。
末永:そうだ。その横が宮井陸郎じゃないの?
黒ダ:宮井、いたような気がする。
末永:このサングラスの人。
細谷:これ、宮井さんですね。
黒ダ:それわかる?
細谷:背も低めで、シュッとした(笑)。ちょっとかわいらしいというか。
黒ダ:顔の形に特徴があるんです。
細谷:今もそんなに特徴が変わってなくて。
末永:そうそう。
黒ダ:このときって何を? これも何かマネキンを使ったやつ?
末永:ですね。そうだと思います。よくわからないね、この写真だと。
黒ダ:よく見たらですね、たぶんここで何かしていて、このへんが末永さんじゃないでしょうか。
末永:このヘルメットかぶってるやつね。
黒ダ:たぶん下に何か置いてやってるんだと思います。
末永:だと思う。
黒ダ:あまり記憶がない?
細谷:末永さん、どれですか。
末永:たぶんヘルメットかぶってるやつ。でもこの頃って本当にもう毎週何かやってた。
細谷:68年がとにかくすごいんですよ。
黒ダ:怒涛のように。これ確か、テーブルの上に薬瓶みたいなのを置いて……。
末永:何かやってるね、これ。何やってるんだろう。薬を混ぜたりなんかして、儀式をやってるのかな。
黒ダ:食べる?
末永:ここに何か箱があって。
黒川:(写真に)ハイライトと書いてあるのはガリバーの作品ですよね。
末永:どれどれ?
黒川:左下にあるハイライト。看板みたいなものが。
黒ダ:ちだ・ういがこれ着て写真撮ってた。
末永:ああ、そう。ふーん。
細谷:『黒の手帖』か何かでした(註:正しくは「街を占領したアングラ文化」、『毎日グラフ』1968年5月26日)。ちなみに宮井さんはこれ?
末永:そうそう、それそれ。
細谷:わかりやすい。
黒ダ:でも何か顎のこういう形が。それだけで断定はできませんが。
細谷:今せっかく名前が出たので、ガリバーさんとの付き合いは?
末永:たぶんもっと早い時期で、夢土画廊で……
黒ダ:昨日名前が出てましたね。
末永:「視覚展」をやってるときに、ヨシダ・ヨシエと一緒に来た気がする。それで、彼がメジャーを持って歩いててさ、あの頃。どこに行っても測定してるっていう。ギャラリーに来て測定して、しばらく話して帰った。
細谷:その後、お付き合いは?
末永:しょっちゅうじゃなくて、何かのときにありましたよ。彼のだいぶ前の作品集みたいなのをもらったか何かのときに、ひょっこり連絡があったりしたことがあって、でもあまりそれ以上の接点は彼とはなかったね。
細谷:そうですか。いわゆるフーテンとしてもそんなに?
末永:有名人だったからね、彼ね、新宿では。
黒ダ:日本三大ヒッピー。
末永:風月堂にガリバーがいるみたいな感じだったから。
黒ダ:やっぱり写真を見るとかっこいいですよね、彼も。
末永:あと、ちょっとあとだけど、僕たちがストリート・ファイティング・ロックをやって、いろんなところでロック・イベントみたいなことをやってる時期に、木村英輝というのがいたんだけどさ、彼が京大の西部講堂か何かでコンサートみたいなのをやって(1971年3月の「ロック・フェスティバルMojo West」など)、そこでロック的なミュージック的な感覚で木村英輝とも会ったり僕もしてたので、そのとき、ガリバーが何か組んでやってる感じがあったし(ガリバーと木村は共著で『Too Much No. 1』を1970年にスペースマラソンから発行)、そのくらいのつながりで、それ以上、彼がもっとその後、個人としてのアートをいろいろやっていくけど、そこはあんまりね、「こういうのやってるから見に来て」って言われて1回行ったことがあったけど、あんまり僕の中では入ってこなかった。
黒ダ:わかる気がする。
細谷:なるほど。じゃあちょっと続けていきますが、この次のは末永さん参加してないみたいなんですが、マキ(「魔鬼」とも表記)とクルマのハプニング(1968年3月25日)。
末永:これ、何かに写真が出てます?
黒ダ:これはないです。
末永:じゃあちょっとわからないです、僕も。
黒ダ:クルマも自動車を使ってやったんですかね? 「魔鬼」ってありますけど、高森マキのことですよね?
末永:うん、高森マキですよ。
黒ダ:それから、これですね(マキとマカオの街頭散髪および「キスキスキス」、1968年5月14日、数寄屋橋公園・日劇前、「ハプニングってなあに?」、『女性自身』、1968年5月27日)。
末永:これはね、数寄屋橋で彼らがやって。このとき僕は参加してないの。それで、わりと牟田君とマキと何人か、あるいは青目なんかも関わったことがあったと思うんだけど、ときどき勝手にいろんなところで、こういう街頭ハプニングみたいなことをやってた。その一連のひとつですね。
黒川:じゃあ、末永さんも(ほかのメンバーが)やっていること自体、よくわからないものもあったんですか。
細谷:(末永も)知らないで〈告陰〉の誰かがやってるとか。
末永:もちろん「今度、数寄屋橋でやる」とか、お互いあるんだけど、全部が全部付き合ってるわけじゃないし、見てるわけじゃないし、どんどん好きにやれば、みたいな感じだったかな。
黒ダ:これなんか日常的な都市空間の中に見慣れないもの、異物を見せるという、〈告陰〉の基本的なコンセプトはあまり関係ないですよね。
末永:そうそうそう。
黒ダ:だからいわゆるこれが「ハプニング」か。
細谷:〈告陰〉としてというよりは、個人の活動というか。
末永:そうそうそう。それに近い。
黒ダ:ただ一応ニュースレター(『告陰通信』)に載っているので。
末永:そうそう。だからわりと、そういうゆるい関係だったから。
細谷:ちょっと戻りますか。池袋駅前および地下(1968年4月4日)。
黒ダ:池袋がいくつもあるんだけど。
末永:これ(目隠しして傘をさす末永と高森の写真、3月か6月のベトコン儀式と思われる、池袋西武百貨店前)は西武デパートの前でやったやつでしょう。 黒ダ:これ(白衣に仮面のメンバーらを末永がロープで縛る写真、1968年6月、池袋西武百貨店前)は別のときですよね。
末永:別のとき、全然。
黒ダ:これ(ロープで縛る写真)もベトコンなんですかね。
末永:いや、これは違う。だからこれ(目隠しして傘をさす末永と高森の写真)がベトコン儀式で、これは要するに、当時さ、ニュースでよく出たんだけど、ベトコンの戦士というか解放戦線(南ベトナム解放民族戦線)の人が捕まって、その場ですぐ黒い目隠しをしたまま射殺されたんだよ。処刑なんだけど。それがすごくセンセーショナルに世界中に配信されてインパクトが強かったので、目隠しをして街の中を歩くというのを彼女と2人で組んでやったという。
細谷:これは2人でやったんですか。
末永:そうです。
黒川:さっきの本牧亭の舞台でも、白装束に黒い目隠しをした場面がありましたよね。それもベトコン?
末永:それはあまり意識してなかったと思うよ、ベトコンのことは。このときはそのためにやったという感じ。
黒ダ:これ、高森さんは何をやってたんですかね。
末永:傘をさして、二人で腕を組んで、カップルが街の中を、僕は上半身裸でデパートの前を歩いてるっていう。そういうやつですね。
黒ダ:ちなみに、こんなのは告知しない? いきなり?
末永:いきなりハプニングでした。
黒ダ:写真を撮るとしたらメンバーの誰かが撮るのですか。
末永:そうですね。誰か一緒についてきていたんだと思う。だから、わりとそれぞれやっていたんだよね。思ったらその場でやるみたいな。
黒ダ:そういうやつもあるし、これとかけっこう本格的な(白衣に仮面のメンバーらを末永がロープで縛る写真)。
末永:そうですね、仕込みをしてやってたかなという感じ。
黒ダ:どの写真がどれかというのが正確かどうかわからないので。ただこれはちょっと本格的で、いい写真なので。ただHさんの顔がモロ見えなので(『肉体のアナーキズム』に)使わなかった。使いたかったんだけど。
細谷:これすごくいい写真。『Bien 美庵』に載りましたよね。
黒ダ:そうですね。
末永:そうそう、『Bien美庵』(2002年11月、末永蒼生「告陰とあの時代がめざしたもの」掲載)にね。
黒ダ:これだけ本格的な儀式だから、(年表に)載ってるはずなんだけど、68年4月、これではないんでしょうね、たぶんね。
末永:そうだね。ちょっとわからないね、日付が。
黒ダ:これは別にベトナム戦争とかそういったテーマじゃない?
末永:そうじゃないですね。
細谷:ベトコン儀式の後か前か、同じくらいという感じ?
末永:同じくらいでしょうね、1ヶ月のうちの。
細谷:すごい。
黒ダ:これは仮面白装束の人もいるけど、末永さんが、これは紅白の紐ですかね。
末永:そうですね。
黒ダ:紅白の紐で縛る?
末永:うん。
黒ダ:どんなテーマだったんでしょうね。
末永:たぶんあんまりね、ベトコンの問題とか他のものみたいにテーマ性を掲げて、意味をもたせてやるってことをしてないと思うんですよ。
黒ダ:そうなんですね。
末永:だから、そこであんまり意味づけをしても……。
黒ダ:これ、西武百貨店前でいいのかな。
末永:そうですね。西武百貨店のところで。
黒川:さっきのベトコン儀式のほうは周りの人も半袖とかなんですけど、こっちはもうちょっと冬っぽいんですよね、服装が。
末永:もしかしたらベトコン儀式より前かもしれない。春先とか。
黒ダ:69年8月(6日)の『週刊言論』(「ハプニング集団万博破壊共闘派の生態」)に出てるんですけど。
末永:ああ、そうなの?
黒ダ:こっち(鉢巻男二人がそれぞれ白衣人物を背負う写真)はそうなんですよね。ただ、やった日と記事の発行日が近かったかはわからない。
細谷:これはロープですかね。
末永:そうそう。紅白の、お祭りに使うような。
細谷:トコトコ行きましょう。桂小金治アフターヌーンショー(1968年4月23日)。
末永:これはね、週刊誌(前出『週刊言論』)とかに出て。
細谷:写真がありますね。
黒ダ:これ(写真見せる)、名前がこれでいいか、わかる人とわからない人がいて。
末永:これが水町(幸男)でしょう。それでマキと石橋と、たぶんこれがね、青目だと思う。ちょっと待って。ちょっとわかりにくいね。こっちが青目だよね。
黒ダ:じゃあ、これが青目。このサスペンダーの人が。
末永:そうだね。わかった、わかった。そういうこと。これがけっこうテレビで出ちゃったからスキャンダルになって。
黒ダ:これって生(なま)か。
細谷:生放送。
末永:生です。
黒ダ:これも股間のソーセージを食べる?
末永:これはそんなところまでやってないですよ。
黒ダ:どの部分が猥褻なんだろう。
細谷:服を脱いでるってことなんですかね。
末永:ただそれだけでしょう。それで、スタジオの中で音に合わせて、どんどん行進することをやっただけなんだけど。
細谷:それがあまりにも異様だったんですよね、きっと。
末永:お茶の間としては。だから生じゃなかったらできなかったですよね。本当に即興的にその場でやっちゃったから。これがVTRだったらカットされてたでしょうね。
黒ダ:これって高森、石橋は上が裸ですかね。
末永:いや、裸にはなってない。
黒ダ:それで猥褻と言われるかな。
末永:この時代の感覚だとやっぱり。
細谷:脱いでないですね。
末永:脱いでない、脱いでない。だからありえなかったんじゃないの、当時としては。しかも本当に昼の時間のアフターヌーンショーだったから、なんで突然こんなのが出てきちゃったのっていう。
黒ダ:テレビでしかも生放送だから、ちょっと思い切ったことをやっちゃえという感じもあったわけですか。
末永:そうそう、ありましたね。
細谷:ちなみにテレビのオファーはどうやって? テレビ局からくるんですか。
末永:そう。たぶんね、週刊誌とかにチョコチョコっと出てるじゃないですか。そういうのできっと話題性として、ということだったと思う。
細谷:じゃあどんどんいきますね。68年5月のようですが、アンダーグラウンドシネマ・イン・長崎。映画とティーチイン。これは上映をしたということですかね?
末永:(当時のチラシを見ながら)羽田闘争とかのフィルムをちょっとやって、儀式みたいなことをやって、っていうやつだったんだね。
黒ダ:それ、場所はどこでしたっけ。会場?
末永:会場、書いてない。
黒ダ:長崎は長崎ですよね。
末永:長崎ですね。
黒ダ:市民会館? わからないな。
細谷:これはなんで急に長崎に?
末永:僕が長崎出身ということがあって、牟田君も長崎だったからさ。じゃあ長崎で、という話がもち上がって。長崎でやる大きな意味はあんまりなかった。
黒川:近い時期のエンタープライズ(1968年1月に佐世保港に入港した米原子力空母への反対運動)は特に関係なく?
末永:なく。
黒ダ:「(公開実験)シチュエイション」(1968年5月18・19日、C.C.C.)がきて。
細谷:「シチュエイション」がきますね。ヨシハラNORIO。公開実験というやつですね。これは記憶にありますか。シチュエイション。
末永:もうひとつチラシが、そのときのじゃないかなというのがあるんだけどさ。黒ダさん、覚えてない?
黒ダ:覚えてないですよ。でもこのデータは他からも何かあったな。今このチラシだけで何か覚えてることは?
末永:ヨシハラさんと一緒に池袋の会場を借りて、ちょっと映像を使ってハプニングをしたのを覚えてるのよ。そのときのチラシがあったんだけどね。美術館(練馬区立美術館「あしたのジョー、の時代展」、2014年7月20日~9月21日)のときには出したんだけど。
細谷:その映像というのはハプニングの、儀式のときの映像?
末永:じゃなくて、ちょっとね、環境アートみたいなことを当時僕考えてて、やってたんですよ。どこかにチラシがあったんだけど……。今僕が言おうとしたのは、電車の中から、普通の西武線とかそういう電車なんだけどさ、進行方向に映像を……。それそれそれ(チラシ)。出てきたじゃん。これをやったときだと思うのよ。
細谷:「シチュエイション」って書いてありますね。
末永:でね、どういうことかっていうと、空間が、ギャラリーならギャラリーがあるじゃないですか。一方の壁には電車が前に進んでるところ、先頭(の車両)から撮った線路の上をずっと走ってる映像が映るわけ。反対側の壁には後ろ側の、線路がどんどん遠のいていく映像が映るわけ。するとこれ(空間)が電車になるわけ。
細谷:装置というか空間として。
末永:そう。環境を映像でそうやって作って、その場所にしちゃうというね。
細谷:状況、シチュエーションですね。
末永:だから「ブラック・フェスティバル」のときもそれに近いことをやったんだけど、ビルに映像をずっと映していくということをやって。今で言うマッピング。
黒ダ:プロジェクション・マッピング。
末永:プロジェクション・マッピングをやってたわけ。そういうのをやる実験の始まりだった。そこに参加者が入ってきて、(空間)全体が動いてるな、電車が動いてるなという感覚をつかんでもらって、その中でまた少しパフォーマンス的なことを身体を使ってやったり、ちょっと総合的にやったのが今のチラシの。
細谷:ちなみに、その中ではどういうパフォーマンスをされる? 行為というか。
末永:そのときはライトとか、映像も使ってやったけど、半透明のビニールみたいなものがあって、それを外側から参加者が見てるわけ。奥のほうからライティングされて、するとそのライトの前で女性がパフォーマンスする。シルエットだけがずっと動いてるというようなことをやった。
黒ダ:それ、他の儀式とすごい異質ですよね。
末永:異質でしょう。
細谷:空間を使ってということですもんね。
黒ダ:当時の環境芸術にたしかに近い感じ。
細谷:それも8ミリですか。
末永:そう、8ミリ。
細谷:それがあったら再現できそうですよね。新しく電車で撮ればできるんじゃないですか。
末永:できる、できる。
黒ダ:今やってもけっこうウケる。
細谷:末永さんのディレクションでね。
末永:そうそう。だからこういう「あなたの未知の感覚を引き出すシチュエイション」っていうことを使ってやってるわけ。ヨシハラNORIOという人が写真とか映像を使うのが好きだったと思うんだよね。それで組んで2、3回そういうことを彼と一緒にやった。
細谷:撮影されたのもヨシハラさん?
末永:いや、撮影は僕。だから何て言ったらいいんだろうね、〈告陰〉というのは、そういういろんなことをやってたからさ。表に出たときはああいう〈万博破壊共闘派〉とか突出してたからね。だけど、普段はわりとそういういろんな実験的なことをやってたという感じですね。
黒ダ:ボーダーレスですからね。
黒川:これだけいろいろやっている68年も、その間、子供の絵の教室をやっているんですよね?
末永:アトリエやったりとかね、教室やったりとかやってたわけ。
細谷:豊島芸術研究所、「6・15池袋ティーチイン あなたにとって’70年とは何か」(1968年)。
末永:たぶんこれは70年安保に向けて、いろんな……
細谷:6・15ですからね。
末永:6・15でしょう。ちょうど60年安保のときの事件(樺美智子死亡)があったときなので、それに合わせて、研究所に来てたメンバーはもちろんだけど、周りの人たちにも声をかけて、これはもう明らかに政治的な現象をアーティストなりアートの場でどう考えるかということをやったわけですね。
細谷:次がですね、青目海とハプニング・オブ・ビートロジー。
黒ダ:これ、会場もわからない。
細谷:68年6月20日。これは何かチラシとかあったんですか。
末永:これはわからない。まったくわかりません。次がさっきのやつ。
細谷:ベトコンですね。その間、米タン闘争(1968年6月26日)なんかもありまして。
末永:「告陰の食儀再演」(1968年6月28日)。これたぶん、前にギャラリーとかでやったやつをもう1回、〈告陰〉の事務所かどこかでやったということじゃなかったかな。だから大したものではないです、これは。
黒ダ:あといろいろトークっぽいもの、講演会とかそういうものがいっぱい。
細谷:講演がたくさんになってくるんですよね。思想の科学社でこのとき「ユートピアの会」がありましたね(1968年7月3日)。末永さんの講演(“ハプニング”芸術=非芸術の理念)ですかね。
末永:そうですね。思想の科学研究会はいろんな研究会があったじゃないですか。その中に「ユートピアの会」というのがあって、ときどき呼ばれて行って、それで僕たちのやってることはどういうことなのかみんなに話を聞いてもらって、ディスカッションするみたいな、そういう感じですね。
黒川:このときの「非芸術」というのは「反芸術」とはまた違う?
細谷:「芸術=非芸術の理念」という演題。
末永:うん、これはたぶんね、「反芸術」というのは反の意味があると思うけど、「反哲学」と同じで。だけど、結局それって「反芸術」という名の芸術だよね、っていうことになっちゃうので、もうちょっとそのへんを深く考えてみたいというのもあって、あえて「非芸術」にしたんだと思う。
黒ダ:じゃあこれは何かの文献にあったんじゃなくて、末永さんがご自分で考えた?
末永:そうですね。
細谷:またテレビ出演で「3時のあなた」(フジテレビ、1968年8月3日)ですね。
末永:このへんも全然記憶にない。
細谷:立て続けですからね。1ヶ月後ですから。
黒川:あまりご記憶にないというのは、実際にハプニング的なことをやったというよりは、何か話したくらいの感じのものなんでしょうかね。
末永:そうですね。そんな特にそれ自体がメインテーマで大きく出たとかいうことではないと思いますよ。
細谷:それでまた次に長崎に行かれて。1週間後に長崎でコクラヤギャラリー上映会。
末永:長崎のコクラヤギャラリーというのがあったんだけれども。
細谷:これも映画上映ですね。
末永:そうですね。あの当時は8ミリも含めて持ってたので、そういうのを持って。一番わかりやすいじゃないですか。そこで見せて、ティーチイン的なものをやったりとか。だから何かこう、今こういうことが起きてるっていうことをやっぱり伝えていく。それこそネットも何も当時ないわけだから、実際行って、生で場を作るということを、ちょっと巡業してたのかな。
細谷:それは昨日話していた羽田闘争とかの?
末永:そうですね。
細谷:ちなみに、さっきの「サイバネセックスの歌」は作品として完成したんですかね。
末永:してなかったと思う。
細谷:ただ(未完成のままイベントで)上映して?
末永:作品としてというほどね、だいたい撮ったものを細かく編集して音を入れたりとかしてないから。あくまでパフォーマンスをやったり、何かイベントをやるときの一要素として映像を流しながら、っていうことですよね。だから独立した映像作品として完成させるというのはあまりなくて。
細谷:「サイバネセックスの歌」というのを、映像を流しながらパフォーマンスをした記憶はありますか。
末永:地方で、たとえば長崎でパフォーマンスはしてないと思う。たぶん上映会中心だと思う。
細谷:なるほど。その後、東京で画廊喫茶シャボンというところで「告陰大博覧会」という。
末永:池袋にあったんですよね。わりと大きな、壁面全部使えるようなところがあって。僕の当時の事務所がそばにあって、使い勝手もいいし、駅からもわかりやすいというので、ときどきそういうのをやってましたね。
黒ダ:ただこれ、(「告陰大博覧会」会期中に同じ会場で)水町さんとかHさんとか個人の作品展なんだけど、「告陰大博覧会」という形は?
末永:たぶんそれぞれでいろいろやってたんだけど、「告陰大博覧会」のときには個人じゃなくて、メンバーがいろんな表現をしたり、壁に絵をダーと貼るとかね、そういうのをやってたんですよね。
細谷:パフォーマンスもされた?
末永:ちょっとやってた気がする。さっき写真があったんだけどね。あとで出てきたら。
黒ダ:この画廊の写真はないですか。
末永:あとでちょっと見ておく。
黒川:末永さんの印象では、使える壁面は風月堂よりも広かった感じですか。
末永:風月堂くらいだったかな、うん。
黒ダ:それはかなり大きいですね。
細谷:岡部(道男)さんの映画(『クレージー・ラブ』、1968年)とかもあったりするんですけれども、最初のブラック・フェスティバルがありますね(1968年10月13~19日、アングラポップ)。
末永:そうですね。そうそう。渡辺千尋のポスター・デモ開始というのがあって(同年10月)、このへんからブラック・フェスティバルが実は始まってて、それで渡辺千尋ってデザイナーで、僕の高校時代の美術部のもともと仲間だったんだけど、桑沢デザイン(研究所)を出てやってました。それでこれ、どういうポスター・デモかっていうと、女性が立っててそれを下からスカートを覗くように。
黒ダ:これ(映画『ブラック・フェスティバル』冒頭のスティール)ですね。
末永:これ。映像にも出てきますよね。これを(新宿駅)西口の地下道の、西口の一番東寄りって言ったらいいかな、駅のほうじゃない、外側に地下道があるじゃない? ずっと。なんとなくわかります?
細谷:ええ。
末永:あそこの、今ちょっときれいになってるけどね、地下道にあれをずっと貼っちゃったのね。ポスターを。
黒ダ:勝手に?
末永:勝手に。だから歩いてる人は、絵なんだけど、女性のスカートの中を覗きながら歩いてるような雰囲気になっちゃうわけ。要するに女性がスカートを履いてると、下からそれを写真で撮るような絵なの、イラストなの。盗撮。
細谷:それが下にバーンと貼ってある?
末永:そうそう。
黒ダ:映像を見ると、床にバーンと貼ってある?
末永:そうそう。それを彼(渡辺千尋)が自分で持ちながら走ってくるところから、あの映像は始まってるわけ。
細谷:普通の人が歩いてくると、下から盗撮のポスターが貼ってあるということですね?
末永:そうそう。
黒ダ:壁じゃなくて地面に貼ったのか。
末永:そうそう。それが「ブラック・フェスティバル」の始まりのひとつのパフォーマンスというわけで。
細谷:じゃあこれ(渡辺のポスター・デモ)は(ブラック・フェスティバルの演目に)つながってるわけですね。
末永:つながってます、ここから。さっき言った、ヨシハラさんたちとプロジェクション・マッピングみたいなことをやりながら新宿をずっと練り歩くという。ビルにずっと映像を映しながら、16ミリで撮ったやつをね。こんな大きな映写機をこうグッと車で押しながら。
細谷:押しながら?
末永:うん。なんとなく映るんだよ、ビルに。
黒ダ:映るかな。それって。
細谷:新宿のどのあたりですか。
末永:東口。昔の二幸ビルとかあったあたりの、スタジオアルタがあったあたりの、あのへんの通りをずっと映しながら歩いた。
黒川:時間帯はどれくらいですか。あまり明るいとダメですよね。
末永:夕方以降で。昼間は僕と秋山(祐徳太子)さんがやってたでしょう。
黒ダ:これ(檻に入って移動する写真)ですね。
細谷:昼間はこれをやって、夜は映写機を?
末永:そう、そういう感じ。
細谷:夜、映写機を押してたら、警察は来ないんですか。
末永:そのときは引っかからなかったね。
黒ダ:私もプロジェクターを仕事柄よく使ってるわけなんだけど、夜でビルの壁面に大きく映すとしたら、相当な光量と相当な画質がないと見えないと思うんだけど。
末永:けっこう強かったみたい。どっかでヨシハラさんが(映写機を)借りてきたか手に入れて、強い……。
細谷:あとは今よりももう少し街が暗かったかもしれない。
黒ダ:それはありうる。
末永:薄暗くなるし、新宿とはいえ。
細谷:僕も仲間とデモ隊列から(周りの建物に)映写したことあるんですけど、街が明るすぎちゃって映らないんですね。
末永:そうそう。だからあのときの、10・21のフィルム(『10月21日・夜・新宿(騒乱)』)や『幻のブラックフェスティバル』(ともに1968年)もさ、街頭は暗いもん。
黒川:ちなみに、さっきの「車と仮面による儀式」の車って、そういうこと(映写機を運んだ手押し車)を言っているんじゃないですよね。
末永:違う、違う。それとは別です。
細谷:「ブラック・フェスティバル」という名称はどこから来たんですかね。
末永:たぶん、特にどこかからもってきたというのはなかったので、やっぱり、〈告陰〉として当時これを企画したので、やっぱり僕の中の〈告陰〉の陰の部分。陰陽でいうと陰の部分からのメッセージみたいなことも含めて、たぶん「ブラック・フェスティバル」ということでやったような気がします。
細谷:じゃあ、どなたがつけたかということでもなく?
末永:たぶん僕が決めたと思いますよ。あとは映像にも映ってるような感じで。
黒ダ:(映像からのスティールを見せて)この石橋さんの人力車があって。この次のやつで、何か紙を配ってるんですよね。これは何かメッセージがあるんじゃなくて、ただの紙なんですか。
末永:ただの紙。
黒ダ:真っ白な紙?
末永:あえて白い紙を配る。というのは、ああいう紙とかチラシとかを配ると、当然そこに何か書いてあると思って、説明を知りたいわけじゃん。人間って説明を知りたいから。それで何もないものをあえて配るということは、自分でイメージして考えたら? ということであって、こっちが説明することではないという。
黒ダ:映像の中に紙をもらって裏返す人が。いろいろバラバラにやって、最後はみんなで終わりみたいな感じでしたが。
末永:そうですね。あと東口の地下道でちょっといろいろやって。
黒ダ:これが続いて、秋山さんがいて、仮面の人と素顔の人がキスをしているという。
細谷:アングラポップの室内?
末永:いや、あれは東口の地下道。今でもある。これはアングラポップに入ってから。
黒ダ:顔を白塗りにして何か空手のような。
末永:これは〈クロハタ〉の人。
黒ダ:〈クロハタ〉の人ですか。
末永:最後のほうにわりと〈クロハタ〉でやってた人で、何て言ったかな。キノシタさんとかオオシタさんとか、何かそういった名前の人で。
黒ダ:マツナガ? マツシタ?
末永:マツシタだったかもしれない。
黒ダ:松下一平か。
末永:そうそう、そうでした。
黒ダ:それでこの中に高原らしき人がいて。
末永:そう、高原さん。
黒ダ:だから〈クロハタ〉だろうと思って。じゃあ〈クロハタ〉なんですね。
末永:そうです。
黒ダ:わかってよかった。
末永:これは最後の日。
細谷:最後の日は室内(アングラポップ)で。
末永:最後の大集合。だから〈クロハタ〉も来たし、〈ゼロ次元〉も来たし、というような感じでしたね。20日にそれをやって、終わって、このときこれを撮ってるじゃないですか、映像を。その16ミリカメラを持って、翌日(国際)反戦デーに行ったという、そういう流れでしたね。
細谷:10・21ですね。
黒ダ:アングラポップのフィルムの最後で何かお坊さんと尼さんが出てくるんだけど、この人たちは何だったんだろう。
末永:この頃いろんな人が飛び入りしててさ。少し前からもちろん知っていて、ポスターに書いてあるんだけど。
黒ダ:名前がすごいいっぱいあって。
末永:(チラシで)秋山さんの上に出てる〈エアリスト〉というグループだった。
黒ダ:エアリスト? 聞いたことないんですけど。
細谷:飛び入りの人が入ってくることもあるんですね。
末永:ありました。
細谷:「今回出る!」って出演して。
末永:そうそうそうそうそう。
黒ダ:私の知らない名前がいっぱいあって、きりがないのでやめますけど。でも今のは初めて聞きました。
細谷:10・21の撮影のときは、末永さんと何人かで行かれたんですか。
末永:カメラをやってた黒木直哉と僕がたぶん一緒に行動してました。もちろん石橋初子もあのときにいて、相当、西口行って東口行ってって、回って撮ってたのね。右翼系の人がいたりとかして、ちょっと危険な状況があって、乱闘みたいなのが起きたり、殴られたりする人もいたし、けっこう緊迫してましたよね。だから僕は石橋さんとそのときは普通の格好で一緒に行動してたんだけど、ヤバくなると2人で腕を組んで、すり抜けると。単なるカップルだなって思わせて、すり抜けたりしながら、また東口行くとか、そんな感じで撮影してた気がしますね。
黒ダ:そういう意味では女性が混ざってたほうがよかったわけだ。
細谷:そうかもしれないですね。
黒川:あの「ブラック・フェスティバル」のポスターの絵は誰の絵ですか。
末永:僕です。これは僕が最初に描いた原案というかチラシなんですね。それで、これを渡辺千尋がもう少しデザインアップして大きくしたのが、練馬区立美術館でやったときには掛かってたと思うんですよ。
細谷:「あしたのジョー」(「あしたのジョー、の時代」展、2014年)のときの?
末永:そう。
細谷:国際反戦デーがあって、それから「儀式 ヘッドパワー」(1968年10月20日)。
黒ダ:これがわからないんです。これが前にお見せしたときにわからなくて、ヘッドパワーかなと前におっしゃった。週刊誌で、さっきの『週刊大衆』と一緒、明治神宮のと同じ記事なんだけど。
末永:これは平田さんの写真?
黒ダ:いや、違ったと思いますね(註:あとで平田写真と確認できた)。(〈告陰〉とは)仮面が違う。たしかさっきのと違うと思いますね。
末永:違うよ。だってこれ、〈ゼロ次元〉でしょう。これ、〈ゼロ次元〉だよ。
黒ダ:これは加藤(好弘)なんだけど。
末永:この仮面も違うし。
黒ダ:じゃあこれは〈告陰〉じゃないということですね。
細谷:「狂気見本市大会」に入りますね。年忘れアングラまつり(1968年11月30日、イイノホール、東京・虎ノ門)。
黒ダ:これは本当の総決算だったやつで。
末永:だから、この時期に「狂気見本市大会」があって、〈薔薇卍結社〉はちょっと違ったけど、あとは秋山さんと〈ビタミンアート〉が一緒にやって。結局、これは68年ですよね。
細谷:ええ、68年の最後ですね。
末永:このあとにかなり万博問題が持ち上がって、それで池袋のアートシアターだったかな、「ブラック・フェスティバル」をやってるんですよ。「池袋ブラック・フェスティバル」だったかな(「万博破壊ブラック・フェスティバル」、池袋アートシアター[現・シアターグリーン]、1969年6月8日)。新宿でやった「ブラック・フェスティバル」をさらに進めていこうということで、池袋でブラック・フェスティバルをやって、反万博宣言みたいなものを、たしかそこで出したんです。
黒ダ:12月29日に告陰センター事務所で「告陰 年忘れの宴」ってあるけど、これって、忘年会っぽい感じなのかな。
細谷:「年忘れアングラまつり」のことを先に聞きたいんですけど。
末永:11月の話?
細谷:イイノホールのほう。この写真です。
末永:これ、イイノホールね。
細谷:〈告陰〉としてはどういったことをしましたか。
末永:これ、今の写真あるでしょう。
細谷:これは写真けっこうあります。
末永:もう少し他にもあるでしょう。いい写真あるね。僕が持ってないのもあるよ。
細谷:平田さん(の撮影)。
黒ダ:平田と、あと羽永(光利)さんだったかな(註:羽永写真は雑誌に掲載されたものも含めて現存なし)。
末永:羽永さん撮ってたかもしれない。これけっこうね、〈告陰〉としては演劇的要素をシナリオ的に入れてやったんですね。最初は会場を巻き込んでお神輿を作り。
細谷:会場を練り歩く。
黒川:この場面は全部〈告陰〉ですか。
末永:そう、全部。おもしろかったんだよ。練り歩いて、舞台の上で儀式的なことをやるっていう。
細谷:指揮者みたいな。
末永:そうそう。このときはバッハのブランデンブルグ(協奏曲)を鳴らして、写真ではちょっと合唱してるような感じなんだけども、音楽だけ流れてるんですけどね。
細谷:指揮棒を振ってるのは末永さんですか。
末永:いや。中村政治(まさはる)。彼は音楽が好きだった。
細谷:中村政治(せいじ)さんじゃなくて、政治(まさはる)さんですね。
末永:そう。それで、このブランデンブルグを使おうということになって。白いのを着た人がいっぱい立ってるじゃない? この日本刀を持って女性と刺し違えてるのが僕なんだけれども。
細谷:そうでしたか。
末永:それでね、刺し違えた瞬間に、ここの舞台に乗ってる10何人の心臓のところから真っ赤な血がダーと流れる仕掛けになってた。
細谷:どうやって出すんですか。
末永:ここ(心臓のあたり)に血袋みたいなのを仕込んでおいて。ちゃんと合図をして、ダッとなった途端に。客から見るとワーと流れて見える仕掛けをしたんですよ。
黒ダ:けっこうインパクトがあったでしょうね。この前の石橋さんのセーラー服、鞭打ちはよく見るけど、こっちよりも……
末永:そう、こっちがピークというか、盛り上がったクライマックスだったので、ここを見せたかったっていう。
黒ダ:じゃあ、これ(鞭打ち)は……
末永:それは導入でした。
細谷:櫓(やぐら)みたいなところで扇を持ってる、あれは?
末永:あれは〈ゼロ次元〉。だからね、けっこう盛り上がった。相当盛り上がったの。
細谷:何人くらいでやったんですか?
末永:15、6人から20人近く。
黒ダ:すごいですね。最大級の儀式。
末永:そう。人を集めて、みんなおもしろがってやってくれたし。だから僕の中で、こうやってもう1回改めて見ると、やっぱり生と死とエロスみたいなテーマがあったのかなという気がしますね。
黒ダ:特にこの死というのが非常にはっきり出てる。
細谷:そうですね、今お話聞いてると。
末永:だから非常に際どいんだけれども、三島由紀夫の『憂国』という映画、あの世界にどこか近い感覚があった。結局、最初〈告陰〉をつくった頃に、横田元一郎は日大の芸術学部の映像だったんだけれども、もちろん足立正生の映画もあり、それで、「三島由紀夫の憂国って何だったのかな、あれは何なんだ」という話はわりと語り合っていたんですよ。
細谷:あの割腹は何だったのかと。
末永:そうそう。だから結局、三島の中では人間というのはやっぱり一人ひとりだけでは社会を作っていけないというか、やっていけないので、彼の概念の中では天皇というものとつながって初めて、男と女も愛し合えるんだというような感じじゃないですか。だから何かこう、彼のもっていた生と死とエロスみたいなものに近い、それこそエロスとタナトスの世界なんだけれども、彼は右から来て、僕たちは左というより、リベラルなアートから来たわけだけれども、でもそのテーマって究極、みんなが抱えてる問題じゃないかなと思ってたので、どうしてもそういうイメージが出てきちゃうんですよね。
黒ダ:この石橋さんの横にいるのは?
末永:僕です。
黒ダ:もう1人いますよね。もう1人出てるんだけど。
末永:これはわからない。
黒川:演出に音楽を使うことはけっこう多かったんですか。
末永:いえ。ちゃんと使ったのはこのときくらいかな。わりと街頭でやることもあるから、あんまりそこでは使ってなかった。ここは完全にイイノホールっていう劇場だから、音響装置があるし、これいけるねっていうことで。
黒ダ:〈ゼロ次元〉でもあんまり音を使ってないんですよ、たしか。屋外でそういう音を出すという機材がまだない?
細谷:室内のものは再現できるかもしれないですね。末永さんがやる希望があればですけど。
末永:そうですね。だからこのときの世界と、「ブラック・フェスティバル」のときの地下道で秋山さんとかがやってくれたんだけど、檻の中から出てきて男女が抱き合ってるシーンとかあるじゃないですか。あれけっこう、自分で言うのも変だけど、映像として見ておもしろいなと思ってるんですよ。
細谷:そう思います。
末永:よくとってあったけどね。だいたい残らないと思ってやってたから。
細谷:一回性のものとして。
末永:そう。
黒ダ:映像もわりと画質よかったよね。16ミリだから。
末永:そうね。
細谷:そのあと、これは鈴木史朗さんの構成・演出で、68年12月8 日、真珠湾不意討27周年忌念反戦衝撃場(中央労政会館講堂)。
黒ダ:いかにも鈴木がつけそうな名前。
細谷:これは『告陰通信』に載っていたわけですけれども、特に記憶はない?
末永:ないです、これは。
黒ダ:〈クロハタ〉絡みで、イイノホールのときの別の写真。これは〈薔薇卍(結社)〉。
末永:そうですね。
黒ダ:これもよく見たら卍だから〈薔薇卍〉だと思ったけど。
末永:そうだと思います。
黒ダ:これ、〈クロハタ〉ですかね?
末永:これ、子供が出てるんだね。
黒ダ:〈クロハタ〉が出たことにはなってるんだけど。
末永:〈クロハタ〉出てたよ。
黒ダ:これかな。
末永:だとしたら、これ松下さん? 他で〈クロハタ〉っていったらさ、わりとメインで出てくるのは松江さんか高原さんしかない。この頃はかなり松下さんが出てたと思う。
細谷:じゃあ、お子さんも松下さんのお子さんですかね。
末永:どうなんだろうね。
細谷:平田さんの写真にもお子さんがいっぱい写ってる。このときのリハーサルの写真があって。
黒ダ:じゃあ松下の可能性が。
細谷:さっき黒ダさんがおっしゃった、年忘れの宴、告陰センター事務所で。これは映画をみんなで上映して見たという?
末永:そうですね。たいしたことないです、これ。わりと内側(メンバー向け)に近いんじゃないかな。
黒ダ:だから忘年会じゃないですか。年忘れの宴ですから。
細谷:それで最後、69年の頭にですね、岡山に行かれてるんですね。
末永:はい。
黒ダ:ただこのへん、データが若干錯綜してるので、そのあとにも岡山のセンイ会館というのが出てきてて、たぶん街中のセンイ会館というところと岡山大学の両方でやったんじゃないか。2月22日と23日というやつが、たぶんこれと一緒だと思うんだけど、でも岡山でやった記憶があるかというのと、これ、能勢伊勢雄関係じゃないかと思うんだけど。
細谷:特に覚えてらっしゃらない?
末永:このへんは特に僕の記憶ではないですね。深くはないですね。
黒川:〈告陰〉としては、大学闘争の場の中に行って何かやったというのは、あまりないですかね? 〈ゼロ次元〉は法政(大学)に行ったりしましたけど。
末永:中央大学だったかな。バリケードの中で……。日大だ。日大のバリケードの中で1回映像を持っていってやった覚えがあるけど、たぶんそれは記録が残ってないのかもしれない。
細谷:それは横田さんの関係ですかね? 日大に行ったのは。
末永:いや、直接横田さんとは関係なかったと思いますね。
黒川:事前の予告もなくフィルムを持って?
末永:うん。結局いろんな場に僕は出かけていたので、バリケードやってるところだって行ってみようかなと思ったりして。そこで集会とかやってるじゃない、中で。そういうときに上映させてもらったりとか、っていうのはわりとあったので、そんな改まって宣伝してやるというのではなかった。
黒川:行ってその場で「じゃあ、やろうか」みたいな。
末永:そうそう。
細谷:封鎖してる中に入って?
末永:うん。
細谷:ちょっと休憩に入る前に聞きそびれてしまったことがあって、バリケード封鎖の中に入っていたときもそうなんですけど、末永さんといわゆる学生の活動家とのやりとり、どういう感じなんですかね? 議論になるんですかね?
末永:非常に議論になりにくいですね。というのはやっぱり、特に初期の全共闘だとね、もうちょっと自由さがあったと思うんですよ。それがだんだん全国全共闘みたいになっていって、組織化され、新左翼が入り、ということになると、個人の感覚よりも組織としてやる。あるいは内ゲバも起き始めてということだから、むしろ真逆ですよね。僕たちが思ってた個としてどう自己解放していくかということではなくて、いかに大学という体制と闘うか、そのためにいかにして自分たちの組織の体制を作るかという。結局、両方とも硬直していくわけだけどさ。だから、議論としては噛み合わないんだけど、まだこの時期だと多少そこで寝泊まりしたりだとか、自由な、ちょっとコミューン的な状況ってあったと思うんですよね。
細谷:学生の中でもアングラに興味があったりとか。
末永:そうそう。だからそういう部分の多少の話はできたけども、それがひとつのうねりとなって、ひとつの運動となってつながっていくというところまではいかなかったと思う。そこまで意識の共有は、なかなかできなかったと思いますね。だから向こうも、こっちのことわかりにくかったと思うけどね。
黒ダ:一応、呼ばれて行ってるんですよね?
末永:呼ばれて行ってるかというよりも、そういうのってどうしても人間関係ができちゃうので、「今日こういうことをバリケードの中でやってるよ」とか「今日こういう集会があるよ」とか、僕たちに限らずいろんな人がそこに入っていたというのは実際あるのよ。歌う人が入っていたりとか。だから、そういうもののひとつとしては関わったりしてたと思うんだけれども。もっと簡単に言うと、やっぱり僕たちが〈万博破壊共闘派〉ということを打ち出して初めて彼らは、これは誤解だったかもしれないけど、ひとつの反体制的な運動なんだなというふうに言葉で認識したことによって、ということですよね。
細谷:じゃあ、その〈万博破壊共闘派〉から休憩のあとに聞いていきたいと思います。
末永:はい、ちょっと休憩。
黒ダ:今68年の話しかしてないのにこれだけ(笑)。
末永:そうだよ(笑)。
黒ダ:すごい重いんだもん。しょうがない。
黒川:この年どうなってるのかなって。
黒ダ:あの68年もようやくできたというか。
末永:それだけ68年という年がね、非常に濃密な。
黒川:世界的にも68年ってよく切り口にされますけれど、末永さんのなかでほかの年と比べて、そんなに違いましたか?
末永:うーん。
黒川:パリ(五月革命)とかいろいろありましたけど、実際のところ日本で68年って……。
末永:ただ逆に、69年がどうだったかと考えたときに、69年はかなり体制側とそれに対する運動が対峙して、究極にグッと角を突き合わせるような状況になって、69年の最後のほうで運動としては潰れていくし、エネルギーも失っていくわけじゃないですか。68年というのはまだね、音楽とかアートとか、文化というか表現の部分と政治的なもの、つまり自己表現と政治的な表現がまだ共存しながら開花していたギリギリの年だったと僕は思っているんです。自分の体験を思い出しても。まだそういう遊びがあり、軽やかさがあった。そういうものがどんどん削ぎ落とされるというか、排除されて、本当に政治的な観念のぶつかり合いになったのが69年の最後のほうだった。それで東大の(安田講堂の)時計台の問題があり、潰れていき、そして(東大全共闘の)山本義隆とか(日大全共闘の)秋田明大が逮捕され(註:山本は9月5日、秋田は3月12日に逮捕)、ということが続いて、もう本当に萎びていった。そこで行き場をなくした人たちが、より過激な連合赤軍のほうに行ったり(註:連合赤軍は1971年7月結成)。アラブ赤軍というのもあったけどね、結局そっちに行ってしまった。日本の中では現場として、それ以上行けなかったというのもあったと思うんですよね。だから、そのギリギリのところが68年。いわゆるカウンター・カルチャーと言われるけども、カウンター・カルチャーっていろんなものを含んでいたわけですよね。社会風俗から始まって、文化、政治、全部が含まれていたのがカウンター・カルチャーだったと思うんだけど、そのカルチャー的な膨らみをもった最後のギリギリが68年だったかな、という感じが僕はしてますね。
黒ダ:なるほど。いったん休憩を。
(休憩)
黒川:〈(万博破壊)共闘派〉からですね。
末永:〈共闘派〉に関して言うと、昨日ちょっと話しましたよね。
細谷:島田恭一さんからバリサイ(バリケート祭)やってるからということでコンタクトがあったというお話だったんですけれども、ちょっと時系列的に確認をしたくてですね。バリサイが始まるのが、黒ダさんの年譜によると、69年4月11日に(京都大学)教養部バリサイ始まるとあって、松田政男講演とか寺山修司を囲む会。このときに行かれているんですかね?
末永:はい。
細谷:実はその前にですね、すでに「万博破壊」という名称で、まず名古屋のシアター36というところで、〈告陰〉は参加した? 69年2月22日。「8(エイト)ジェネレーション+インターメディアショー」。名古屋に行った記憶はありますか。
末永:名古屋に行った記憶はあるんだけど、このとき僕は関わってたのかな。
黒ダ:シアター36って、一応椅子と舞台はあるんだけど、すごく小さな劇場です。シアターサブロクと言ったかな。写真があるな。〈ゼロ次元〉がブランコを使って、(風倉匠の)風船膨らませて、水上(旬)が写ってるんだけど、かなり特殊な演出だから、行ってたら覚えてると……
末永:何か名古屋かどこかのチラシがあった気がするんだよな。これ、ヨシダミノルの名前が出てるから。3月。
黒ダ:それは京都の男爵でやったやつ。
末永:これは覚えてる。
細谷:じゃあ名古屋は……
末永:行ってなかったかもしれない。
細谷:そうすると新宿で寝体(ねたい)、路上で寝たりとか、そういうのは〈告陰〉は参加してたんですかね。
末永:3月23日というやつかな。これ、僕行ってない気がする、たぶん。
黒ダ:何しろ寝体なもので(誰が参加したか写真でもわかりにくい)。別の写真があったな。
細谷:そうすると〈告陰〉として参加するのは(京都の)男爵(1969年3月29・30日)からですかね。
末永:そうですね。男爵は覚えてる。
細谷:「反万博狂気見本市」。写真はこれですね。
末永:男爵ね。はい。
黒ダ:これ、〈告陰〉で間違いないですかね。大きなペニス状のものを。
末永:なんとなく覚えてる。
黒ダ:(裸の上に)ビニールで……
末永:これ覚えてる。
黒ダ:この69年2月から3月にだんだん反万博というのが出てきてるんだけど、のちに〈万博破壊共闘派〉となるのの、その大本、最初というかきっかけが何だったのかがよくわからなくて。イイノホールまではなかったという話ですよね。
末永:そうなんだけど。池袋のさ、グリーンシアター(アートシアター)か何かで。
黒ダ:それはもっとあとです。
細谷:九州(福岡)から帰ってきてからです。
末永:そうなの?
細谷:69年6月8日。キャラバンのときですから。
末永:そうか、そうか。なるほど。だからもうこの68年の、ごめんなさい、69年の春以降、「万博破壊」というテーマがかなり前面に出てきて、反博が始まったという感じですよね、結局。それで散発的にいろんなところで、名古屋とか九州に行ったりしていたわけですよ。それで、さっきの(1968年)6月の池袋の「ブラック・フェスティバル」で、何かこう、何だろうね、『アサヒグラフ』か何かに金坂さんが書いた記事(「狂気の遠征隊(キャラバン)“万博破壊共闘派”京大に入る」『アサヒグラフ』1969年7月4日)にも出てたけど、そのときになんとなく宣言みたいなものを出して、本格的に対峙していくみたいな感じですね。
黒ダ:ここ(男爵のときのチラシ)に(万博破壊第一)宣言が出てるんだけど。だからイイノホールまで全然なかったのに、何かそういう万博破壊という、反万博というのが〈告陰〉とその周辺で起こったというのは、きっかけは何かあったのかなと。
末永:これはね、万博問題だけということで出てきた考え方じゃなくて、70年安保、そして70年万博ということだったわけ。学生とか反戦運動が当然、日米軍事同盟である安保に対峙していくのであれば、一方でアートとか文化のほうは万博に対峙していくみたいな。だから自分たちは万博、反万博で行くということで、要するに70年という年に向かっての、反戦(運動)や学生たちが安保、そして自分たちは万博への問題意識。それは昨日もちょっと言ったけど、学生たちこそが時代を更新していくという意味ではよほどクリエイティブであって、アーティストのほうは何か内向してしまっている。だとしたら、自分たちにとっての安保は万博じゃないかというような考え方が、いろんな加藤(好弘)さんたちとのディスカッションのなかでも語られたわけ。だから政治と文化両面からの70年に向かう動きとして、〈万博破壊共闘派〉という形をとろうということになったんですよ。
黒川:さっき見せていただいた本牧亭の黄色いポスターには「日本元祖儀式屋総出演万国博覧会官許出場決定戦東関東大会その1」と書いてあって、万博という言葉を使っていても否定的なニュアンスがない。
末永:あれは反万博じゃない。
黒川:万博を時事的なネタにしているくらいだった。
末永:そうそう。
黒川:70年安保と絡んで反対という意識が醸成していった時期というのは……。
末永:つまりね、それはどういうことかというと、こっちが仕掛けたのか体制側が仕掛けたのかという問題なんだけどさ。それは言ってみれば、なぜ70年万博なのかということなのよ。つまり、いかに安保の問題から目をそらすかということとしての万博が設定されているわけですよ。どっちも国策だからさ。そこは見抜けるわけじゃない? 怪しいじゃないかと。実は万博と安保はセットになって向こうはやってきていると。万博に対する問題意識というのは、そこではっきり鮮明になっていったわけですよ。だから簡単に言えば、万博の謳い文句というのがあってさ、科学技術による(人類の)進歩と調和ということなわけでしょう。それって結局、テクノロジーによって人間が管理されていく方向に働くわけですよね、国がやる以上は。その目くらましみたいなものに対して、やっぱり目を覚ます方向で何かできるんじゃないかというのが、反博の考え方だったと思うんだよね。普通の人はお祭りやるんだからいいんじゃない?と単純に思ってるわけだからさ。
黒ダ:流れとしてはそれでよくわかるんですけど、すごく唐突感が否めないんですよね。イイノホール68年は〈ゼロ次元〉はガンガンやってきて、そのときは安保も万博も全然出てこないわけじゃないですか。もちろん〈告陰〉のやつは政治的な意味もあったと思うけど、〈クロハタ〉はこの時期なんとなく終わっちゃってますから、68年12月まで本当にある意味でお祭り騒ぎ的なものをやっていて、それがなぜ(反万博を掲げるようになったか)。加藤さんについても言われていることだと思うんだけど、なんで〈ゼロ次元〉が突然政治化したんだろうという。ひょっとして全共闘運動の中でもやっぱり、69年になったら次は70年だという、学生たちの中でもそういう動きが目立ってきたからだという、学生たちの運動の中でそういう変化が……。
末永:学生運動や反戦運動は早くから70年安保というのは目標にしてるわけだから。そこに向かってたと思うんですよ、65年あたりからね。
細谷:末永さん自身は万博の意識というのは69年に入る前からですかね?
末永:イイノホールで「狂気見本市大会」をやった頃までは、そんなには浮上してなかったと思うけど、ただ、ハプニングとかアングラとかっていう文化の新しい流れのなかで自分がものを見ている範囲ではそうだったの。だからそこではあくまで表現としての身体表現とか、新しい表現としての追求をしてたと思うんですよ、自分もほかの人も。だけど一歩引いたところで、いろんな政治的な闘争現場に出かけて行ったりしてるので、もちろん全体の動きというのはわかってるわけですよ。そうすると単なる一分野の話ではなくて、人間としてどういうふうにこの社会的なものを見ていったらいいかというね、ベトナム戦争を含めて、そっちの方向にどんどん日本が足を踏み入れていくという状況があって、そのために軍事同盟を強化するための安保というのが設定されていたのは早くからわかってたし。それまでは僕もデモに行ったり、集会に行ったりして、それでアートはアートで新しいことをやりたくてやってた。でもこれがだんだん自分の中で結びついていくというか、そういうようなことが僕個人の中ではあって。もうひとつは、アートのことを追求していく、アートのあり方というのかな、生き方を追求していくなかで、もうこの時期には万博に協賛していくアーティストがどんどん出てくるわけだよね。いろんなパビリオンの準備に関わったりとかデザインをやったりとか、博覧会だからさ、そっちに行くじゃない? アーティストによってはそこで大きい仕事ができたり、認知度が上がったりということもあって、それほど疑問をもたないままに行っちゃった人も少なくないわけですよ、実際。でもそれっていうのは結局、自分たちが60年代の後半から、アートが商品化されていくことに対する非常に懐疑があったわけだから、そこから見たときにも、これはもう、まさにアートや文化の博覧会なわけじゃない? 陳列されるわけじゃないですか、そこで。完全にそこにアートというものが回収されていく装置にもなってしまう。いつもそうだけど、権力というのはそうやって文化やアートを飼い慣らしながら、それを利用していくわけですよね。それはもう極端な場合で言うと、ナチスの時代にオリンピックをやったり、それを映像に撮らせたりね。レニ・リーフェンシュタールに撮らせたじゃないですか。ああいうふうに、ものすごいプロパガンダ的に文化というのは何度も利用されてきた歴史があるわけよ。それに近いにおいを感じたわけ。だから当然、さっき言ったように、安保とセットで向こうはやってきてる、仕組んできてるということになれば、やっぱり万博はひとつの象徴的なテーマになるということだったと思いますよ。
細谷:男爵があって、このとき金坂さんとかも行って、ずっといろいろみなさん討議されてたのかなと思うんですね。万博に向けて、あるいは反博をどう動かしていくかというのがあって、それで69年のさっきの島田恭一氏の声かけ。バリサイですかね?
末永:はい。
細谷:これは松田政男さんも講演してますけど、覚えてますか。
末永:松田政男が来て何かやってるのはわかってたけど、直接の接点はなかったと思う、その現場では。
細谷:ちょっと流れていきますと……。「フィルムブラック・フェスティバル」も続けてやって、今度は万博粉砕編って69年4月26日(ジャパン・コーポ・シネマ)。このときはもう万博粉砕と言っているんですね。映写会をやって。
末永:たぶん、こうやってちょっとでも場と機会があれば、いろんなものを駆使しながら、ここでは完全に万博破壊のキャンペーン行動に、かなりもう全力投球をみんながする、同じ方向でやるということだったと思いますね。
細谷:それで九州にキャンペーンで行かれるわけですけれども、九州は末永さん行かれた?
黒ダ:69年5月3、4、5日という連チャンで、福岡でやってるんですけど。
末永:九州は僕行ったような気がする。
黒ダ:ただし不思議なことに、黒川さんも〈集団蜘蛛〉をやってるから(北九州市立美術館「森山安英 解体と再生」展図録の編集、2018年)よく写真見てるんですけど、末永さんか〈告陰〉と思われる人が見つからないんです。これ戸畑(5月3日、戸畑文化ホール)なんですけど。
末永:九州に行ったことは僕覚えてるよ。そのときはね、桜井孝身とか一緒だった。
黒ダ:戸畑のときに会場の戸畑文化ホールの近くが警察署だったので、それに対して末永さんが批判した。なんでこんなところでやるんだ、と。
黒川:戸畑のときは〈集団蜘蛛〉が仕切ったんです。会場を押さえたりとか。森山さんが言うには、押さえた会場が警察署の目と鼻の先だった。そのことに対して末永さんがすごくお怒りになったというのを森山さんは記憶していて。
細谷:権力に近い場でやるというのが。公安への対策というか、もっと言うと、ついて来てるというのがあった?
末永:この前後、少しそのあともだけど、かなりヤバいよね、っていうのは情報が入ってたんだよね。それはありえるだろうなというのはみんなわかりながら、多少の警戒はしてたけど、そんな本格的に対策を練っていたわけじゃないと思うんですよ。わりとメディアで週刊誌や何かの取材があって、そういうところって両方と通じてるじゃないですか。だからそういう情報がちょっと入ってきたりして、けっこう狙われてるかもというのがあったですよ。だからきっとそういう議論はあったと思う。
黒ダ:森山氏は警察が近いから選んだわけじゃなくて、たまたまだと思います。たぶん福岡の人たちも反万博運動をやってきた流れをそんなに知ってたわけじゃないから、だからわりと無防備にというか、ここでいいやと、特に問題視しないでやったのかなという気もするんですけどね。
末永:そうかもしれないけどね。
黒ダ:ただそのエピソードでわかるのは、森山さんの話で、とにかく末永さんは確実に戸畑のときにはいたということで。
末永:そうね。
細谷:九州の一連の3日間、「アングラ映画とハプニングの夜」とか続けてやるんですけれども、パフォーマンスをした記憶っていうのはありますか。
黒川:戸畑のときに〈告陰〉らしき写真がまったくないのがすごく不思議。
黒ダ:(写真を見せて)これで誰か〈告陰〉メンバーらしい人がいます?
末永:ちょっとわからないな。これじゃわからないね。
黒ダ:でもこれ、福岡の人に聞いても、加藤(好弘)さんに聞いても、誰だかわからない人がけっこう何人かいるんだよね。秋山とか水上とか〈蜘蛛〉のメンバーとかはわかるんだけど、そうじゃない人たちがいて、それが〈告陰〉かなと思ったんだけど違った。
細谷:〈告陰〉としては何人かで行ったんですかね、九州。
末永:何人かで行った。だから、どうなんだろう。〈九州派〉の人が、桜井さんとか入ってるのが第3日(5月5日)、明治生命ホールがありますよね。その前にも桜井さんは来てはいるけどね(註:同年3月の男爵への桜井の参加は確認できないが、6月11日の京都でのデモに桜井が参加した写真あり)。桜井さんのことはすごく印象が強かったので、そばで一緒にやってるのは覚えてるのね。
黒ダ:これ、前にお見せしたかどうか。これは次の2日目の農民会館(5月4日)。福岡の2日目なんだけど、ここでですね、やっぱりビニールで身体を包んだ男がいて、ビニールって男爵でやってたので、ひょっとしたら〈告陰〉かなと思ったけど違う? これ、誰だかいまだにわからないんですよ。〈ゼロ次元〉関係じゃない。九州関係でもないと。
細谷:行かれたのは〈告陰〉のみなさんであると。何かパフォーマンスをしたという記憶はない?
末永:九州大会の、桜井さんのことをよく覚えてるって言ったんだけど、そのときは名古屋の……
細谷:水上さん?
末永:じゃなくって、岩田さんとか、あのへんと一緒に何かやったのをよく覚えてるのよ。
黒ダ:〈告陰〉単独でやってたのがある? 要するにみんなで一緒にやってたのはあるんだけど、〈告陰〉としての演目というのは覚えてません?
末永:覚えてない。
黒ダ:これ(明治生命ホールの舞台の下で両手を前に挙げて歩く男3人)、違いますよね? この手前で。
末永:これは違う。
黒川:遠征しているわけだから、そんなに大がかりな小道具とか用意できないわけですよね。
末永:わりとその場で簡単に打ち合わせして、それぞれのグループで、ここはこうしようとか、ここは一緒にやろうとか、誰かがちょっとディレクションしてやる程度のことだったかもしれない。九州なら九州でその現場にいる人たちが参加したりしてるわけだから、その場で作っていくみたいなのがあったと思うんですよね。
黒ダ:じゃあ可能性としては、末永さんも中村さんもいたかもしれない?
末永:いたと思います。
黒ダ:その組み合わせだと他にもっといた?
末永:もっといたというのは?
黒ダ:〈告陰〉メンバー。
末永:〈告陰〉のメンバーは石橋さんとかも一緒に行ってたのは覚えてる。
細谷:ちょっと先行きますよ。重要となってくるのがその後の「万博破壊ブラック・フェスティバル」(1969年6月8日)ですね。これ池袋アートシアターで。このときに写真が撮られるというわけですね。
黒ダ:『週刊明星』(「特別取材 全裸で挑戦された吉永小百合と坂本九 『万博フンサイ!』を叫ぶ“芸術的”ゲバ隊の直接行動」、1969年6月29日)に出てという。
末永:(片手あげの写真を見て)これ石橋さんかな。それでね、たぶんこのときから、かなり警察は動向を気にしてたと思う。特に『週刊明星』に出たのは大きかったと思うし、『週刊明星』で取材をしてた、たぶんアイザワさんとかいう記者だったと思うけど、彼のところにもしかしたら警察から何かあったかもしれない。「どうなんだ?」っていう。それでキャラバンがまた行くじゃないですか。そこはずっと警察がついて来てたから。
細谷:公安がついてくるというのはわかっているんですね?
末永:実際パトカーが僕たちの車のあとをついて来てたから。だからこの頃から(公安が)動いてたのはわかりますね。
黒ダ:ちなみに、(片手あげの写真を見て)石橋、これたぶん小山(哲男)だと思うんですよね。
末永:ちょっとわからないな。顔がぼんやりしてて。
黒ダ:こういう髪の毛(金髪? ロングのヘアピース)をつけてて。
末永:そうだね。
黒ダ:これは高橋(美千子)ですよね。
末永:うん、たぶん。だいたいそのへんが〈告陰〉かなという感じだね。
黒ダ:これは中村? わからないか。
末永:かもしれないけど、あまり顔が見えないので。
黒ダ:このときはかなり主要メンバーというか。
末永:そう。
細谷:それでキャラバンに出るというところで、キャバランに出てから、京都でデモというか。
末永:八坂神社、行きましたよ。
細谷:ですよね。そういうデモ行進というか、外で歩いたりするときも警察がずっとついてくるわけですよね。
末永:うん。
黒ダ:これ、このへん(中央手前に「万博破壊」ヘルメットをかぶった女性のいる写真)が八坂神社かどうかわからないけど。
細谷:これ京大じゃないですか。
黒ダ:京大かな。いや、わからない。これとか。
末永:京大かもね、このへん。門かもしれない。
黒ダ:これ、真ん中、末永さんですかね?
末永:かもしれない。
黒ダ:これ(中央手前)、石橋だと思う。これ(その右後ろ)、水上かな。
末永:ちょっとわからないな。
細谷:それでキャラバンに行って、京大の屋上でやりましたね。このときは末永さんは……
黒ダ:上に?
末永:いると思います。います、います。
細谷:で、水上さんがロープで(地上に降りようとした)。
末永:途中から大変なことになっちゃった。
黒ダ:じゃあ、さっき池袋に出てた〈告陰〉のメンバーはキャラバンにも参加してる?
末永:そうです。
黒ダ:ちなみにこれ(京大で片手あげする集合写真2枚)、前にメールでお送りしたけど、わかんない人が何人かいまして。この人、〈告陰〉じゃなさそうですね。
末永:違う。違いますね。
黒ダ:このへんも? 金坂いますね。
末永:そこはね、いないんだよ、意外と〈告陰〉の人が。どういう瞬間の写真だったかわからない。
黒ダ:別行動だったか?
末永:かもしれない。
細谷:ヘルメットはあれですよね、〈告陰〉の羽のやつですよね。
末永:そう。
細谷:あれはどなたでしたっけ。ヘルメットを作ったのは。
黒ダ:ヘルメットを作ったのは(〈ゼロ次元〉の)上條(順次郎)じゃなかったっけ。
末永:そうだったかも。それで、それぞれグループで色違いで(笑)。〈ゼロ次元〉とか〈告陰〉とか書いて。
黒ダ:そうだったんだ。わからなかった(笑)。
細谷:ちなみに色は覚えてますか。どういう色だったか。
末永:〈告陰〉がわりと黒っぽい。白とかで文字が入ってた気がする。
黒川:秋山(祐徳太子)さんが言ってたのは、羽がついている人とついていない人がいたと。平(ひら)のメンバーだと羽がつけられなくて、羽がついてるといいなみたいな(笑)。
末永:そんなことあったかな(笑)。
細谷:秋山さんはなんかあれ(話をおもしろくしている)じゃない?(笑)
黒ダ:いや、それ高橋さんも言ってた。
細谷:でもこれ、上條さんが作ったんですか。
黒ダ:じゃないかな。だってFRPから作った。
末永:おもしろかったよね、この羽はね。全共闘のヘルと違って。
細谷:そうそう。何て言ったらいいか、祝祭的というか。
黒ダ:やっぱりアートになったという。
黒川:そうか、でもグループで色が違ったのか。
末永:そう、違いましたよ。
黒ダ:秋山さんは一人だから別の色だったのかな。
細谷:〈ゼロ次元〉は何色だったんですかね。
末永:何色だったんだろうね。
黒ダ:これ(京都パレードの写真)、末永さんかな。
末永:それ違うね。
黒ダ:これかな。
末永:そっちだね。それそれ。
黒ダ:これですね。じゃあ、このへんは〈告陰〉じゃなそうですよね。
末永:そうね。
細谷:キャラバンから帰ってきて、昨日6・15統一集会に参加したというのはお聞きしまして、69年の6月29日に『週刊明星』の掲載記事があり、末永さんや〈告陰〉メンバーが順次目白署。これは任意同行というよりも、その場で逮捕?
末永:逮捕。いきなり。だからずっと尾行されてたと思うんだよ。事務所を出て、ちょっと食事して、外出たら4、5人くらい、突然取り囲まれて。
細谷:令状が。公然わいせつ罪が?
末永:あと事務所が近かったからさ、事務所に来たんだよ。資料とか何かあるんじゃないかと思って。
細谷:いわゆるガサ入れが入って。
末永:うん。もうそのまま。
黒ダ:そのとき、かなり資料を持っていかれたりしました? 押収というのか。あるいは警戒していて最初からそういうのはしまっていたとか。
末永:一部はね、すでに移動してたと思うんですよ。なんとなくヤバいというのはわかっていたから。でもチラシ類とか、そういうのはやっぱり置いてあるわけだから。ここ(年譜)に書いてあるよね、これ。編集部、警察に証拠物件として資料を提供した、と。
黒ダ:ええ。これは間違いないですね。
細谷:それで調書をとられるわけですけど、どんなやりとりだったか覚えてます? 警察と。
末永:あのね、その逮捕の意味がわかったんだけど、見せられたのがさ、反戦派の学生とか、反戦の活動家、市民も含めての写真だった。
黒ダ:その顔、その人を知ってるかという?
末永:そう。関係あるか、と。だから向こうは、かなりアート系の動きと反戦派が結びつくのを一番警戒していたと思うし、もし結びついてたらまずいなというのがあるから、それを牽制する意味もあったと思うんですよね、逮捕自体が。だから、もちろん知ってても知らないで通すわけだけど(笑)。
黒ダ:本当に知らなかった?
末永:知ってる人もいました。
細谷:それは言えないですよね(笑)。政治運動とアートの動きという、そのつながりをとにかく彼らは知りたかったわけですね。
末永:そう。実際、留置場に入ってみたら、ほとんどみんな学生だもん。反戦デモで捕まった人たちの中に自分たちも入ったということ。だから意図がはっきりしてたわけ。
黒川:(赤瀬川原平の千円札裁判や新左翼関係の弁護を行なった)杉本(正純)弁護士には入ってもらったんですか、結局? たしか『生きのびるためのコミューン』では……
末永:だから面接というかさ、面会みたいなときには彼が来て、そこでできる範囲のアドバイスみたいなのはしてくれたような気がするけども。
細谷:救対(救援対策)で杉本弁護士が入ったということですね?
末永:そうそう。そのへんはヨシダ・ヨシエとか、かわなかたちがちょっとサポートしながら、そういう救援態勢を作ったということだった。
黒川:千円札裁判以来、何かそういうことがあったら弁護士は杉本さんという流れがあったんですかね。
末永:(うなずく)
黒ダ:(反戦活動家らを)知っててももちろん言わないというか、知らんぷりをしてたけど、結局、罰金、起訴とかされなくて?
末永:略式裁判というのがあってさ、罰金、保釈。半月入ってたわけだよ。
黒ダ:14日間と書いてあったから。
細谷:じゃあ勾留延長したんですね。
末永:そうそうそう。こういう軽犯罪でしょう、ある種。だから長いわけよ。その間ずっとそういう取り調べだった。それは相当長時間。
細谷:勾留延長で半月ですか。
末永:うん。
黒ダ:取り調べをするために?
末永:延長したのはギリギリ14日で。14日だよね、2週間だから。
細谷:そうそう。
末永:ギリギリまでってことだったんだけど、実際に行なわれてたことは、朝10時くらいからね、本当に夜8時9時くらいまで取り調べもあったし、あとは検察に呼ばれて、そこでけっこう長く検事の取り調べがあったよね。だから結局、もうこの時期に、そういう反体制的ないろんな勢力をどう取り締まるかという動きがもちろん出てて、とにかく70年の前にやらなくちゃいけないというわけでしょう。
細谷:一掃したいわけですね。
末永:そうそう。その動きの一環だったということだったの。
黒川:〈万博破壊共闘派〉とはどういう考えで何をやっていたんだということよりは、誰々を知っているかみたいな事実確認が多かったんですか?
末永:それももちろんありますよ。それもあるし、〈万博破壊共闘派〉に関わってる他の人もできたら引っ張りたいわけだから、すごい一生懸命押してくるわけだけど、それはもう……
細谷:突っぱねるわけですね。
末永:言えないわけだよね。それで……、今考えるとどういうことだったのかな、あれは。要するに、ああいうふうにメディアを向こうも利用してさ、非常にスキャンダラスな、とんでもない連中が、公然わいせつ罪になるわけじゃない?
細谷:新聞に載るわけですよね。
末永:要するにイメージダウンを図るようなことにメディアも利用されたし、手先みたいなものだからさ。掌を返すわけだから。そうすることによって、70年に向けてのいろんな動きのひとつとして出てきたという本質をいかに隠して、ただのバカ騒ぎをした連中がいたということにしてしまいたかったという。
細谷:そういう既成事実みたいなのを作っちゃう。
末永:そうなの。そういうことだったの。
細谷:それでお聞きしたいのが、それまでは機動隊との肉弾戦というかね、現場でやってたのが、マスメディアがそういうふうに動いてくる。あるいは情報テクノロジーというかね。それが今度は敵になる。目に見えない敵というのをやっぱりそのとき意識されましたか。メディアの存在。
末永:うん。今日の最初に話したように、やっぱり国家権力の暴力装置としてのメディア操作、メディア支配というのはものすごく感じましたよね。だから今すごいリアルでしょう。今のインターネット時代は完全にそうなっちゃったから。当時からそういうことなんだなというのが、よくわかったというのはありましたよね。だから、釈放されてすぐ、また大阪城公園の反博大会(1969年8月7~11日)に出るというのは、そこでちょっとでもこっちも反撃するというかね、そう簡単にはいかないよというのを出すためにも、メッセージとしてあれをやったわけだけれども。昨日もちょっと話したように、やっぱり本当に世の中の変化を生み出すには、直接権力の装置と向き合っても、これは違うんだ、そういうことじゃないとつくづく認識したわけですよ、僕個人として。たぶん他のメンバーも、それは感じたと思う。みんながみんな、僕とか秋山さんとか加藤さんと同じような意識の方向だったかどうかはわからないわけよ。要するに、他のアーティストにとっては、“反万博というテーマのアート活動”をしてた人もいるわけじゃん。だけど、僕とか加藤さんは特に、やっぱり万博というさ、何だろうね、文化や情報を使って人間管理をしていくことに対して、アートとしての問題ももちろんあるけども、生身の人間性やエロスというのがやっぱりそこで封じ込められていくということに対する問題意識があって、特にこの運動をやってるさなかは、そこがものすごく僕とか加藤さんの中で研ぎ澄まされていたわけ、その認識が。だからこそ逮捕になっちゃったと思うんだよ。単なるアートの、おもしろい茶化したテーマだったら、ならなかったと思うんですよ、こういう事件には。少し前にメキシコ・オリンピックで弾圧(1968年10月2日、オリンピックに反対する学生らのデモ参加者を虐殺したトラテロルコ事件)が起きたんだよね。それで向こうは問題になった。だから、そういうオリンピックとか万博とかでテロが起きるということはすでに(権力側は)わかってたわけよ。それのひとつのアーティスティックなやり方として、一種のテロみたいに権力のほうは敏感に察知したんだね。半月も勾留されるって考えられない。2、3日でしょう、そういう軽犯罪だったら。だから僕にとってはものすごくいい体験でしたよ。そうしないとやっぱり次の個人の意識に向ってどう響かせていくかという発想もなかったし、政治の問題も明らかに人間の心というか、精神の問題が投影していて、精神分析の世界でいうと(ヴィルヘルム・)ライヒとかが言ってたようなことに近づいていくわけですよ。だからやっぱり、社会の深層というか、人間の潜在意識、下部構造にアプローチするということなしに、政治の上部構造というのを変えていくことは不可能だということがはっきりした、僕の中で。そういう人間の精神構造が投影されて、こういう権力構造を意識のうえで作ってるに過ぎないわけだから、そこでいくらいじり回してもそれは単なるパワーゲームでしかないという。それは僕が発想を変えていく大きな契機でしたよね。
黒川:万博に対する認識が加藤さん、末永さんとほかの人たちで違いがあったという話がありましたけど、〈万博破壊共闘派〉というのは今の末永さんからご覧になって、運動だったんですかね。政治運動、美術運動、ちょっとよくわかりませんけど、運動体だったのか?
末永:これは適切な喩えかどうかわからないけれども、アメリカでね、ヒッピーのムーブメントがあった。60年代、ビート・ジェネレーションからヒッピーへという文化の展開がありましたよね。アメリカはちょうどベトナム戦争が激化して、ものすごく国内で亀裂が入っていくなかで、ヒッピー的な精神運動、文化運動、プラス政治性をもったヒッピー運動というのが起きたじゃない? それがイッピー(Yippie)ということだったんですよ。だから、ほとんど僕たちがやった万博問題というのは、その言葉をあえて使えば、イッピー的な行動だったと思う。金坂さんも何かにそれを書いてたしね。
黒川:子供の教室は〈万博破壊共闘派〉の時期もやっていらっしゃったんですよね。
末永:だから逮捕されてるときに、教室に来てた子供たちとか親とかビックリして、ええ!みたいな、僕は釈放されたらもう誰もいないだろうなと思った。だってすごいスキャンダラスな記事が、『(夕刊)フジ』(「逮捕された“ハダカの儀式”」、1969年7月18日)とかさ、出たでしょう、大きく。
黒ダ:(記事を見て)これですからね。顔出てますからね。首謀者ですからね(笑)。
末永:それで、もう誰も生徒は残ってないだろうと思ってたんだけど、半分残ってたのよ。ある種、感動でしたね。知ったうえで、続けましょうということで。だから、それはそれとして、ずっとやってきてたわけです。昨日だいぶお話したけど、子供であれ大人であれ、精神構造をどういうふうに解放していくかということと、政治や社会の問題というのは、同じ問題だから。要するに、意識というネガフィルムが投影されているのが社会であって、このネガフィルムが変わらなければ、それが投影された社会は変わりようがないわけですよ。ここの問題として子供のことも大人のセラピーのこともやってたわけだから、それはとにかく継続して、当然やるということで。だからある意味では、僕がやってる子供の場を作り続けることとか、大人のセラピーをやることというのは、うまく言えないんだけど、これは細谷さんがうまく言えるかもしれないけどね、それはすごく僕にとって政治的なことでもあるの、実は。分離してないんですよ、そのふたつは。
細谷:〈PEAK〉に行く前に、反博のもう本当に最後のほうで、山手教会とかで反博ティーチイン(東京プレ反博、7月12日)ってありましたね。このとき、いわゆる学生運動家とやっぱり対立というか、もう噛み合わなかったですか?
末永:全然噛み合わない。要するに、彼らの運動はかなり追い詰められてたし、情勢として。かなり追い詰められて必死な状態になって、余裕がないので、僕たちがやってたことに対して何なんだ、ふざけんじゃない、みたいなさ。そんなおふざけやってる場合じゃないでしょう、みたいに向こうは思っちゃうぐらい、もう遊びがなくなってた。ムーブメントのなかに。彼らの心にもね。
細谷:なるほど。
黒川:逮捕を機に〈万博破壊共闘派〉で脱落した人は特になく、みんな続けて大阪までやろうという雰囲気だったんですかね。
末永:大阪ハンパク(反博)の話?
黒川:はい。逮捕後も継続して、ここでやめちゃダメだという感じだったんですか。
末永:うん。それはやめちゃダメだし、ここで1回反撃しておかなくちゃいけないと。それと〈ベ平連〉との関係があったからさ。〈ベ平連〉が大阪ハンパクをやろうともちかけてきて、やったんですよ。だから、もっとこれはいろんな人に意味を知ってもらわなくちゃいけないというのもあり。けれども、じゃあ、その先にね、その方向性で万博というテーマでどれくらいのビジョンがもてたかというと、なかったと思う、誰も、実は。もう勢いでそこまでやるしかなかったという感じ。それがちょうど69年の終わりになっていくわけで。だから昨日話したので言うと、そこでちょうど、おおえさんのああいう、幻覚共同体ということで彼はやってきたんだけれども、要するに意識、ちょっと硬い言葉で言うと、当時の意識革命的なほうに行かないと、もう物理的革命では限界だということがあったような気がするんですよね。
細谷:〈PEAK〉に移るというか結成に行くんですけれども、〈告陰〉は解散になるんですか。
末永:〈PEAK〉に向かって発展的解散をしたの。このへんに〈PEAK〉の写真があったけど、メンバーのほぼ半分以上が一緒に〈PEAK〉に衣替えした。まったく発想も違っちゃったんだけどね。こういう即席バンドでやって。こういうのは別に、それが音楽であれ何であれさ、もともとパフォーマンスをやってきてるから。普通にやれてるわけよね、表現として。
黒ダ:直前まで〈告陰〉にいたけど、〈PEAK〉に移るときにやめたという人はいなかったんですか。
末永:主要メンバーはやめてないね。石橋さんもいるし、水町もいるし、みんないますよ。ご存知のように、明治公園でやったじゃないですか。ストリート・ファイティング・ロックをやって、それがけっこう海外メディアに取り上げられたりして。大きな政治集会だったし来るでしょう、海外からテレビとかラジオとか。それでたぶん向こうでも伝わったと思うんですけど、そのあと続けていろんなところで、〈ベ平連〉の集会とかにも出ていってやったんだけれども、ちょっとね、対立ほどはいかないけどやはり「何なんだよ」みたいな話になっちゃって。これは清水谷公園かどこか(1970年3月)で、僕たちが楽器を持ち込んでバンド演奏をしたんだけど、〈ベ平連〉の連中が隊列を組んで迫ってきて、もみ合いになりそうな状態だったんですよね。でも、オープンな場なので、いろんな若い人の飛び入りもありました。
細谷:そうですね。だから新しいグループたちが出てきますね。
末永:これなんかも飛び入りだったけど、女優だったりりィが、当時音楽をやってたんだよ。りりィって亡くなったでしょう、3、4年前に。
細谷:ええ、(2016年に)亡くなりましたね。
末永:あと三上寛とかも。僕たちがやってるところにやって来て。
黒ダ:これ清水谷ですか?
末永:清水谷公園。これは日比谷(公園)ですけどね。
細谷:それで新しい、末永さんより下の世代なのかな、〈万歳党〉だとか(も参加した)。
末永:うん。それは代々木公園でやった「人間と大地のまつり」(1971年8月28・29日、代々木公園)の、日本でのわりと本格的なアースデイということで、最初に僕たちがやって。
細谷:ちょっとその前に、砂川反戦(砂川文革反戦祭、1970年7月25~27日)のところを。
黒ダ:その前にちょっと、〈PEAK〉になって、半分〈告陰〉主要メンバーは継続したんだけど、〈PEAK〉になってから入った人たちということで、これ(『PEAK』2号)に出ている人たちの武谷兄弟(明、光)とか、岩渕(英樹)もこのときからですかね。
末永:岩渕さんはね、〈告陰〉の後半にちょくちょく出入りしてた。いわゆる反戦運動の闘士だった。でも何か知らないけどおもしろがって、何かと一緒に行動してました。
黒ダ:岩渕さんはどこか大学のセクトの人だったんですか。そういうわけじゃない?
末永:覚えてない。結局〈PEAK〉もやめて、あとに彼はさらに反戦運動に入っていって逮捕されて、けっこう長い間、裁判闘争をやってたんですよ。そのときに証拠物件として、弁護側のね、10・21の僕のフィルムを裁判で使ったんだよ。つまり彼が映ってるか映ってないかなんだよ。当然映ってなかったんだけど。そういうことにもあのフィルムが、弁護側の資料として。
黒ダ:武谷兄弟というのはどうやってつながってきたんですかね。
末永:武谷(明)君はね、僕の20歳くらいからの友人だったの。黒ダさん知ってるけど、武谷三男の息子。
黒ダ:理論物理学者?
末永:そう。もう本当に湯川秀樹の次と言われたくらいの人ですよ。それでお父さんもけっこうそういうリベラルな学者だったので、『思想の科学』の創刊とかに関わったような人なのね。その息子たち2人と付き合いがあって、特に上の長男のほうとわりと気が合って、普通に友達付き合いをしてよく遊んでる友達だったの。彼は僕が〈告陰〉をやってるときはちょっと離れてた。〈PEAK〉になって音楽とか入れていろいろ楽しい感じでやっていこうよとなったら、また友達付き合いが復活して。でも彼もいろんな雑誌の編集やったりとか、物書き的なことをチラッとやってたけども、ロシア系のお母さんと日本人の武谷さんのあいだに生まれたので、当時はけっこう大変だったんだよ、彼の人生は。だからそれだけものを深く考える、僕にとっては語り合えるすごくいい友達だったんだけど。10年くらい前に亡くなっちゃったんですけどね。でもこのときは一緒に楽しんで、こうやってバンドをやろうよと言うと、下の弟のほうがギターとかピアノとかやってたから、何度か一緒に参加して、明治公園でやったストリート・ファイティング・ロックのときも演奏に加わった感じでしたね。
黒ダ:武谷とは〈告陰〉の前からの友達として?
末永:そう。個人的な友人としてずっと付き合ってた。
黒ダ:どういう接点があったんでしょう? 別に美術つながりじゃないんですよね?
末永:ある友人の紹介で僕の個展(1965年、画廊喫茶マチエールか)に来たんですよ、20歳頃。そこで話してすごい気が合ってしまって、というような関係でしたね。
黒ダ:あとこれ(『PEAK』2号)、マリアとかカズエとかいるんだけど、よくわからないんだけど。
末永:マリアというのは実はね、高橋(美千子)さんのニックネームだったの。
黒ダ:これ、高橋さんでしたっけ。じゃあこれも〈告陰〉からの継続組だったんですね?
末永:そうそうそう。
細谷:ちょっと先行きます。ストリート・ファイティング・ロックは何回かやられたんですね?
末永:うん。いろんなところでやって、砂川のときもそういう感覚でやってたし、あとはわりとキャラバンというか、日比谷から銀座とか、あっちのほうでパレードみたいなことを週に1回とか、チョコチョコやっていたんですよ。だけど今回の話の流れでもわかるように、わりと自由な集団とはいえ、集団でやっていくことの限界。それをまた社会にアピールしたり、社会的にキャンペーンしていくことの限界を僕個人が感じて、というのはさっきも言ったとおり、どうしてもリーダーがいたりそうじゃなかったりということに、人間社会の縮図を感じるんですよね。体制だろうが反体制だろうがどっち側に立っていようが、そうなっちゃうんだなって。それで、もっと個人を対象に響かせていくものをやりたいというのがあって、もう1度改めて子供のアトリエを中心に、子供の絵の分析や何かのほうを深めていきたいということもあった。もっと直(じか)に個として付き合える、そういう対話の中で何かをやっていくという方向に、はっきり僕の中で方向が定まっていったので、逆に言えば、社会という幻想が自分の中でなくなっちゃったということですかね。
細谷:おそらくそれがのちの「SURVIVAL ’72」(1972年2月11~15日、関東学院大学寮)につながっていくと思うんですけど。
末永:それが一番〈PEAK〉としての、ちょっとまとまった、最後のほうのイベントでしたね。
細谷:その前にさっき話した「人間と大地のまつり」があって。
末永:『美術手帖』(1972年2月号)に書きましたよね、僕。
細谷:書きました。文化叛乱というのを(特集「文化叛乱/いま」のなかのグラビア「造反から生活革命へ」)末永さんが構成されているんですけど、松澤宥さんたちの概念、コンセプチュアルな(作品をつくる)人たちも(「人間と大地のまつり」に)参加してるわけですけど、接点はありました?
末永:僕はあまりなかった、松澤さんとはね。名前はもちろん知ってたし、おもしろいことやってるなってわかってたけど、非常にコンセプチュアルなもの、アートの流れのなかですごいおもしろい実験をやってたと思うんですよね。だけど、相当僕の感覚とは違う人だなというのはわかるので。
細谷:そうなんじゃないかなと思ってました。
末永:最近、この何年かね、松澤さんのコンセプトを研究したりしてた女性がいるじゃないですか。
細谷:嶋田美子さん。
末永:ああいう人からいろいろ連絡をもらって、会ったりもしたんだけど。
細谷:(松澤は)おそらく末永さんとは違うんじゃないかなと。一応聞いてみようかなと思ったんですけれども。
黒川:ちなみに、ストリート・ファイティング・ロックのときに末永さんがタンバリンを持っている写真がありますが、奏者として入っているんですかね。
末永:うん、奏者としても入ってる。あとリズムセクションというのはさ、外でやるときは、それこそハプニング的なことがいろいろ起きるんだよ。だから、ああいうものがひとつの合図になって、こっちでやろうとか、音を出そうとか、場面転換しようとか、やりやすいというのもあって、わりとそういうことだったかもしれません。
黒ダ:あと本格的なドラムセットだったら移動しづらいですよね。
末永:大変でしたよ。あのときは一応ドラム持っていったんだけどね。ドラマーもいたんだけどさ。
黒ダ:基本的にはギター……
末永:ドラム、ここにあるでしょ。
黒ダ:ドラムしっかりあるわ。
黒川:キーボードもありますもんね。
末永:あります。キーボードも運んだ。
黒ダ:本格的ですね。
黒川:電気はどうしたんですか。
末永:電気は発電機で。あとこのとき、武谷(明)君が協力してくれてたので。武谷君の家ってね、わりと有名な総合病院なの(母ピニロピが開設した武谷病院)。それでね、そこにある救急車を出してくれたの、彼が。内緒で。
黒川:それ、本(『生きのびるためのコミューン』)にありましたね。
細谷:それで中に向かって突破したと。
末永:そうしないと入れなかったの。明治公園が全部機動隊に囲まれてて。でも救急車だと機動隊も「はい、どうぞ」みたいな感じで。
細谷:今じゃ考えられないことですね。
黒川:救急車の中を見なかったんですね。中を見たら楽器ということですよね。
末永:うん。こっちは半分遊びですけどね。
細谷:でも本気で遊んでるわけですもんね。それで先行っちゃうと、〈PEAK〉の活動としての最後、フリーゼミナールを何日か逗子でやられて(1972年2月11~15日、関東学院大学寮)。
末永:あのときに金坂さんとかゲイパワーの東郷健とか小沢遼子とか、詩人の諏訪優とかいろんな人が参加しました。諏訪優さんは僕の本(『生きのびるためのコミューン』)の中で最後に対談をしてくれた。あれはわりと彼がちゃんと話してくれた。彼はアメリカのビート詩の紹介者だったし、あの時代のことをよくわかってたんだけど、諏訪さんも(フリーゼミナールに)来てもらって。
細谷:『ニューヴァーブ』って(ミニコミ誌を)山形でやってた菅原(秀)さんは?
末永:彼はもともと音楽系の人だったんだけど、僕の新聞や何かを見て感じるものがあって、出入りするようになって、しばらく、けっこう長く付き合ってましたけども。
細谷:もうずっと山形にいらっしゃって?
末永:途中から東京に来てたみたい。しばらく会ってませんけど。もう10年近く会ってないかな。
細谷:田中美津さんともこの頃ですか。
末永:田中美津さんはね、直接会って講座に来てもらったりとか、僕、1980年ちょっとの頃、1981、2年の頃なんだけど、共同通信の記事の企画をしてたことがあったのね、何かバイト的に。知り合いの記者、編集委員がいて。
細谷:それは末永さんの名前で?
末永:うん、出てたかもしれない。あとでコピーを見せるけど。そのシリーズの中で田中美津さんを取材するというのを僕が出して、田中美津さんに直接会っていろんな話をしたり、昨日ちょっと話しましたよね。ウーマン・リブの話と当時のムーブメントがどういう関係だったかというのを話したと思うんだけれども、それで田中美津さんとすごく通じるものがあって、1981年当時、僕がやっていたイメージファクトリーというスペースにゲストとして来てもらって、話をしてもらったりとか。これが毎日新聞の「街の学校」という記事(1981年8月20日付)になりました。そのあと、たまたま僕が2、3年後に体を壊してしまって、彼女は鍼灸師なので。彼女(途中からインタビューに同席したハート&カラー・プロデューサーの江崎泰子)もそうなんだけど、一緒に鍼灸院にかかったことがあって、ずいぶん助けられました。
細谷:この頃やっぱりヒッピーのある種ブームというか、「部族」とかいろんな人たちが、山であるとか、あるいはいろんな島……
末永:吐?喇(トカラ)列島とかね。
細谷:生活共同体というふうにいくわけですけれども、末永さんはこの本もそうですけれども、都市共同体にこだわったというか、そこに行くじゃないですか。
末永:「部族」とか当時のコミューン志向みたいなものがありましたよね。いろんなところに山岸会とかもちろん「部族」の人がいるところ、長野とか僕は回って、本(『生きのびるためのコミューン』)にも書いてますけども、接触もあったし、いろいろ一緒にやったんだけど、僕がベッタリと共同体志向にならなかった理由をあとから考えたことがあるのよ。どうしてかなと。彼らと交流しながらも、なぜ僕はそっち方向に行かなかったのかなと思ったときに、たぶん僕がずっと絵を描いてきたということ、子供の頃から。要するにアートの世界で生きてきて、そういうものを作り出す、手を使って何か道具を使ってものを作り出すというのがもともとのアートの語源じゃないですか。だから人間というのはアートをする人だと僕は思ってるわけ。もっと言うと、人工的に何かを作る生き物だと思うんですよ、人間は。もし人工的に作る能力がなかったら滅びてると思います、すでに。だけどやっぱり道具を使い、表現をし、記号を使い、アートと言ってもいいんだけど、それをやることが人間なんだ。当然、そこで起きてくる問題とかもちろんありますよね。だけどそれを受け止めて、どう生き延びていくかというのが、僕は人類の課題かなと思って。僕なりだけど。その発想のルーツに、ずっと絵を描いてきたということは、たぶんあるだろうなと思うんですよ。だから、むしろ自然か都市かということじゃなくて、何かを生み出していくということが、僕の質みたいなものを作ってるのかなと思ったことはあります。あとから考えて。しかも、創造活動というのは究極は個人の世界だと思うし。
黒ダ:実際には、見せるとか普及するというのは措いておいて、ただものを作るということだとしたら、むしろ都市化以前の人間というのは田舎でものを作ってきたわけで、別に材木使って何か作ってもいいし、あるいは木彫りやってもいいし、織物やってとか、自然の中のより原始的な共同体の中でも、ものは作ろうと思えば作れるんだけど、ただ僕が知る限りでは、「部族」とかあのへんの人たちはもの作りにあまり興味がないんですよね。だから、せいぜい作ったってサイケデリック・ポスターとかで、それってアメリカ直輸入の、別に特別珍しくも何ともないやつなので。だから僕はそれ(「部族」らの芸術活動)を調べたほうがいいかなと思ったときに興味を失ってしまったのは、やっぱり生活そのものが大事で、生活の仕方が大事で、ものを作っていくことに興味がなかったのかなという感じがあって。
末永:だから黒ダさんが今おっしゃったように、僕の中にはそういう自然主義的なものとか自然幻想がやっぱりないんだよね。
黒ダ:それは経験的にというか、そういうことなんですかね。わりと都市で生きてきたという。
細谷:生まれ育った環境が。
末永:生まれ育ったのが長崎というのはある意味、江戸時代から国際都市だったので、そういう環境も関係あるかもしれないけど、今黒ダさんが言ったみたいに、地方だったり、自然の中で何かを作っても生活することはできる。生活するために何か作らなくてはいけないけど、それはまださ、自然主義的な感じがするんだよね。アートというのはさ、過剰なものじゃない? 別にアートがなくても生きていけるよという人のほうが多いわけで、過剰なんですよ、何か。人間って過剰な生き物だと思うんですよ。それはたぶん脳がすごく働くようになり、言語をもったことによって、物事をどんどん過剰にイメージしたり作り出していくのが、人類のもって生まれたものという気がするのね。要するに言葉というのは、いろんなものに名前をつけて、カテゴライズして、過剰にいろんなものを言語によって発見して作っていく作業ですよね。それが人間なんだろうなと僕は思うんですよ。そうするとね、僕は田舎のほうにしばらく行ったりなんかしても、最初はいいんだけど、すぐ退屈しちゃうのよ。それは過剰なものがないわけ。だから自分の脳なり全身が生み出す過剰な何かをどうやって消化して生きるかということはすごく感じるので、だとしたら自然の中に行かなくてもいいというか、そうじゃないほうが、むしろ自分が活性化されるというかな。代謝が起きる、ちゃんと。そんな感じがしますけどね。
細谷:そうすると、加藤さんとか宮井さんとかはインドに行って、ヒンズー教に関心をもつとかありますが、今おっしゃったようなところでやっぱり末永さんはそっちに行かなかったというところですかね。
末永:そうですね。
黒ダ:インド行かれてなかったですか。
末永:僕は行ってない。
黒川:行こうと思ったこともないですか。
末永:うん。別の意味で行ったけどね、ずいぶんあとに。インドには、ちょっと話がまた、どうしよう。話があっちこっちいって、わからなくなっちゃうと思うんだけどさ。じゃあ、ちょっとだけいい?
細谷:どうぞ、どうぞ。
末永:話はそれるけれど、実はね、89年ちょっと前くらいからお付き合いのあった写真家がいて、内藤忠行さんという人がいるの。有名なのがこの浜野安弘と作った『地球風俗曼陀羅』(浜野安弘構成・文、内藤忠行撮影、神戸新聞総合出版センター、1989年)というね。
細谷:その本、久しぶりに見た。
末永:モンゴロイド文化圏のいろんな文化とか風俗みたいな歴史を。これはものすごく当時話題になったんですよ。その後、彼はいろんなテーマで、「ジャズ」や「桜」とか、いろんな写真集も出してる人なんですよ。僕はたまたま『色彩自由自在』を作るときに、カラーページをどうしようかというときに、君(江崎)だったよね、たぶん? 「内藤さんの赤い布の写真がいいよね」と言って。
江崎:うん。
末永:それで内藤さんに会ったんですよ、写真を使わせてほしいって。それがきっかけで彼とお付き合いが始まったわけですよ。それで彼も僕たちが(1989年から)やってる色彩学校のこととかおもしろがってくれて、一緒に韓国に色彩のフィールドワークに行ったりとか、メキシコとかグアテマラに行ったりとかして、世界を回りながら、世界の色彩文化を通して何かを表現していこうという作業を彼と始めたの。ちょっといい言葉が浮かばないんだけど、ある意味、色彩論から見た文化人類学みたいなことをやりたいと思ったわけ。フィールドワークとしていろんなところに行ったんですよ。その中でインドにもしばらく行って、いろんなところの記録をとったり写真を撮ったりして、向こうの人の色を通してのいろんな文化の話を聞いてみたりとか、取材をしたりしてた流れがあった。それはインドだったりバリ島だったり、そういう目線でフィールドワークとして行くという。だから結局、僕たちがやってる色彩のことというのは、子供から始まって一般の大人、アーティスト、全部含めて、個のアートとして見る色彩と、一方で、こういう民俗文化とか伝統文化の中にある色の意味をどう見出していって、それがどういうふうに文化を形成しているかというね。個と文化という、いくつかの層で色をとらえ直したいという、僕は当時そういう意欲をすごく感じていて、それでいろんなところを旅行して、やっていたということがあったんです。
黒ダ:そういう観点から(世界の)いろんなところを回られたということですね。
細谷:それでフリーゼミナールがあって、〈PEAK〉は解散というふうになるんですか。
末永:そうね。ほとんど1年半くらいで解散した。やってるときもね、僕は当時、新宿の西落合のアパートに住んでたんですけど、子供ができた頃で、その生活の場が溜まり場になっちゃって、一緒にパレードをやったりしてた連中もよく遊びに来たり、また地方から訪ねてきたりというのがあったんですよ。「SURVIVALフリーゼミナール」をやったこともあって、全国から集まりましたからね。それで、僕のアパートで、今で言うアートセラピー的なこともやって、みんなで絵を描いたりして、それについてセッションをしたりということも、具体的に始めていっていたということもあって、だんだん僕の活動がより個人レベルで対話するという方向にいった。もうグループとしてバーンと何か打ち出してやるということから僕は手を引いていくというか、そこは非常に意識的にシフトしていったということですね。
黒川:じゃあ〈PEAK〉は発展的解散というより、それぞれが個の活動に入っていったということですかね?
末永:そうですね。そう思ってもらっていいですね。
黒ダ:自然消滅というか。
細谷:先ほど出た岩渕さんの事件とは関係なく?
末永:関係なかったです、直接は。ただ、人間関係はありましたから、何かできることはないかなと思って、彼の裁判のときに。だから記録フィルムをちょっと貸してと言われて。
細谷:なるほど。もうちょっとだけなんですが、この頃、このファミリーという言葉がね、ある種はやったというか、言葉として出てきたと思うんですけれども、昨日見せていただいた「全共闘と家族」というあの本(前出『思想の科学』、1979年3月)のページにも書かれていましたけど、末永さんはファミリーというものにどういう見解があるのかなと思って。
末永:それはね、いわゆる血縁の家族ということじゃなくて、むしろ血縁を超えた精神的ファミリーという意味での、つまりコミューン的な、それもベッタリじゃない、個々に生きながらつながるという関係がすごく当時あったので、それこそ都市コミューン的な感じで。僕のアパートとかはわりとみんなが集まって泊まっていったりとかしてたので、そういう精神の共同体みたいな意味合いでのファミリーですね。
黒ダ:でもそのことと、すぐ前に言われた個人の活動、お子さんもできて、個人の活動とか自分の色彩性というほうに行きたいというのと、今言った血縁を超えたコミューンとしてのファミリーというのは、やっぱり同時には成立しないですよね?
末永:それは個々人によってどうとらえるかというのは本当に一概に、断定的に言えないんだけれども、みんな集まってきて、いろいろそうやって語り合ったり、場を共有するってことは、当然、自分の血縁の家族に疑問があるからなんですよ。非常に息苦しさを感じていたり、親子関係に悩んでいたりするわけですよ、みんな。それは永遠のテーマだろうけど。だから、どうやって自分がよりよく、自分らしく生きられるかということを追求する場として、僕もワークショップをやったりしていたので、そういう意味での血縁を超えたファミリーなりコミューンなりというイメージで僕は当時考えていたんだけれども、今の黒ダさんの問いかけに関して言うと、もうひとつ前に進んで考えると、血縁の家族であっても、本当にそこに血縁を超えた精神的なファミリーなり精神的な関係がもててるか、もててないかということが問題だと思ったんですよ。つまり、今でもいろんな親殺し、子殺しが起きるし、すごい問題が家族の中で、密室の中で起きるわけじゃない? なんでそういうことが起きるのかというと、血縁ということに寄りかかりすぎて、精神のファミリーになってない。つまり“心の友”にまったくなってない、親子とか夫婦とかが。単なる役割とか制度の中で生きてるだけですよね。だから本当はそこで1回解体して、自分を解放するなり確立したうえで、もう1回関係を結び直すのならいいんだけれども、なかなかそこまで家族の中でできないですよね。普通の血縁の家族の中では。血縁というものに依存しすぎちゃって、当然のごとくやってるわけですよ。だからそういうものを求めてた分、当時若い人が僕のところに集まってきてて、自分の心の問題、親の悩みの問題、いろんなことを語り合って、少しでもそこから一歩踏み出す場として、きっかけとして居場所を作っていたという感じですよね。
黒ダ:家出して、どこかそういう田舎で友達とコミューンを作ろうとして、そこでファミリーとかいっても、結局それはもともとの問題を回避してるだけですよね。
末永:そのとおり。つまりそこの精神的な切り替えができてなかったら再生産するんだよ、結局は。疑似家族をまた作ってしまう。
細谷:疑似家族を作ってまた次の世代に。
末永:そうそう。
黒ダ:結局同じことになっちゃうという。
細谷:もうずっと末永さんはそういう形で対話、コミュニケーションをされて。コミュニケーションは20代の頃からお考えになってきて、ずっと今も続けて?
末永:そうですね。そこはものすごく、僕はずっとつながってるテーマのひとつだと思ってて。最近でも色彩学校でワークショップをやったり、ダイアローグというテーマでけっこうやってるんですよね。コミュニケーションと言われるけど、一方的に伝達するだけで対話になってないですよね。モノローグをお互いしてるだけみたいな、行き違ったまま。でも「コミュニケーションしたよね」とか思いこんでいるわけじゃないですか。
細谷:それこそ今のSNSとか。 末永:そうそう。そうですね。だからダイアローグができるかできないかというのは、自分で自分を立たせて、自分の心をちゃんと生きれてるかどうか。それを生きれてない人はダイアローグがありえないですよね。語るべきこともないわけだし、聞くべきこともないわけだから。ただ役割を確認し合ってるおしゃべりで終わっちゃうという。ほとんどそうですよね。だから最近、心理的なセラピーとかワークショップでも「ダイアローグ」という言葉がテーマとしてよく使われるし。たとえば精神疾患の治療でもオープン・ダイアローグという言葉が最近使われるようになったでしょう。それは非常に回復効果があるということが、薬と同等、あるいは場合によってそれ以上の効果があるということが最近日本でも紹介されて、言われるようになったんだけどさ。そういう意味も含めての対話ということ。でもたぶんその前に、僕たちって人と対話する前に、自分と対話してないと、人と対話できないんですよね。自分の中のダイアローグができてないと。それはやっぱり自分の心をとことん見つめて、自分が今何を生きて何を感じたいのかということがわかることからしか始まらないわけですよ。だけど自己対話の能力というのがものすごく破壊されるのが、近代の教育と現代社会だと僕は思いますね。自分と対話しちゃいけないんだから。先生の言うことをただ聞いて服従しなきゃいけないわけだから。自己対話の能力はどんどん芽を摘まれていくわけ。だから自分が何だかわからないから、いつまでも自分探しをしなきゃいけないというね。でも結局、自分探しに役立つ商品をただ買うだけであって、それは。という状況にどんどんなってるじゃないですか。だから、そこから離脱するためには自己対話、そして本当の対話。目的と結論のない対話ですよ。目標や結論がある対話は、政治家はみんなそれをやってるわけで、対話ではなく駆け引きだけですよね、やってるのは。人と人との関係をどう生み出していくかというのが、今特に僕たちがやってるワークショップとか講座の大事なキーワードにはなってる。
細谷:なるほど。〈PEAK〉のあと、80年代、90年代、それこそ色彩学校も始まって、国内でけっこう美術教育というのを美術家がやったりとか、あるいは文化人がやったりとか。末永さんはいろんな見方があると思うんですけど、この人は話せるなという人はいましたか。
末永:たぶんそういうことが話せるのはね、大雑把に言うと、美術関係者以外の人(笑)。というのは、もう美術の世界で何かしら勉強したり、ちょっとでもやれた人はね、どこかにアカデミックなものが染み込んでるし、どっちかというと美術といっても日本の場合はね、日本画は別として、西洋美術ですよ。西洋美術の方法だったり考えだったり歴史を染み込ませているわけですよ。一種の西洋信仰ですよ、日本の画壇をずっと支配してきたのは。もう明治からね、全部ヨーロッパの真似をすることで追いつこうとしたわけだから。そうである限り、美術教育を、当事者である、たとえば子供なら子供の側に立って、自己表現としての表現力を養うという発想自体が出てこないんですよ。いかに美術的な価値のある技術とか方法を仕込んでいくかというね。かつて自分たちがやられたことを子供たちにもやりたがるわけ。子供が絵を描くと、もちろんおもしろそうな絵もあれば、どうでもいいような落書きもあるわけよ。でもどうしても美術の素養がある人はね、子供の絵を美術的に見て「いいよね」って言っちゃうのよ。子供にとって美術的にいいかどうかは、そんなの関係ないよってことでしょう。だからむしろそこから離れてる人のほうが対話ができるわけですよね。
細谷:昨日今日と本当にいろいろとお聞きしてきましたが、長年に渡る文化活動の中で、さまざまな関わりの中で、末永さんが一番大切にしてきたことは何か、そして、これから末永さんが何をしたいかということをお聞きしたい。
末永:これからのことは、そう簡単に言語化すると、ちょっと本当かなと自分で思っちゃうけど、ただ今問いかけてくださったことは、すごく僕にとっても大事なことであって、何を一番大事にするか。大事にしてきたか、大事にしていきたいかということだと思うんですよ。そのことで今僕が思い出すエピソードがひとつあって、東日本大地震のあとに、岩手とか福島とか仙台とか、いろんなところでワークショップをやったり、ボランティアでしたけれども、アートセラピー的な手法を活かしてやってきたんですよね。2年くらいグループを組んで、みんなでやったんだけれども。色彩学校の修了生がアートセラピーの勉強をしていて、すぐ現場でできるという態勢があったので、ボランティア・チームの立ち上げが早くて、震災が起きてすぐ、虹のアトリエ……。何だったっけ。東日本大地震ナントカって名前をつけたよね?(「東日本大震災支援 クレヨンネット」)。それで(岩手県の)大槌町でやったときに、たまたまフジテレビの報道番組が取材に来たのね。取材してて、僕がやってるとことかインタビューとか撮ったんですよ。そこで「末永さんにとって何が一番大事なんですか?」って、同じことを聞かれたのね。そのときに僕は、生きるってことは表現することだし、表現することは生きることという話をしたんですよ。取材する側がすごく腑に落ちたみたいなこと。つまり子供たちが、ほとんどもう大変な被害のあとでね。人が死んだり、いろんなものが破壊されて、凍りついたような表情で動けなかった子供たちが、みんなで紙と絵具をバーと広げてね、それこそボディ・ペインティング的なことも含めて、好きにやらせたわけ。そしたらもうグッチャグチャになりながら笑い始めたんだよね。そこの大槌町の園長先生が、「震災以来、初めて笑いました」と言ったのね。一種の生命が爆発したみたいな、凍りついてたものが解凍されていったみたいな感じがあったと思うんですよね。それがなぜ起きたかって、やっぱり表現したからだと思うわけ。それも言葉だけの表現じゃなくて、全身使って、色を使って、身体を使って、手で触って表現をする。表に全部出してしまうというね。そのときに生命力がもう1回復活していくのを目の当たりにするようなことがあったんですよ。それはいろんなところで、神戸の震災のときにもやってきたし、今回もそうだったんだけど。生きるというのは表現することだし、表現するのは生きることだというのに、ある意味、今の細谷さんの問いかけも、僕はそこに尽きるような気がする。表現するのが人間だし、表現することが生きることだし、表現しなければ生きたことにならないということですよね。そういうふうに思うので、どんな場面であっても、どんな時期であっても、それをやるっていうことで自分もそうありたいし、そしてどうしてかというと、表現というのは同じものは二度とできないんですよ。同じ表現ってできないじゃないですか。印刷でもしない限り(同じものは)表現できない。生身の人間だったら。それでしかも、一人一人全員同じことはできない。同じことをやろうとしても絶対にはみ出て違うものになってしまうというのが、人間のおもしろさですよね。人間の心と生命というのは常に一回性でしかないということと、唯一性なんだというね。もうそこかなと僕は思います。表現だからこそ、それが出てくる。一回性、唯一性が出てくる。何か私たち人間に生きている意味があるとしたら、そこに見出せるのかなという感じがするんですよね。
細谷:もしかしたら一回性という言葉だけじゃなくて、それは〈告陰〉からずっと続いている、常に変わり続けて表現していくということは続いているのかもしれないですね。
末永:たぶん僕の感覚の中ではそうだったと思うんですよ。いちいち意識的、意図的でなくても、その感覚だけで僕はずっと生きてたのかもしれないので、そうなっちゃうんですよね。
細谷:最後にですね、これはオーラルの定番(の質問)なんですけれども、これからいろんな形で美術に、美術というか表現活動を志す人、あるいは生活のなかで表現している人もたくさんいると思いますけれども、あるいは都市に生きる人、若者、そういった方々に何かメッセージがあればお願いできればと思うのと、あと、これだけは言っておきたいということがあればお願いできればと思います。
末永:なかなか一言でキメというのができないですけども、今お話したこととちょっとつながるんだけどね、コリン・ウィルソンが書いた『アウトサイダー』という本(1968年に福田恒存訳で刊行)があるんですけども、彼があの中で、人間は一回生まれきりでそのまま生きていく人と、もう一度生まれ直す人がいるという意味合いのことを言っているんですよ。生まれきりというのは、両親から生まれて、その家庭環境や社会・文化環境を刷り込まれて、作られた人間ですよね。作られた人間として生涯を送ってしまう。だけどもうひとつは、いわば1回死んで、もう1回生まれ直す人がいる。それを「アウトサイダー」というふうに彼は言ってるわけね。だからそれまでの環境や文化の外側に出て、もう1回生きる人、自分を。それが自分固有の生まれてきた意味として生きていくことになるんじゃないかなと僕も思うので、生まれきりじゃなくて、もう1回でも、もう100回でも、生まれ直せる人生かなっていうふうに。それはどこにいても、そういう意識さえ目覚めていれば、気づくと思うんですよ。昨日と同じ自分を生きてるなってふと気づいたときに、その瞬間ハッとして変わるじゃない、人って。だから常に生まれ変わり続けるってことかなと思うんですけどね。どうでしょうか。
細谷:ありがとうございます。
末永:あとはチョコチョコ思いついたら言っていただいて。
黒ダ:質問というかコメントなんだけど、今最後に言われたいくつかのことで、人間の表現とは一回性とか唯一性とかって、誰が言ったか、わからないんだけど、人間のDNAみたいなのっていうのはほとんど同じものがありえないということなので、だから当然違ったものを表現するのは当然なんだということなんだけど。でも実際には、たとえば今時の若い人たちでも、ひょっとしたら子供とかあるいは学校でも、人と違ってると排除されたり仲間はずれにされたりいじめられたり。要するに空気読めないという言葉があって、みんなと同じことをするっていうことが、学校で教わったということじゃなくて、人と違ったことをしてはいけないという、そういうタブーみたいなのが当然のように若い人たちに広がっているんじゃないかと思って、私はそれがすごく嫌で。というのは、私は子供の頃から集団行動ができなくて、登校拒否児だったんだけど、そこで人と違っててもいいという唯一のものというのがアートかなと思っていたんですよね。だけど実際には日本の社会というか、子供や若い人ってそうなってないというか、同じように考えるというか、人が言ったからこう考える。だからそれに対して何かどういうことができるかというと、先ほどダイアローグということを言われたけど、結局ダイアローグをするために自分と対話できなければいけないんだけど、結局そういうことをやってると仲間はずれにされていじめられるとなってくるのかなと。それを一体どうやったら現代社会、今の状態で、今末永さんが最後に言われたことが実際に自分を変えたり人を変えたりできるのかなというのが。
末永:そうですね。それこそ今の話とつながっていて興味深いんだけど、つまり、今AIとか言われてね、ますますインターネットは世界中に張り巡らされて、みんながもう強制的に画一化されて、個人がみんな単なる情報端末になってしまってるという状態があって、たぶん本当に仕事もどんどん変わっていくだろうし、あるいはなくなっていくだろうし、機械で全部替わってできるようになったときに、その状況にどのくらい絶望できるかだと僕は思うんですよ。絶望はすごく大事だと思うんですね。もうダメだと。これじゃもう生きていけないと。これじゃあただの機械じゃないかというね。結局AIができたということは、実は文明というのはすべての人間をAI化するための文明だったと思うんですよ。だったら技術ができたからAIのほうがいいじゃないかと。金がかからないし、ガタガタ言わないしということで。はたしてはっきり認識できるかどうかですよ、その絶望感を。そのことが認識できたときに、じゃあもうやめようと。機械の真似をするのはやめようと思う人がどのくらい出てくるかなというふうな感じが僕はするんですよね。
黒ダ:いったん死ななきゃいけないわけですね。
末永:そうです、そうです。
黒ダ:絶望するというのはいったん死ななければいけない。
末永:そういうことですよね。
黒ダ:どうやったら自分を殺せるかということですよね。
末永:だからね、僕がやってることは本当にささやかなことでしかないんだけれども、なんで子供の場を作ってるかというのは、何でもいいから好き勝手に遊ぶ、好き勝手に表現してみる、おもしろい、表現の快楽に溺れてみるくらいのことを、子供のときにやることの大事さって、すごく僕感じるわけ。それはその子の根っこになるわけですよ。その子が小学校、中学校に行ったときに、集団主義的な画一化の中に入ったときに違和感を感じるから。違和感を感じるためには、自分の感性がないと感じらないわけですよ。無理にそこでやってると、病気になるわけよ。自閉的になったり鬱病になったりするわけよ。で、あえて言うなら病気になったほうがいいと思うんですよ。そこから外れていくわけだから。それで違う生き方を見つけるという人も、少数だけど今出てきているし、良いか悪いかは別として、ああいうアール・ブリュット的なものに関心がいってるというのも、それはまた例によって商品化されていく別の問題は起きているけども、直感的にあれに惹かれる人がいるというのは、自分の中の死んでしまった何かを感じているから、惹きつけるものがあるんだと思うんですよね。だからまず、それが僕が50年ずっと子供と向き合ってきたことの理由だし、さらに大人に対しても、なんで色彩学校をやってるかというのは、姿形は大人に見えても、ほとんどの人間は子供のときと同じようなメンタリティで生きてるんですよ。何も変わってないんですよ。だから、最初のときの子供的な自在な感覚を何かのきっかけで取り戻せる場があればいいなと思ったんですよね。たしかに少数だけど、それで変わっていく人がいるのよ、生き方が。何やってたんだ自分は、と。言われたとおりにやって、ただ苦しんでいたんだけど、結局自分を単に見殺しにしてただけだということに、ある日、色なり絵なり何でもいいんだけど表現をして、その快感を思い出したときに違和感を感じるわけ、この社会に。その違和感からもう1回再出発するっていうか、さっき黒ダさんが言ったように生まれ直すということが始まる場合がある。でもまあ、僕はそんな楽天的にいろいろ考えてるわけじゃないけれども、そう簡単にいくと思わないし。でも自分にできるとしたら、それしかないなという感じですかね。
黒川:さっきの同調圧力にしても、その一方で二極化みたいな現象にしても、どっちも集団心理的画一化からそうなっちゃうところがあるから、それを逃れることによって、どっちでもない道の可能性がどこかにあるのかなという気がしますね。
末永:そうですよね。第三の道じゃないけど、それはありうると思うのね。2日間いろいろ聞いてもらって、今僕が訊かれた話とかやってることが今回のテーマと関係あるけど、実は僕にとっては60年代のときに、その感覚がより開花したということですよ。だからここまで来ないと意味がないわけ、今のこのことを僕はやらない限り。単なる「あのときのアングラ・アートだったよね」というナツメロじゃないわけ。あのときに芽が出たものがあったとしたら、それは常にさ、水をやり光を当てて、もっと違う社会的な畑に作っていかないと意味がない。僕みたいな人間は、ほかにも目立たないところでいろんな多様な人たちがいてやってると思うのね。そうすると、こういう人間が今いて何かやってるということが、実は60年代が生んでくれたものだったという気がするけど、どうでしょうね。
細谷:おっしゃるとおりだと思います。
黒ダ:『肉体のアナーキズム』の中に出てきた人たち、亡くなった人もかなり増えてきましたけど、今もお元気で、かつ、あの時代のスピリットをもって活動してる人ってほとんどいなくて、本当に末永さんくらいかなと。
末永:よく僕が話す、人はなぜ絵を描くのか、表現するのかっていう、人間が一番最初に何かを表現したときの感動とか、発見とか、必然性とか、たぶんあったと思うんだよ、生きのびるために。その原点。そのときは別に美術というカテゴリーもないしさ、多少宗教儀式的なこととしてやった部分はあっただろうけども、商品化もされないわけだしさ。だからそこにやっぱりアートの源流があるだろうなと思う。その源流は実は見え隠れしながら、本当は今までも続いているはずなんですよね。それをどうやって、その地下水を流し続けるかという感じはしますよね。
黒ダ:地下水。
細谷:地下水脈。いったん切りますね。
末永:はい。ありがとうございます。
(了)